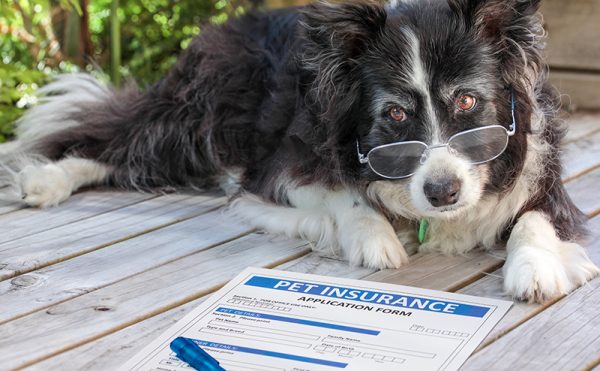ペット保険にはさまざまなタイプがあるため、「どうやって選べばいいかわからない」とお悩みの方も多いでしょう。
この記事では、「ペット保険についてよく知らない」という方のために、保険の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)が、ペット保険の選び方を解説します。
ペット保険の7つの選び方や、保険商品を絞り込む6つのポイント、最終決定前のチェックリストなどを詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- ペット保険を選ぶときは何が大切?
- ペット保険選びで失敗しないためには?
- どの補償割合が一番人気なの?
- 待機期間や免責金額ってどんなもの?
- 犬と猫で重視すべきポイントは違う?
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考にされてください。
ペット保険の選び方はなぜ重要?

なぜ、ペット保険の選び方が重要かというと、犬や猫が突然ケガや病気になったときの経済的な負担をしっかりカバーできるかどうかに関わるためです。また、加入条件や補償内容について理解し、複数のペット保険を比較検討してから契約することで、加入後のトラブルや後悔を防げます。
ここで、あらためて簡単にまとめると、ペット保険とは犬や猫の治療費の一部を保険会社が負担する仕組みです。人間とは異なり、ペットには公的な医療保険がないため、動物病院での治療費は全額自己負担となります。
ケガや病気で通院や入院、手術が必要になった場合には、高額な治療費がかかるケースも少なくありません。そのため、もしものときの経済的な負担を軽減するには、ご自身とペットにあったペット保険を選ぶことが大切なのです。
ペット保険の選び方|まずは7つのパターンから決める

ペット保険の選び方は多岐にわたりますが、まずは以下の7つのパターンに沿って、ご自身のニーズに合った保険のタイプを絞り込んでいくのがおすすめです。
【パターン1】補償範囲で選ぶ(通院・入院・手術)
ペット保険の「補償範囲」は、おもに「通院」「入院」「手術」の3つに分けられます。下記の表でそれぞれの補償内容と特徴をわかりやすくまとめました。
| 補償範囲 | 内容 | 重要ポイント |
| 通院補償 | 診察・検査・処方薬などの通院 | 軽度な病気や慢性疾患などで通院が多い場合に重要 |
| 入院補償 | ケガや病気などよる入院 | 長期入院や重症疾患の備えに重要 |
| 手術補償 | 骨折・誤飲・腫瘍摘出などの手術 | 高額な手術費用をカバーしたい場合に重要 |
入院補償は、入院期間が長引くほど費用が高額になる傾向があり、重症の場合に備えられます。手術補償は、一度の手術で数十万円かかることもあるため、高額治療に備えるうえで重要です。
ペット保険のプランには、通院・入院・手術すべてをカバーする「フルカバー型」と、入院・手術のみを補償する「特化型」があります。
- フルカバー型:通院・入院・手術が補償対
- 特化型:入院や手術の費用のみを補償対象
保険料はフルカバー型のほうが高めですが、補償の幅を重視する方におすすめです。保険料を抑えて入院や手術などの高額治療に備えたい場合は、特化型を選ぶと良いでしょう。
◆通院補償つきペット保険がおすすめな人は?
通院補償つきのペット保険は、「軽い体調不良や慢性疾患の通院費用をカバーしたい方」におすすめです。
保険会社の調査では、犬猫ともに通院が最も多い治療であることがわかっています。具体例として、アレルギー性皮膚炎や外耳炎、胃腸炎など、入院や手術が不要でも定期的な通院や投薬が必要なケースが多くあります。
通院補償があれば、自己負担額を抑えつつ安心して動物病院を受診できるため、日常的な健康管理に役立つでしょう。
関連記事:なぜペット保険で通院補償が必要なの?選び方やおすすめのプランも解説!
【パターン2】補償割合で選ぶ(50%・70%・100%)
ペット保険の「補償割合」とは、動物病院でかかった治療費のうち、保険会社がどれだけ負担するかを示します。保険料と自己負担額のバランスを決める重要なポイントです。
ペット保険では、おもに50%・70%・100%の補償割合が一般的で、まれに補償割合が30%や90%などのプランもあります。以下に、自己負担額のシミュレーションや、人気の補償割合をご紹介します。
◆補償割合ごとの負担額シミュレーション
ペット保険の補償割合が高いほど、飼い主さまの自己負担額は少なくなり、万が一の際の経済的負担は軽減されます。しかしその分、月々の保険料は高くなる傾向があります。
| 治療費合計 | 補償割合 | 保険金額 |
自己負担額 |
| 100,000円 | 50% | 50,000円 | 50,000円 |
| 70% | 70,000円 | 30,000円 | |
| 100% | 100,000円 | 0円 |
たとえば、上記のように、治療費が10万円かかった場合、補償割合が50%であれば自己負担額は5万円、70%であれば3万円、100%であれば0円となります。加入前に十分にシミュレーションを行い、納得のいくプランを選ぶことが賢明です。
※ペット保険商品ごとに定められた日額上限や回数制限などによって、実際の保険金の支払額は変動します。
◆最もよく選ばれている補償割合は?
保険会社や商品によって異なりますが、一般的なペット保険では、補償割合70%のプランが人気を集めています。この理由は、万が一の際の自己負担額を大きく抑えながらも、それほど月々の保険料負担が大きくない、というバランスの良さが挙げられるでしょう。
以下では、補償割合ごとに、おすすめな人をご紹介するので、個々のニーズに合わせて慎重に検討してみましょう。
| 補償割合 | おすすめな人の特徴 |
| 30% | とにかく保険料を抑えたい人。 ある程度の治療費を自己負担できる人。 |
| 50% | 保険料と自己負担額のバランスを重視する人。 基本的な補償があれば満足できる人におすすめ。 |
| 70% | 中程度の保険料で充実した補償を得たい人。 高額な治療費にも備えておきたい人にも。 |
| 90% | 保険料の負担が多少大きくても問題ない人。 自己負担額を極力減らしたい人におすすめ。 |
| 100% | 保険料が高くなっても最大限の安心を求める人。 高額治療のリスクに万全な備えをしておきたい人に。 |
関連記事:ペット保険の補償割合とは?50%と70%はどっちがお得?何割がおすすめ?
【パターン3】年間支払限度額で選ぶ
ペット保険を選ぶ際には、「年間支払限度額」も重要なポイントです。年間支払限度額とは、その年に保険会社が支払う保険金の上限金額を指します。補償プランによって、50万円、70万円、100万円などの上限金額が設定されています。
たとえば、年間支払限度額が50万円のプランで、年間の治療費が60万円かかった場合、保険金は最大50万円までとなり、残りの10万円は自己負担※となります。
※実際の保険金支払額や自己負担額は、ペット保険の各プランによって異なります。
とくに、慢性疾患のあるペットや高齢のペットは、年間を通して通院や検査、治療が多くなるため、年間支払限度額が十分に設定されたプランを選ぶことが大切です。ペットの健康状態や年齢、将来的な治療費を考慮して、適切な年間支払限度額のペット保険を選びましょう。
◆日額や回数制限のないペット保険とは?
多くのペット保険では、年間支払限度額とは別に、「通院は1日あたり〇円まで」「手術は年間〇回まで」といった制限が設けられています。日額や回数制限のないペット保険とは、こうした1日あたりの支払限度額や、年間での通院・入院・手術の回数に制限を設けていないプランを指します。
通院回数が増えたり、治療費が高額になったりしても、年間の利用回数や、1日あたり支払限度額にとらわれないというメリットはあります。ただし、日額や回数制限のないプランは、シニア期に保険料が高くなったり、免責金額が設定されていたりする場合もあるため、注意が必要です。
【パターン4】保険料予算から選ぶ
ペット保険を選ぶ際に「保険料」は非常に重要なポイントです。保険料はペットの種類や年齢、補償範囲、補償割合、年間支払限度額、免責金額の有無などによって変わります。一般的に、補償内容が手厚くなるほど保険料は高くなる傾向があります。
また、ペットの年齢が上がるにつれて保険料も上昇しますが、その上がり方にはおもに3パターンがあります。
- ペットの年齢に応じて毎年少しずつ上がる
- ペットの年齢区分ごとに段階的に上がる
- 一定の年齢に達すると保険料が固定される
保険料の上昇ペースは保険会社やプランによって異なるため、申し込み前に、保険料表はかならず確認しましょう。保険料の安さだけで選ぶと、あとから補償が十分でないと気づく場合もあるので注意してください。
関連記事:ペット保険の保険料の相場金額は?値段が上がらないプランも紹介!
【パターン5】加入条件で選ぶ
ペット保険には、保険会社ごとにさまざまな「加入条件」があります。おもに「ペットの種類」「年齢」「健康状態」が重要な条件です。申し込みをする前に、自分のペットが加入できる条件を満たしているかチェックしましょう。
| 条件 | 内容のポイント |
| ペットの種類 | 犬・猫が基本。うさぎや鳥などは対象外もあるため要確認。 |
| 年齢制限 | 新規加入は生後◯か月〜8歳までなど制限あり。年齢超過は加入不可。 |
| 健康状態 | 持病があると加入不可や補償対象外の可能性。診断書が必要な場合も。 |
ペット保険のおもな補償対象は犬と猫ですが、一部の保険会社ではうさぎや鳥、フェレットなどのエキゾチックアニマルを対象としたプランを提供している場合もあります。
また、多くのペット保険で、新規加入できる年齢に上限が設けられています。一般的に新規加入は7歳~8歳くらいまでとされている保険が多く、高齢のペットは加入が難しいでしょう。
健康状態については申し込み後に、保険会社の審査があり、持病や既往歴などによって、加入ができなかったり、特定の病気が補償対象外(不担保)となったりする場合があります。
関連記事:ペット保険の加入条件をおさらい!犬猫の入れない病気や年齢の条件とは?
【パターン6】終身継続の可否で選ぶ
ペット保険を選ぶ際、「終身継続できるかどうか」は非常に重要です。多くのペット保険は1年ごとの更新制ですが、高齢になると以下のリスクがあります。
- 契約が打ち切られる場合がある
- 保険料が大幅に上がることが多い
ペットは年齢とともにケガや病気のリスクが高まり、治療費も増加します。そのため、ペット保険に加入していない場合は、自己負担額も増えることが予想されます。
犬や猫がシニアになっても終身継続できるペット保険を選ぶためには、「ケガや病気を理由に契約の打ち切りをしない」と明言している保険会社を選ぶと安心でしょう。
関連記事:ペット保険の終身とは?慢性疾患になると継続拒否されて更新できないの?
【パターン7】請求方法で選ぶ
ペット保険の「請求方法」は、おもに窓口精算と後日精算の2種類があります。
| 窓口精算 | 後日精算 | |
| 特徴 | 会計時に保険証を提示し自己負担分のみ支払い | 治療費を全額支払い後、保険金を請求 |
| メリット | 高額治療でも一時的な負担が少ない | 動物病院の選択肢が広い |
| 注意点 | 対応病院が限られるため事前確認が必須 | 一時的に全額立て替えが必要 |
窓口精算は、動物病院の会計時に保険証を提示し、自己負担分のみ支払う方法です。高額な治療費でも一時的に全額支払う必要がありません。ただし、窓口精算ができるペット保険は、保険料が割高になる傾向がある点は留意が必要です。
後日精算は、動物病院で治療費の全額を自分で支払い、後日保険会社に書類を提出して保険金を請求する方法です。Webやスマホアプリから診療明細を送る「Web請求」に対応する保険会社も増えています。
どちらの請求方法が自分に合っているか、を基準にペット保険を選ぶのもおすすめです。
関連記事:窓口精算できるペット保険!アイペットとアニコムどちらが良いか徹底比較!
※上記でご紹介した選び方は目安であり、実際の保険商品の詳しい内容に関しては、各保険会社の重要事項説明書等でご確認ください。
ペット保険の絞り込み|最終決定は6つのポイントで比較

ペット保険を、上記で7つのパターンである程度絞り込めたら、最終決定のために、さらに具体的な6つのポイントで比較検討を進めていきましょう。
【ポイント1】免責金額はある?
ペット保険の「免責金額」とは、保険金が支払われる際に、飼い主さまが自己負担する一定の金額のことです。たとえば、免責金額が5,000円のプランで治療費が10,000円かかった場合、飼い主さまが5,000円を負担し、残りの5,000円に対して保険金が支払われます。
これは、少額の保険金請求を減らし、保険会社の事務コストを削減することで、保険料を抑えるという目的があります。下記にメリット・デメリットをまとめました。
- メリット:月々の保険料を抑えられる可能性がある
- デメリット:結果的に自己負担額が増える場合がある
ある程度の少額なペットの治療費は自己負担で支払い、もしものときの高額治療費にしぼって備えたいという人には、免責金額のあるペット保険が合っているかもしれません。
関連記事:ペット保険の免責って?免責金額、免責期間、免責事由をわかりやすく解説!
【ポイント2】待機期間はある?
ペット保険には、契約成立から補償開始までの「待機期間」が設けられています。これは、保険会社や補償内容、病気の種類によって異なります。以下は待機期間の目安です。
| 傷病の種類 | 待機期間の目安 |
| ケガ | 0日 |
| 病気 | 30日 |
| 癌(がん) | 30日〜90日 |
※保険会社やプランによって異なる場合があります。
待機期間中に発症したケガや病気、またはその期間中に判明した病気は、補償対象外となります。これは加入直前の体調不良や病気を理由に急いで加入する「駆け込み加入」を防ぐためです。
そのため、ペット保険を選ぶ際は、各プランの待機期間をかならず確認してから申し込みましょう。病気がちなペットや子犬・子猫を迎える予定がある場合は、待機期間がないペット保険や、短いペット保険を選ぶことをおすすめします。
関連記事:ペット保険【待機期間なし】は3社!すぐ使えて補償開始が早いのは?
【ポイント3】補償対象外になる傷病は?
ペット保険選びでは、どのような傷病が「補償対象外」なのかも重要です。多くのペット保険で補償対象外となる費用は、ワクチン接種や去勢・避妊手術、健康診断などの予防医療費、美容やケア目的の費用などが挙げられます。
そのほかに、以下のような「ペット保険によって補償の有無がわかれる傷病」もあるので、事前に確認しましょう。
- 歯科治療
- パテラ(膝蓋骨脱臼)
- 椎間板ヘルニア
- 先天性疾患・遺伝性疾患
- 夜間診療などの時間外診療費
ペット保険の約款や重要事項説明書などをよく読み、小型犬ならパテラ、猫なら歯科治療など、愛犬・愛猫のなりやすい病気が補償対象に含まれているペット保険を選ぶと安心です。
関連記事:ペット保険で補償対象外になるのは?ワクチンや療法食、サプリメントは適用外?
【ポイント4】特約の内容は?
ペット保険には、基本補償に加えて、特定のリスクに備える「特約」が用意されている場合があります。おもな特約には以下のようなものがあります。
- ペット賠償責任特約
- ペット葬儀費用特約
- 飼育費用補償特約
多くの特約は、追加の保険料を支払うことで任意で付帯できるものですが、契約時に自動的に付帯される特約もあります。
ペットの性格や生活環境、備えたいリスクに応じて、必要な特約を選択しましょう。特約を活用することで、基本補償だけではカバーできない幅広いリスクに備えられます。
関連記事:ペット保険の特約って何?ペット賠償責任特約は必要なの?
【ポイント5】どんな割引制度がある?
ペット保険の保険料を抑えるために、各保険会社が提供している「割引制度」についても確認しておくことが重要です。これらの割引制度を上手に活用することで、年間の保険料を節約できる可能性があります。
| 割引制度 | 内容 |
| インターネット割引 | オンラインで申し込み完了で適用 |
| 多頭割引 | 複数のペットを同一保険会社で契約すると割引 |
| 無事故割引 | 一定期間保険請求がない場合に適用 |
割引制度や適用条件は保険会社ごとに異なるため、複数のプランを比較する際には割引の有無もかならずチェックし、実質的な保険料で検討しましょう。
【ポイント6】付帯サービスは充実している?
ペット保険には「付帯サービス」が用意されている場合があります。これは契約者が受けられる相談窓口や優待特典などのことで、保険選びの際にはこれらも重要な比較ポイントです。代表的な付帯サービスには以下のようなものがあります。
保険会社によって内容が異なりますが、代表的な付帯サービスには以下のようなものがあります。
| 付帯サービス例 | サービス内容 |
| ペットの健康相談 | 獣医師や専門家に電話・オンラインで相談可能 |
| しつけ相談 | ペットの行動やしつけについて相談できる |
| 健康チェック | ペットの健康を年1回など無料で測定できる |
| 迷子捜索サービス | ペットが迷子になった際に捜索をサポート |
| 優待サービス | ペット用品や関連サービスの割引・特典 |
付帯サービスは飼い主さまの不安を軽減し、ペットの健康管理を助ける重要なポイントです。ペット保険選びの際には、補償内容だけでなくこうしたサービスも含めて検討しましょう。
犬と猫では違う?ペット保険の選び方のポイント
犬と猫では、かかりやすいケガや病気の種類、生活スタイルなどが異なるため、ペット保険を選ぶ際にもそれぞれで考慮すべき点があります。愛犬・愛猫に最適な保険を見つけるために、以下のポイントを確認しましょう。
犬のペット保険選び
犬種によってかかりやすい病気が異なるため、愛犬の犬種特性を考慮したペット保険選びが重要です。たとえば、以下のように愛犬のなりやすい病気が補償対象に含まれているかを確認しましょう。
【犬種別のなりやすい病気の例】
- ダックスフンド・コーギー:椎間板ヘルニア
- フレンチブルドッグなどの短頭種:呼吸器系疾患
- ゴールデン・レトリーバーなどの大型犬種:股関節形成不全
また、犬は散歩などで外出する機会が多いため、誤飲・誤食や交通事故、ほかの犬との喧嘩など、予期せぬケガのリスクも猫に比べて高まります。そのため、手術や入院だけでなく、通院補償も手厚いプランを選ぶと良いでしょう。
また、他人への噛みつきや器物損壊など、犬による賠償事故に備える「賠償責任特約」の付帯できるペット保険を選ぶとなお安心です。
猫のペット保険選び
猫のペット保険を選ぶ際には、猫特有の疾患リスクを考慮することが重要です。猫は、一般的に以下のような病気になりやすい傾向があるとされています。
【猫のなりやすい病気の例】
- 腎臓病
- 膀胱炎
- 糖尿病
- 甲状腺機能亢進症
- 歯周病など
これらは慢性化しやすく、長期的な通院や治療が必要となるケースが多い疾患です。猫のペット保険選びでは、通院補償や入院補償が手厚く、年間支払限度額に余裕のあるプランを選ぶと安心です。
もしくは、保険料をなるべく抑えたいという方は、通院補償がない入院・手術費用に特化した猫専用のペット保険を選ぶのも良いでしょう。猫は犬に比べて、保険料が安い傾向がありますが、高齢になっても無理なく保険料を支払えるプランを選ぶことが大切です。
失敗しないペット保険チェックリスト
ペット保険選びで失敗しないためには、事前の情報収集とご自身のニーズとの照らし合わせが不可欠です。以下のチェックリストを活用し、後悔のない選択をしましょう。
| 質問 | 確認内容 | チェック |
| Q1 | ペットの種類、年齢、既往歴は加入条件を満たしていますか? | □ |
| Q2 | 補償範囲(通院・入院・手術)は十分ですか? | □ |
| Q3 | 補償割合(50%・70%など)と保険料のバランスは適切ですか? | □ |
| Q4 | 年間の支払限度額や日額・回数の利用制限に問題はありませんか? | □ |
| Q5 | 月々の保険料はご自身の予算内ですか? | □ |
| Q6 | ペットの高齢期の保険料も支払い可能ですか? | □ |
| Q7 | ケガや病気による更新打ち切りの可能性は確認済みですか? | □ |
| Q8 | 保険金の請求方法はご自身に合っていますか? | □ |
| Q9 | 免責金額の有無と金額を把握していますか? | □ |
| Q10 | 補償対象外となる傷病や費用を理解できましたか? | □ |
|
Q11 |
割引制度や付帯サービスの有無を確認済みですか? | □ |
| Q12 | 保険会社の評判や口コミを調べましたか? | □ |
| Q13 | 約款や重要事項説明書を読み理解できましたか? | □ |
このチェックリストを参考に、ご自身とペットにとって最適なペット保険を探しましょう。わからない点は、保険会社の公式サイトの「よくある質問」や相談窓口を利用することもおすすめです。
【Q&A】ペット保険に関するよくある質問!
ペット保険に関する疑問は多く、加入を検討する上で解消しておくべき点がいくつかあります。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
ペット保険は病気になってからでも入れる?
基本的に、ペットが病気になってからの加入は難しいのが現状です。申し込み時には、保険会社にペットの健康状態や既往歴の告知が必要で、審査によって加入可否が判断されます。
ただし、すでに完治している過去の病気や、現在抱えている持病などを補償対象外とする「不担保特約」を付けることで加入できるケースもあります。迷った場合は、保険会社に直接問い合わせて確認してみましょう。
関連記事:ペット保険は病気になってから入れる?治療中・先天性疾患の加入条件は?
高齢の犬猫もペット保険に加入できる?
高齢の犬猫でも、ペット保険のプランによっては加入できます。多くの保険会社では新規加入の上限年齢が8~12歳程度に設定されていますが、一部の保険会社には、加入年齢の上限を設けていないシニア向けプランもあります。
ただし、高齢のペットが新規加入する場合、若いペットに比べて月々の保険料が高くなる傾向があるため、将来的に保険料が支払えるかも確認が必要です。
関連記事:ペット保険に加入できる年齢には制限がある?ペットの年齢が不明だと入れない?
ペット保険の乗り換えはできる?
ペット保険は原則1年ごとの更新制のため「乗り換え」は可能です。
ただし、乗り換えを検討する際は、加入条件・補償内容・保険料・待機期間を十分に確認することをおすすめします。契約のタイミングによっては無保険期間が発生して、いざというときに補償が受けられないリスクにつながるため注意しましょう。
連記事:ペット保険乗り換えるならどこがいい?タイミングや見直しポイントは?
ペット保険の掛け持ちはできる?
多くのペット保険で、複数の保険商品を契約する「掛け持ち」は原則として可能です。しかし、複数の保険に加入した場合でも、支払われる保険金の総額が、実際に発生した治療費を超えることはありません。これは、保険の「実損払い」という原則に基づいているためです。
ペット保険を掛け持ちするメリットは補償が手厚くなる点ですが、デメリットとしては保険料の負担が増える点が挙げられます。メリット・デメリットをふまえて慎重に判断することがおすすめです。
なお、掛け持ち不可のペット保険もあるため、事前に調べておきましょう。
関連記事:ペット保険は掛け持ちするべき?おすすめの組み合わせをFPが解説!
まとめ│ペット保険を選ぶときは補償内容をしっかり確認すること!
ペット保険の選び方は、愛するペットとの健やかな生活を長くつづけるために非常に重要な決断です。犬や猫の種類、年齢、健康状態、そしてご自身の経済状況やライフスタイルによって、最適な保険プランは大きく異なります。
まずは、通院・入院・手術の補償範囲、補償割合、年間支払限度額、保険料予算など、大まかな希望を明確にすることから始めましょう。時間をかけてじっくりと事前リサーチを行い、ご自身とペットにとって最適なペット保険を見つけ出してください。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
【ペット保険比較】10秒でカンタン比較
あなたの家族はどちら?
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
種類は?
年齢は?
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田犬
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴犬(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上
- スコティッシュフォールド
- マンチカン
- アメリカン・ショートヘア
- ノルウェージャン・フォレスト・キャット
- ラグドール
- ブリティッシュ・ショートヘア
- ミヌエット
- サイベリアン
- ベンガル
- ラガマフィン