
猫の死因で何が一番多いか知っていますか?愛猫との別れは誰にとっても辛いものです。少しでも別れに向けて心の準備をしておくためにも、この記事では猫に多い死因ランキング10選を詳しく解説し、突然死の原因、老衰との違い、飼い主ができる対策などもお伝えします。
- 猫の死亡原因になりやすい病気は?
- 猫の腎不全ってどんな病気?
- 子猫は死亡のリスクが高いの?
- シニア猫が長生きするためには?
- 家猫と外猫は平均寿命が違うって本当?
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
猫の死亡原因ランキング│最も多いのは腎不全?

猫の死亡原因にはさまざまな病気が挙げられますが、統計によると「腎不全」が最も多いとされています。ここでは、猫の死因のトップ10の具体的な症状や原因を簡潔にご紹介しますので、愛猫の健康管理に役立ててください。
【猫の死因ランキングTOP10】
- 1位:慢性腎臓病
- 2位:腫瘍(ガン)
- 3位:心疾患(循環器系)
- 4位:消化器疾患
- 5位:呼吸器疾患
- 6位:肝臓・胆嚢・膵臓の疾患
- 7位:感染症
- 8位:代謝・内分泌疾患
- 9位: 外傷・事故
- 10位:原因不明・突然死
データ参照①:アニコム家庭どうぶつ白書2023
データ参照②:日獣会誌 75, e128~e133(2022)「動物病院カルテデータをもとにした日本の犬と猫の寿命と死亡原因分析」
猫の死因1位:慢性腎臓病(腎不全)
猫の死因として最も多いのが、慢性腎臓病(腎不全)です。猫全体の慢性腎臓病(CKD)は1〜4%程度※とされていますが、高齢になるほど急増し、10歳以上のシニア猫では罹患率が約22%、15歳以上では数10%にのぼるという報告もあります。
腎臓は、老廃物の排出や水分・ミネラルのバランス調整、造血ホルモンの産生など、猫にとって欠かせない臓器です。腎不全になるとこうした働きが弱まり、全身に悪影響を及ぼします。
※データ参照:National Library of Medicine「猫の慢性腎臓病の管理における経口AB070597の有効性」
◆猫の慢性腎不全とは?
猫の慢性腎不全は、腎機能がゆっくりと低下していく進行性の病気です。一度発症すると元に戻ることはなく、進行を遅らせる治療が中心となります。初期には症状が出にくいのですが、以下のような症状がみられることがあります。
【猫の慢性腎不全のおもな症状】
- 水をたくさん飲む(多飲)
- 尿量が増える(多尿)
- 食欲の低下
- 体重が減る
- 嘔吐
血液検査より早く「飲水量の変化」で気づくこともあるため、日頃の観察が重要です。
◆猫の急性腎不全とは?
「急性腎不全」は、短期間で急激に腎臓の働きが低下する病気で、中毒や感染症、尿路閉塞などが原因になります。猫の急性腎不全の症状は、以下のように急激にあらわれるのが特徴です。
【猫の急性腎不全のおもな症状】
- 食欲の低下またはまったく食べない
- 嘔吐やぐったりして元気がない
- 水を飲まなくなる/逆に多飲になる
- おっしこが減る/まったくしない
- 体温の低下
- 脱水症状
- 呼吸が浅くなる/早くなる
- 口の中からアンモニア臭がする
これらの症状は、数時間〜数日で急激に悪化することがあります。「おかしい」と思ったら、すぐに動物病院を受診してください。
関連記事:猫の腎臓病について徹底解説。症状や治療費、予防法、保険について
猫の死因2位:腫瘍(ガン)
猫の死因第2位は「腫瘍(ガン)」です。特に高齢の猫ほど発症リスクが高く、犬と同様に重大な死因となります。
腫瘍は体のどこにでも発生し、食欲不振・体重減少・しこり・元気がないといった症状がみられることがあります。早期発見・早期治療が重要で、定期的な健康診断がガン予防につながります。
猫の死因3位:心疾患(循環器系)
猫の死因第3位は心疾患で、なかでも多いのが「肥大型心筋症」です。肥大型心筋症は、心臓の筋肉(心筋)が異常に分厚くなり、心臓が正常に機能しなくなる病気です。
この病気は初期には症状が出にくく、飼い主が気づいたときには病状が進行していることも少なくありません。進行すると、呼吸困難、不整脈、血栓症などを引き起こし、猫の突然死につながることもあります。中高齢のシニア猫は特にリスクが高いとされているため、注意しましょう。
猫の死因4位:消化器疾患
猫の死亡原因4位は「消化器疾患」で、嘔吐や下痢といった症状がおもな特徴です。これらの症状は一見すると軽度にみえることもありますが、重度の脱水や栄養失調を引き起こし全身状態を悪化させる可能性があります。
特に、猫の慢性的な消化器疾患は、腸炎や膵炎など、ほかの臓器にも影響を及ぼす場合があります。この病気の原因は多岐にわたり、食事が合わない、寄生虫、ウイルス感染、食物アレルギー、炎症性腸疾患などが考えられます。
猫の死因5位:呼吸器疾患
猫の死因の5位は「呼吸器疾患」で、咳、くしゃみ、鼻水、呼吸困難などの症状が見られます。これらの症状は、猫風邪と呼ばれるウイルス感染症や細菌感染症、アレルギー、気管支炎、肺炎など、さまざまな原因によって引き起こされます。
特に呼吸困難は緊急性が高く、迅速な対応が必要です。症状が悪化すると、食欲不振や活動性の低下にもつながり、重篤な状態におちいる可能性があります。
関連記事:猫の口呼吸は呼吸困難のサイン?病気やストレスが原因の可能性も!
猫の死因6位:肝臓・胆嚢・膵臓の疾患
猫の死因の6位は「肝臓・胆嚢・膵臓の疾患」で、食欲不振、嘔吐、黄疸、体重減少などの症状がみられます。初期症状がわかりにくいため、気づいたときには進行していることも少なくありません。
特に猫の肝臓病は、食欲不振から「肝リピドーシス脂肪肝」を引き起こし重症化することがあります。これは、脂肪が肝臓に蓄積し、肝機能が著しく低下する病気です。
猫の「急性膵炎」では、激しい腹痛や繰り返す嘔吐がみられます。「慢性膵炎」になると消化吸収が悪くなり、下痢や体重減少などの慢性的な症状が続きます。
猫の死因7位:感染症
猫の死因の7位は「感染症」で、ウイルスや細菌、寄生虫など、さまざまな病原体によって引き起こされます。特に子猫は免疫力が低いため、FIP(猫伝染性腹膜炎)や猫白血病ウイルス(FeLV)、猫エイズウイルス(FIV)などが重症化しやすい傾向にあります。
症状は感染する病原体によって異なりますが、発熱・食欲不振・下痢・嘔吐・くしゃみや咳など、全身に影響を及ぼすことがあります。ワクチンの定期接種や、外との接触を避ける猫の完全室内飼いは、こうした感染症の予防に大きな効果があります。
関連記事:猫白血病のインターフェロン治療費はいくら?治療の回数や期間を解説
猫の死因8位:代謝・内分泌疾患
猫の死因の8位は「代謝・内分泌疾患」であり、これはホルモンの異常によって引き起こされる病気です。代表的なものには、甲状腺機能亢進症や糖尿病があります。
猫が「甲状腺機能亢進症」になると、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、活動性が異様に高まる、体重減少、食欲増加、多飲多尿などの症状がみられます。
猫の「糖尿病」は、インスリンの分泌不足や作用不足により、血糖値が高くなる病気で、多飲多尿、体重減少、食欲不振などがおもな症状です。これらの疾患は早期発見と適切な治療により、進行を遅らせることができる場合もあります。
関連記事:猫の糖尿病はインスリン費用が高額?インスリン注射のコツは?
猫の死因9位: 外傷・事故
猫の死因の9位は「外傷・事故」で、特に屋外に出る猫に多くみられる原因です。交通事故、ほかの動物との喧嘩によるケガ、高所からの落下、誤飲誤食などが含まれます。
「交通事故」は猫の死因としてかなり多く、年間約35万頭の猫が命を落としているという報告もあります。外飼いの猫は、室内飼いの猫に比べて平均寿命が2年ほど短いとされています。予防のためには、猫を完全室内飼いにすることが最も効果的です。
猫の死因10位:原因不明・突然死
猫の死因10位は「原因不明の死や突然死」です。診断が困難な場合や、病気が急激に進行して死に至るケースが該当します。突然死は飼い主にとって大きな精神的ショックを与えるため、日ごろからの健康チェックや健康診断が非常に重要です。猫の突然死については次の章で解説します。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
猫の突然死│よくある原因や予兆は?
猫の突然死とは、発病後24時間以内に死亡する内因性の死を指し、外傷や中毒は含まれません。ここでは、猫の突然死のおもな原因や、もしものときに飼い主が気づくことができる予兆、そして予防策について解説します。
猫の突然死のおもな要因
猫の突然死の原因で最も多いのが「心筋症」です。特に「肥大型心筋症」は、初期にはほとんど症状がみられず、飼い主が気づかないまま病気が進行して突然死につながることも少なくありません。
猫の突然死のおもな要因をまとめると以下のとおりです。
- 心筋症
- フィラリア症
- 不整脈・心停止
- 脳血管障害
- 血栓塞栓症
- 高カリウム血症
- アレルギー反応
- 中毒(ユリ、殺鼠剤など)
- 熱中症や低体温症
血栓塞栓症(けっせんそくせんしょう)は、心臓でできた血の塊(血栓)が血管に詰まり、特に後ろ脚の血管を塞ぐことが多い病気で、急激に症状が悪化して命に関わることがあります。
フィラリア症は蚊を介して感染する寄生虫疾患で、突然の呼吸困難や虚脱状態を引き起こし、急死する場合もあるため注意が必要です。
また、重度のアレルギー反応や中毒も突然死の原因となり得ます。特定の植物や薬品、食べ物などが原因でアナフィラキシーショックを起こし、急激に体調が悪化するケースがあります。
猫の突然死を予防するために
猫の突然死を防ぐには、早期発見・早期治療が最も大切です。日ごろから以下のポイントを心がけましょう。
- 定期的な健康診断(血液検査・心電図など)
- 飲水量や食欲、排泄の変化に注意する
- 活動量の変化を見逃さない
- 完全室内飼育により事故や感染症のリスク軽減
- 適切な予防接種やフィラリア予防薬の投与
- 猫に有害な食べ物や植物を部屋に置かない
突然死のリスクを少しでも減らすため、愛猫の健康状態を細かく観察し、異変があれば早めに動物病院を受診しましょう。
猫の死亡原因に見る年齢別の傾向

猫の死亡原因は年齢によって傾向が異なります。ここでは、子猫と高齢猫それぞれの死亡原因の特徴について詳しく解説します。
子猫の死亡原因で多いのは?
子猫の死亡原因で最も多いのは「子猫衰弱症候群(新生子死)」です。特に生後1週間以内の子猫に多く、突然亡くなってしまうことがあります。
子猫衰弱症候群の原因はさまざまで、
- 先天性の異常(心臓病や消化器の問題など)
- 感染症(細菌やウイルス、寄生虫など)
- 低体温(環境の寒さなどによる体温低下)
- 栄養不良(母乳不足や授乳不良)
などが考えられますが、はっきりした原因が見つからない場合も少なくありません。
子猫は体が小さく、免疫力も未熟なため、少しの体調不良でも重篤化しやすい傾向があります。異変に気づいたら、様子を見ることなく速やかに動物病院を受診してください。
高齢猫の死亡原因で多いのは?
高齢猫のおもな死亡原因は「慢性腎臓病」です。慢性腎臓病は一度発症すると完治が難しく、進行を遅らせる治療と継続的な管理が必要です。
また、腫瘍(ガン)や心肥大型心筋症も高齢猫によくみられる死因です。
猫の年齢は人間の年齢に換算すると、
- 7歳は約44歳
- 9歳は約52歳
- 16歳は約80歳
に相当し、加齢にともなって身体機能が低下し、病気のリスクが高まります。シニア期はとくに猫の健康管理をしっかりと行い、健康寿命を伸ばせるように心がけましょう。
猫の老衰による死│最期を穏やかに迎えるには?
猫も人間と同様に、年を重ねると「老衰」によってゆっくりと命を終えることがあります。ここでは、猫の老衰の兆候や、老猫の死に備えるために飼い主ができるケアについて解説します。
猫の老衰による死の兆候
猫の老衰は、人間でいう7歳ごろから少しずつあらわれるといわれています。おもな兆候は以下のとおりです。
- 運動能力の低下
- 食欲低下・体重減少
- 毛並みや毛艶の悪化
- 睡眠時間の増加
- 認知症による粗相や夜鳴き
さらに、死期が近づくと、口呼吸をする、ご飯や水を飲まなくなる、目の焦点が合わなくなる、心拍数が減少するなどのサインがみられることがあります。これらは老衰が進行しているサインのため、見逃さないようにしましょう。
老猫の死に備えるために
老猫の死に備えるために、飼い主ができることはたくさんあります。まず、愛猫が穏やかに過ごせる環境を整えて、下記のようなことに気をつけましょう。
- 清潔で快適な寝床を用意する
- 消化に優しいキャットフードを選ぶ
- 嗜好性の高いウェットフードに変える
- 定期的に動物病院を受診する
- 優しく声をかけて精神的に支える
愛猫が最期のときを安心して過ごせるよう、できるだけそばにいて、優しく声をかけたり撫でてあげたりすることがとても大切です。
【Q&A】猫の死因に関するよくある質問5点!

ここでは猫の死因に関するよくある質問にお答えします。猫の平均寿命や亡くなる前に見せるサイン、亡くなった後に猫の死因を調べる方法などについても解説します。
Q1.猫の平均寿命は何歳?
A1.猫の平均寿命は年々伸びており、2024年のデータでは約15.92歳※です。2000年の約7.9歳と比べると、ほぼ2倍に長くなっています。飼育環境によって差があり、完全室内飼いの猫は平均16.34歳、屋内外を行き来する猫は約14.24歳です。
| 猫全体の平均寿命 | 15.92歳 |
| 外に出ない猫の平均寿命 | 16.34歳 |
| 外に出る猫の平均寿命 | 14.24歳 |
※データ参照:一般社団法人ペットフード協会「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査」
なお、世界で最も長生きしたギネス世界記録を持つ猫は38歳と3日生きた「クリームパフ」で、人間年齢に換算すると約170歳に相当する長寿でした。
Q2.猫が亡くなる前に見せるサインとは?
A2.猫が亡くなる前に見せるサインは、行動や見た目、バイタルサインにさまざまな変化があらわれます。
【行動の変化】
- 口呼吸をする
- ご飯や水を摂らなくなる
- グルーミングをしなくなる
- トイレの失敗が増える
- けいれんやてんかんが起きる
- 睡眠時間が長くなる
【見た目の変化】
- 極端に痩せる
- 毛並みや毛艶が悪くなる
- 目の焦点が合わなくなる
そのほかにも、体温の低下や心拍数・呼吸数の低下など、バイタルサインの変化がみられたら、猫の死期が近い可能性があります。できるだけ穏やかな環境で愛猫のそばに寄り添い、必要に応じて獣医師のアドバイスを受けましょう。
Q3.猫は室内飼いと外飼いで死因に違いはある?
A3.猫は室内飼いと外飼いで死因に明確な違いがあります。完全室内飼いの猫の平均寿命が約16歳であるのに対し、外飼いの猫は平均寿命が約14歳と、2歳ほどの差があります。外飼いの猫は、交通事故、ほかの猫との喧嘩による外傷、感染症のリスクが高まるため、寿命が短くなる傾向があるのです。室内で飼うことでこれらの危険から、少しでも愛猫を遠ざけ守ることができるでしょう。
Q4.猫の去勢・避妊手術をすることで寿命は変わる?
A4.猫の「去勢・避妊手術」は、猫の寿命に良い影響を与える可能性があります。手術を行うことで、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症など生殖器系の病気のリスクを低減できます。また、発情期のストレスや、ほかの猫との接触による感染症、脱走や交通事故のリスクも減少するため、結果的に寿命を延ばすことにつながると考えられています。
Q5.亡くなった後の猫の死因を調べるには?
A5.愛猫が亡くなった後に死因を詳しく知りたい場合、動物病院で病理解剖を行うという選択肢があります。日本小動物獣医師会や大学附属動物病院でも病理解剖を実施しています。
猫の病理解剖は、病気の診断や治療の検証、あるいは感染症の特定などに役立ちます。ただし、費用がかかることや、必ずしも原因が特定できるとは限らないことを理解しておく必要があります。獣医師とよく相談し、納得した上で検討しましょう。
参考記事:動物病理診断センター「なぜ死後検査を行うのか?」
まとめ│猫の死因で最も多い慢性腎臓病を予防しよう!
猫の死因には、腎不全や老衰、心臓病、腫瘍(ガン)、感染症などさまざまなものがあります。なかには突然死のように原因が分かりづらいケースもありますが、症状や前兆を知っておくことで、早期発見や適切なケアにつながる可能性があります。
愛猫の最期を悔いなく見送るためにも、日頃から健康管理に気を配り、異変に早めに気づけるようにしておくことが大切です。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
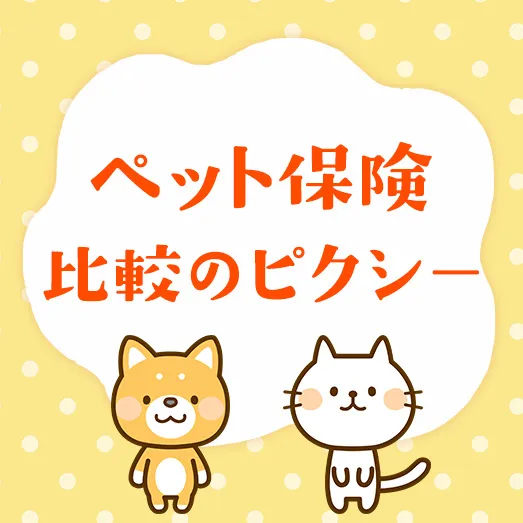
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








