
ぺチャッとした鼻と愛くるしい笑顔でファンも多いパグ。パグを初めて迎え入れるなら、健康に過ごすためのお世話ポイントを知っておきたいですよね。寿命が短いといわれていることから、かかりやすい病気についても把握しておきたいでしょう。
今回は、かかりやすい病気と健康を守るために必要なお世話について紹介します。病気予防のためのポイントをチェックして、長く一緒に暮らしましょう。
- パグの特徴と平均寿命
- パグがかかりやすい病気
- パグのお世話ポイントと健康管理
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
パグの特徴

個性的な表情が魅力的な、パグの容姿や性格などの特徴を紹介します。
容姿
パグは鼻が低くシワの多いところが特徴です。パグのようにマズルの短い犬種を短頭種といいます。フレンチ・ブルドッグやペキニーズ、チワワなども短頭種です。
短頭種ならではのかかりやすい病気やシワが多い犬種のお手入れ方法については、本記事内で紹介していますので、参考にしてください。
パグは筋肉質で引き締まった体つきです。足は短く、後ろ足の筋肉がとくに発達しているため、意外にジャンプ力があると驚く人もいるでしょう。ただし、太りやすい体質のため、理想体重の6〜8kgを大幅に超えないように、管理することが大切です。
性格
パグは人懐っこい性格です。散歩中でも、歩いている人や他の犬に寄っていく姿がよく見られるでしょう。飼い主にも忠実なため、初心者でも迎え入れやすい犬種です。
思いやりがあり自己主張は控えめのため、多頭飼いにも適しています。ただし、食べ物への執着が強い子なら、ご飯の与え方を工夫する必要があるようです。また、活発で運動量は多いため、毎日しっかりスキンシップをとってあげましょう。
被毛
パグの一般的な被毛の色は、フォーンとブラックの2種類です。フォーンとは金色がかった色味で、クリーム色に似ています。この2色以外にも、アプリコットやシルバーを見かけることもあるでしょう。
パグの被毛はダブルコートです。ダブルコートは換毛期があり、春から夏にかけてと秋から冬にかけてなど、季節の変わり目に被毛が生え変わります。この時期は抜け毛が多いため、丁寧なブラッシングが欠かせません。
パグの被毛は短いため、お手入れが楽なのではと思われがちですが、抜け毛が多い犬種であることを覚えておきましょう。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
パグの寿命が短い理由
パグは他の犬種より寿命が短いといわれていますが、これには理由があります。
平均寿命
パグの平均寿命は12.6歳です。犬全体の平均14.2歳より短い傾向にあります。平均寿命が短いひとつの理由は、太りやすい体質であることです。人間と同じく、犬も肥満であるとさまざまな生活習慣病にかかりやすいため、その結果寿命が短くなります。
より長く健康的な生活を送らせてあげたいと考えるなら、食生活に加えて運動や体重管理を心がけましょう。
病気へのリスクがやや高い
パグは体の特徴から、命にかかわる病気になりやすい傾向にあります。とくに呼吸系の病気や、目・皮膚の病気にかかりやすい犬種です。
病気によっては、早期発見により完治できる場合や、完治は難しくても進行を遅らせられる場合もあります。普段の様子をこまめにチェックして、異変があるようなら早めに動物病院を受診しましょう。
パグがかかりやすい病気については次で紹介していますので、病気の内容に加えてどんな症状があるかを確認してください。
パグがかかりやすい病気は?

パグがかかりやすい病気を紹介します。体の部位ごとに解説していますので、毎日のスキンシップで異変がないかチェックしましょう。
パグ脳炎(脳の病気)
パグ脳炎とは壊死性髄膜脳炎の別名で、脳全体に壊死が起こる脳の病気です。発症すると神経症状が確認でき、短期間で死にいたることもあります。初期症状である発作や視覚障害が現れたら、早急に受診しましょう。
重症化すると、
- 同じところをぐるぐる回る旋回運動
- 常に首を傾ける様子
- 無意識に手足をばたつかせる遊泳運動
などの症状が現れます。昏睡状態に陥ることもあり、安楽死を選択せざるを得ないこともある病気です。完治するのは難しいですが、発作を抑えるなどの対症療法を行います。
パグ脳炎は、遺伝的要因で起こるとされているため、明確な予防法がありません。
目の病気
パグのかかりやすい目の病気には、以下の2つが挙げられます。パグは目の露出部分が多いため、目の病気にかかりやすい犬種です。
◆乾性角結膜炎・ドライアイ
乾性角結膜炎はドライアイとも呼ばれます。涙の量や質が低下すると目が乾きやすくなり、角膜を傷つけてしまう病気です。充血したり目ヤニの量が増えたりします。パグのような短頭種は、涙腺の形成不全によって起こることが多いでしょう。
そのほかにも、糖尿病や感染症によって引き起こされることがあります。乾性角結膜炎は予防の難しい病気ですが、点眼薬での治療が可能です。
◆角膜炎
角膜炎は、黒目の表面を覆っている角膜が傷つき、炎症を起こした状態です。角膜の炎症はぶつけることによって起こりますが、短頭種はマズルが短いため、顔をぶつけたときに目が当たりやすくなります。
目を痛がるようなしぐさがみられる、涙や目ヤニが異常に出るなどが主な症状です。重症化すると、角膜が白くなるなどの症状も見られます。
目を強くこすると角膜が傷つくことがあるため、こするしぐさが頻回見られる場合は、受診して目の状態を確認してもらうと良いでしょう。また、他の犬とのケンカで目をぶつけることもあるため、激しいケンカは早めにやめさせます。
角膜炎の基本治療は目薬ですが、炎症した原因によっては、保護用コンタクトレンズの装着や外科手術が必要です。
短頭種気道症候群(呼吸器系の病気)
呼吸器系の病気の中でも短頭種に多い病気をあわせて、短頭種気道症候群といいます。短頭種気道症候群とされる病気は、気管虚脱・鼻腔狭窄・軟口蓋過長症です。
◆気管虚脱
気管虚脱とは気管がひしゃげてしまう病気で、うまく呼吸ができなくなります。パグのような小型犬に多く、乾いた咳や「ガーガー」というような呼吸音を出すなどが主な症状です。対症療法で対応しますが、外科治療によって治ることもあります。
遺伝的な要因が大きいですが、体型や生活環境も影響する病気です。理想体重をキープする、首輪をハーネスに変えるなど、気管に負担をかけないように心がけましょう。
◆鼻腔狭窄
鼻腔狭窄とは、吸い込んだ空気の通り道である鼻腔が狭くなった状態です。「フガフガ」と鼻を鳴らしたり、暑くなくても口を開けて呼吸する様子が見られたりします。
短頭種の特徴による、先天的な要因がほとんどですが、感染症などによって引き起こされることもある病気です。明確な予防法はありませんが、肥満が症状を悪化させる要因にもなるため、太り過ぎには注意しましょう。
◆軟口蓋過長症
軟口蓋過長症(なんこうがいかちょうしょう)とは、軟口蓋(口腔の上奥のやわらかい部分)が、正常よりも長い状態をいいます。軟口蓋が長いと空気の通り道が狭くなるため、呼吸に障害が出るのが特徴です。
- 寝ているときにいびきをかく
- 呼吸が苦しそう、呼吸困難
- 「ガーガー」というような呼吸音がする
- チアノーゼ
- 失神
上記のような症状がみられます。
鼻腔狭窄と同じく、短頭種であることで起こりやすくなる病気です。予防法はありませんが、手術によって軟口蓋を切除して空気の通り道を広くする処置が行えます。
外耳炎(耳の病気)
外耳炎とは、耳介や外耳道に炎症が起こった状態です。腫れたり膿状の液体が出たりして、外耳が正常に働かなくなります。外耳炎はアレルギー性皮膚炎や脂漏性、甲状腺機能低下症などの疾患によって起こりやすい病気です。
定期的に耳をチェックして、
- 外耳が赤い
- 耳垢が増える
- 耳をかゆがる
- 耳が臭う
などの症状があれば、動物病院でチェックしてもらいましょう。洗浄や投薬で改善しなければ、外科手術が必要です。
アレルギー体質なら必要なケアを行う、耳のお手入れを定期的に行い清潔に保つ、などを心がけることで外耳炎になるリスクを軽減できます。
皮膚疾患
パグは皮膚が弱い犬種のため、以下の皮膚疾患にも注意しましょう。
◆マラセチア性皮膚炎
マラセチア性皮膚炎とは、マラセチア菌によって起こる皮膚炎です。マラセチア菌は皮膚にある常在菌で、正常な環境であれば炎症を起こすことはありません。しかし、免疫バランスが崩れるなど環境が悪化することで、皮膚に症状が現れます。
- 皮膚に赤い発疹ができる
- かゆがる
- ベタつきやフケが目立つ
- 毛が薄くなる
などの症状がある場合は、悪化する前に対処しましょう。
マラセチア性皮膚炎は、清潔に保つことで起こりにくくなります。定期的なブラッシングとシャンプー、ぬれたらしっかり乾かすなど、基本のお手入れをしっかり行いましょう。
通常は4〜6週間ほどで完治します。症状の程度によってはさらに期間が必要な場合があり、再発することもあるため、治療が長期間にわたることもあるでしょう。
◆肥満細胞腫
肥満細胞腫は、犬の皮膚にできる悪性腫瘍です。他の臓器に転移することもあるため、早期発見できるかが重要になります。
しかし、初期では症状がわかりにくく、腫瘍がはっきりわかるころには転移していることも多いです。腫瘍があり、同時に吐き気や下痢などの症状がみられる場合は、早めに受診しましょう。
予防が難しく、発見が遅れると命にかかわる病気ですが、初期段階で発見できれば完治も見込めます。内科治療や放射線治療、外科手術など悪性度によって治療内容はさまざまです。
膀胱結石(泌尿器の病気)
膀胱結石とは、膀胱内の尿中に結晶ができ、結石になったものです。尿管結石が膀胱に移動して膀胱結石となることもあります。尿がアルカリ性や酸性に傾くことで起こりやすくなり、遺伝的な要因も考えられる病気です。
膀胱結石は症状が現れないこともありますが、
- 頻尿
- 血尿
- 尿の臭いや濁り(細菌感染が起こっている場合)
などの症状がみられます。いつものおしっこと様子が違うことで、飼い主さまが気づくこともあるでしょう。
尿が結晶化しても結石になる前に対処すれば、膀胱結石になるのを防げる可能性もあります。おしっこの様子を観察することに加えて、健康診断による尿検査で異常がないかを確認しましょう。
結石ができてしまった場合は、結晶の種類によって療法食や手術などで対応します。
熱中症(全身性の病気)
パグのような短頭種は体温調節が苦手なため、熱中症に注意しましょう。短頭種でなくても、犬は体の一部分でしか汗をかけません。体高の低さから、人間よりもアスファルトの熱を感じやすいため、飼い主さまが考えるよりも軽い環境で熱中症になります。
熱中症になると呼吸が荒く体が熱くなり、よだれが多いなどの症状がみられるでしょう。重症化するとチアノーゼや嘔吐などの症状が現れます。
熱中症が疑われる場合は、涼しい場所に移動して、首・脇の下・太ももの付け根などを冷やしましょう。エアコンの効いた部屋に移動させるのもひとつの方法です。飲めるなら水分を与えましょう。これらの方法で落ち着いたとしても、治療が必要な場合もあるため、動物病院を受診します。
熱中症を防ぐためには、室温と散歩の時間帯を工夫しましょう。室温に関しては、次の病気を予防するためのポイントで解説しています。
パグの病気を予防するためのポイント

パグを病気から守るためには、以下のポイントを押さえたお世話を心がけましょう。
体重管理
パグは呼吸障害を起こしやすいため、気道を圧迫しないよう肥満には注意しましょう。パグは太りやすいため、定期的に体重を確認して、生活習慣を見直すのが大切です。食事の量や質は適切か、散歩や遊びなど運動量は足りているかを確認しましょう。
病気以外にも、骨折を防ぐためにも体重管理は重要です。パグはがっしりとした胴体のわりに足が細いため、足に負担がかかりやすい体型をしています。紹介した理想体重を参考に、健康的な体型をキープしましょう。
室温管理
パグは体温調整が苦手なため、飼い主さまが室温を管理しましょう。夏は25度以下、冬は20度以上が目安です。留守番中や就寝中もエアコンを使用して、体調を崩させないように心がけましょう。
シワのケア
シワの多いパグは、シワのお手入れが大切です。お手入れをおこたると皮膚炎につながります。
お手入れのポイントは以下のとおりです。
- ウエットティッシュや蒸しタオルでシワの間をやさしく拭く
- 耳の中や口周りも忘れずに拭き取る
- 綿棒は湿らせてから使う
- お手入れの後は乾いたタオルや綿棒で仕上げる
とくに最後の乾いたタオルや綿棒の使用は大切です。湿ったままにすると細菌が繁殖して、皮膚トラブルを起こします。
定期検診とワクチン接種
病気になるリスクが高めのパグは、定期検診で健康状態をチェックしましょう。定期検診では、血液検査や尿・便検査、レントゲン検査などを行います。普段の生活では気づけないような小さな変化も、定期検診を受けていれば早期発見が可能です。
また、感染症を予防するためにワクチンを接種しましょう。犬のワクチンは2種類あります。狂犬病ワクチンは義務付けられているため、毎年受けなければいけません。一方の混合ワクチンは任意ではありますが、感染症から守るために毎年受けましょう。
正しい生活習慣
健康的な生活を送るためには、生活習慣を整えましょう。若いころからこまめにケアすることは、長生きにつながります。
毎日心がける生活習慣は、
- デンタルケア
- 健康チェック
- 適度な散歩
- 飼い主さまとのスキンシップ
などです。とくにデンタルケアを怠ると歯周病につながるため、子犬のころから慣れさせておきましょう。
パグの病気にペット保険で備える

犬の治療費は高額になりやすいため、病気になっても十分な治療を受けられるように、ペット保険で備えましょう。ペット保険に加入していないと、治療費は全額自己負担です。
たとえば、パグがかかりやすい膀胱結石の手術費用は、15〜20万円ほどかかります。そのほか、入院費用もかかるため、トータルで数十万円かかることもあるでしょう。このようなときでも、ペット保険に加入していれば、高額な治療費をカバーできます。
まとめ|パグの健康を守るためにできること
病気へのリスクがやや高いパグの健康を守るためには、体重管理や室温管理、シワのケアなど過ごす環境や生活習慣を整えることが大切です。
万が一病気になっても治療費の負担を軽減させられるように、ペット保険で備えておくと飼い主さまも安心できるでしょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
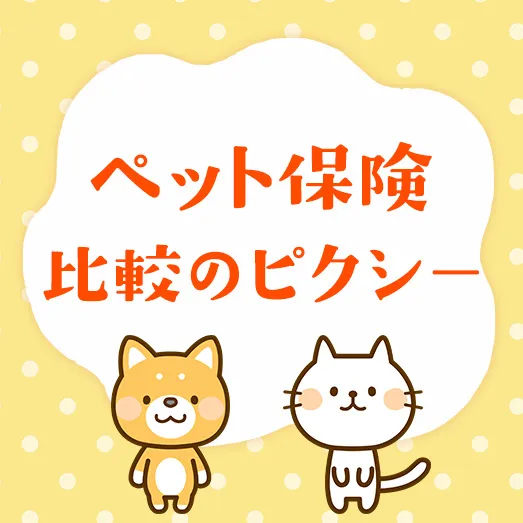
【ペット保険比較】10秒でカンタン比較
あなたの家族はどちら?
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
種類は?
年齢は?
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田犬
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴犬(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上
- スコティッシュフォールド
- マンチカン
- アメリカン・ショートヘア
- ノルウェージャン・フォレスト・キャット
- ラグドール
- ブリティッシュ・ショートヘア
- ミヌエット
- サイベリアン
- ベンガル
- ラガマフィン







