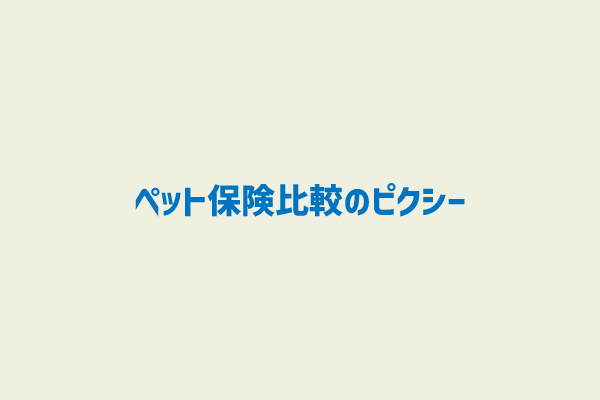家族の一員であるペットにいつまでも健康で元気に過ごしてもらうためには、日ごろのケアに加え、定期的な健康診断が重要です。
この記事では、ペットの健康診断にかかる費用や検査の内容、適切な頻度、そして受診する際の一般的な流れについて詳しく解説します。
- ペットの健康診断、料金の目安は?
- 健康診断は年に何回?目安は?
- 健康診断って具体的に何をするの?
- ペットの健康診断の流れと注意点
- Q&A|みなさまの不安や疑問を解消!
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
ペットの健康診断が必要な理由は?

「ペットにも健康診断って必要なの?」と思ったことはありませんか?
動物は人間のように「お腹が痛い」「だるい」といった体調の変化を言葉で伝えることができないため、飼い主が気づいたときには病気が進行しているというケースも少なくありません。
ペットの健康診断は、見た目にはわからない病気のサインや変化を見つけるための重要な手段として必要不可欠です。健康チェックを習慣化することで、病気の早期発見と早期治療、健康寿命を伸ばすことにつながります。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
ペットの健康診断にかかる費用はどれくらい?

ペットの健康診断にかかる費用は、動物病院やペットの種類、年齢、診断内容によって異なります。
一般的な健康診断のほかに、ドッグドックやキャットドックといった精密検査もあります。
それぞれの料金相場をみてみましょう。
ペット全体の健康診断の費用はどのくらい?
ペットの健康診断にかかる費用は、検査の内容によって大きく変わります。
かんたんな身体チェックだけなら数千円程度で済みますが、レントゲンやエコーなどを含むと金額も上がります。
一般的な検査費用は以下を参考にし、正確な金額は動物病院に確認するようにしましょう。
| 検査内容 | 費用の目安 |
| 身体検査 | 約2,000〜5,000円 |
| 血液・尿・便の基本検査 | 約5,000〜10,000円 |
| レントゲン・エコー | 約10,000〜20,000円以上 |
犬の健康診断の費用はどのくらい?
犬の健康診断の費用は、一般的に5,000円~30,000円程度が目安です。どの検査を行うか、どの病院を選ぶかによっても価格は変わります。
検査の内容は、愛犬の年齢や体調に応じてかかりつけの獣医師と相談して決めると安心です。
ドッグドック・キャットドックの料金相場
「ドッグドック」や「キャットドック」は人間ドックのような総合健診で、検査項目が多岐にわたるため、ペットの体の状態をより詳しくチェックできます。
通常の健診よりも費用は高めですが、その分安心感があります。
ドッグドック・キャットドックの料金目安は以下のとおりです。獣医師と相談し、愛犬や愛猫に合った検査方法をみつけていきましょう。
| 主な検査内容 | 費用の目安 | |
| 簡易コース | 身体検査、血液検査、 尿・便検査 |
約10,000〜15,000円 |
| 標準コース | 上記+レントゲン検査 腹部エコー検査 |
約20,000〜30,000円 |
| 特別コース (精密検査) |
上記+心電図、心臓エコー 甲状腺機能検査など |
30,000円以上 |
関連記事:犬のアレルギー検査は保険適用される?検査項目や費用は?
ペットの健康診断の頻度は?毎年受けるべき?
ペットの健康診断は、基本的に「若齢期は年に1回」「シニア期は半年に1回」が目安です。年齢や体調に応じて定期的に受けることで、病気の早期発見や予防につながります。
とくに犬や猫は、1年で人間の4〜5年分の年齢を重ねるため、1年に1回の健診でも、人に置き換えると数年に1度受けるのと同じ感覚といわれています。
かかりつけの動物病院と相談しながら、年齢や体調に合わせて最適な受診タイミングを見つけてあげましょう。
ペットの健康診断の内容と検査項目

ペットの健康診断では、問診に加え、身体検査、血液検査、尿検査、便検査などが実施されます。必要に応じて「画像診断」と呼ばれるレントゲンや超音波といった検査が追加されることもあります。
では、具体的にどのような検査なのか見ていきましょう。
身体検査(視診・触診・聴診)
健康診断のはじめに行うのが、視診・触診・聴診という基本の身体チェックです。
これらの基本的な検査は、獣医師がペットの全体的な健康状態を把握し、その後の検査項目を検討するうえで非常に重要です。
病気の早期発見につながる小さな変化に気づく場合もあります。
基本の身体チェックで獣医師がどのようなことを確認するのか、以下に詳しくまとめました。
| 視診 | 目の充血や目やに、耳の汚れ、 被毛の艶、皮膚の状態を観察する |
| 触診 | リンパやお腹の張り、体のしこりがないか、 関節の動きなどを確かめる |
| 聴診 | 心臓や肺、お腹の音を 聴診器を使ってチェックする |
血液検査
血液検査は、ペットの体内の状態を把握するために非常に重要な項目です。
少量の血液を採取し、貧血や炎症、白血球や赤血球、血小板の数などを調べる「血球検査」と、肝臓、腎臓、膵臓などの内臓機能、血糖値、コレステロール値などを調べる「生化学検査」が一般的です。
これらの項目を調べることで、外見からはわからない病気のサインや内臓の異常、栄養状態などを早期に発見できる可能性が高まります。
年齢や健康状態によって、甲状腺ホルモンや炎症反応を示す項目の検査が追加されることもあります。
尿検査・便検査
尿検査では、尿の色やにごり、濃さ(比重)、pH、糖やタンパク、血液成分の量などから、腎臓や膀胱の病気、糖尿病の兆候などを調べます。
細胞や結晶、細菌の有無を顕微鏡で調べる「尿沈渣検査」を行うこともあります。
便検査では、うんちの硬さや色、粘液性を観察し、寄生虫や消化不良のサインがないかを確認します。
正確な結果を得るには、なるべく新鮮な尿や便を持参するのがポイントです。
レントゲン・エコー
レントゲン検査とエコー(超音波)検査は、体の内部の状態を画像で確認するための重要な検査です。
レントゲン検査では、異物を誤飲していないかの確認や、骨や関節の異常、肺や心臓、お腹の臓器の大きさと形、位置などを全体的に把握できます。
一方、エコー検査は超音波を使って、臓器の内部構造や血流の様子をリアルタイムで観察します。腫瘍や結石の有無なども詳しくわかるのが特徴です。
内臓疾患や骨格系の異常を早期にみつけるのに役立ち、特にシニア期のペットや、ほかの検査で異常が見つかった場合に行われることがあります。
MRI検査
MRI検査は、強い磁場と電波を使って体の内部を詳しく映し出す検査です。
脳や脊髄、関節などの異常を調べるのに優れており、レントゲンや超音波では見えにくい病変も確認できるとされています。
ただし、全身麻酔が必要なことが多く、対応できる動物病院も限られています。
費用もほかの検査に比べて高くなる傾向があるため、詳しい検査が必要な場合や専門的な診療が必要なときに行われることがほとんどです。
ペットの年齢別におすすめされる検査項目

ペットの健康診断で受けるべき検査項目は、年齢によっても変わります。
若齢期とシニア期では注意すべき病気や体の変化が異なるため、それぞれに適した検査内容を紹介していきます。
0~1歳(子犬・子猫)
1歳未満の子犬や子猫は成長期にあたり、このころの健康診断で先天性の病気が見つかることもあります。
視診や触診などの身体検査が中心になるため、生活するうえで気になる点があれば獣医師に伝えましょう。
ペットショップやブリーダーから迎えた直後は寄生虫やウイルス感染のリスクがあるため、便検査も合わせて実施されることが多いようです。
去勢・避妊手術を予定している場合は、血液検査やレントゲン検査を併せて行うこともあります。
1~6歳ごろ(若齢期)
1~6歳ごろは、成長が安定し健康状態も良好なことが多いですが、定期的な健康チェックは欠かせません。
肝臓や腎臓などの基本的な血液検査に加え、必要に応じてレントゲン検査を受けると安心です。若い時期の健康データを記録しておくことで、異常が見つかった際の比較材料となり、早期発見につながります。
また、体重管理や生活習慣の見直しのアドバイスを受ける良い機会にもなります。
7歳以上(シニア期)
7歳を過ぎるとシニア期に入り、内臓機能の低下が起こりやすくなります。若齢期よりも詳細な血液検査を行い、体の変化を注意深くチェックしましょう。
体重の減少や食欲不振、皮膚のトラブルなどが見られたら、ホルモンバランスの検査や超音波検査も検討してください。
これらの検査は、病気の早期発見だけでなく、生活の質を維持するための対策にも役立ちます。
ペットの健康診断の流れと注意点

ペットの健康診断をスムーズに受けるには、事前の準備といくつかの注意点があります。
予約からの流れとあわせて確認しましょう。
予約から健康診断までの流れ
ペットの健康診断を受けるには、まず動物病院に予約をします。
病院で決められている検査項目以外に気になることがあれば、事前に相談をしておきましょう。
予約当日は指定時間に来院し、問診や身体検査を受けます。問診では食事や排泄、行動の様子などを詳しく聞かれるため、普段の様子を観察しておくことが大切です。
すべて終わったら一旦帰宅し、結果説明や報告書の受け取りは後日となる場合も多いです。
健康診断を受ける場合の注意点
ペットが健康診断を受ける際にはいくつかの注意点があります。
まず、正確な検査結果を得るために、絶食が必要なケースがあります。特に血液検査の前は、食事の影響で血糖値などが変動することがあるため、指定された時間から絶食させるようにしましょう。
飲水については制限がないことが多いですが、これも事前に確認が必要です。
ペットが安心して過ごせるように、普段使っているタオルやブランケット、お気に入りのおもちゃなどを持っていくこともおすすめです。
【Q&A】ペットの健康診断で気になる疑問を解決!

ペットの健康診断に関して、抱きがちな疑問についてお答えします。
健康診断の費用はペット保険で適用されない?
ペット保険はケガや病気の治療費を補償するものであり、病気の予防を目的とした健康診断の費用は補償対象外となることが多いです。
加入しているペット保険の契約内容を事前に確認するか、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
健康診断費用は自己負担となることが多いため、計画的に費用を準備しておくことが大切です。
関連記事:ペット保険で犬猫の健康診断は補償される?費用目安は?いつどこで受ければいい?
うちの子は元気そうだけど、健康診断は必要?
ペットは本能的に体調不良を隠そうとするため、一見元気そうに見えても、体の内部で病気が進行している可能性は十分にあります。
健康診断は、症状があらわれる前に病気のサインをみつけ出すためのものです。「元気そうだから大丈夫」と過信せず、定期的に健康診断を受けさせることが重要です。
猫は外に出ないから健康診断しなくてもいい?
室内飼いの猫でも、健康診断は必要です。
外に出ないからといって病気のリスクがゼロになるわけではありません。遺伝性の疾患、加齢に伴う変化など、さまざまな健康上の問題が発生する可能性があります。
特に猫は腎臓病や心臓病にかかりやすい傾向があるため、定期的な健康チェックでこれらの病気の早期発見に努めましょう。
複数のペットがいる場合、同時に受けられる?
複数のペットを同時に健康診断に連れて行くことは可能です。しかし、動物病院によってはスペースや人員の都合があるため、事前に予約する際にその旨を伝えて相談することをおすすめします。
健康診断はどのくらい時間がかかる?
ペットの健康診断は、基本的な身体検査や問診、採血だけであれば30分から1時間程度で済む場合もあります。レントゲン検査や超音波検査などの画像診断が含まれる場合は、2時間程度かかることもあります。
人間の健康診断と同様に、予約制であっても待ち時間が発生する可能性はあります。来院前に動物病院に所要時間の目安を確認しておくようにしましょう。
検査結果で「異常あり」といわれたらどうすればいい?
健康診断で「異常あり」と診断された場合、再検査やより詳しい精密検査が必要となる場合があります。
ただし、異常値が出たからといってかならずしも重篤な病気であるとは限らないため、すぐに悲観する必要はありません。
まずは、どのような異常で、どのような病気の可能性があるのかをしっかりと理解することが大切です。早期に適切な対応をすることで、病気の進行を抑えたり、症状を緩和したりすることが期待できます。
獣医師の指示に従い、必要な追加検査や治療方針について相談しましょう。
まとめ|大切なペットを守るためには定期的な健康診断を!
ペットの健康診断は、病気の早期発見・早期治療につながり、体への負担を減らしながら健康寿命を伸ばすことができます。
健康診断の内容や費用は動物病院やペットの種類・年齢によって異なりますが、若齢期は年に1回、シニア期は半年に1回の受診が推奨されています。
健康診断の流れや注意点を知っておくことで、安心して受診できるだけでなく、愛するペットの健康をしっかり守ることにつながります。
ぜひこの機会に、健康診断について見直してみましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
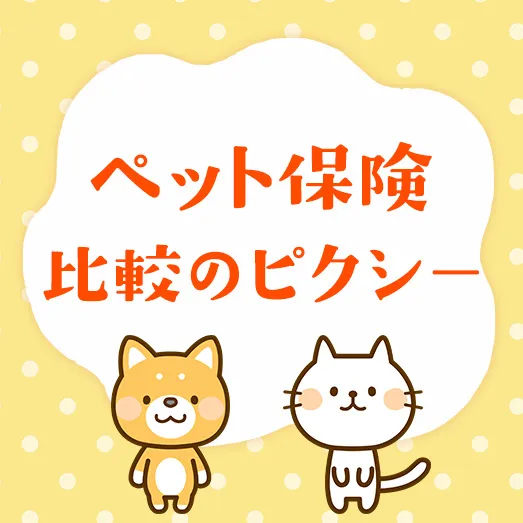
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上