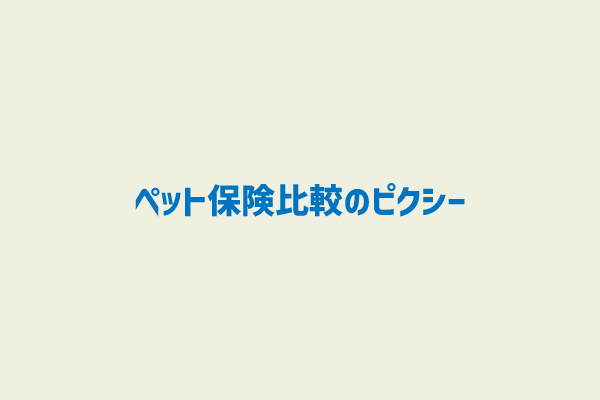「チンチラは病気になりやすい?」「飼育は簡単なの?」
チンチラのお迎えを検討中の方は、このような疑問を抱えているのではないでしょうか。
この記事では、チンチラに多い病気や長生きするための飼育のポイントなどを解説します。
- チンチラの気をつけたい病気
- チンチラの病気のサインは?
- チンチラはストレスに弱い?
- 目やには砂遊びが原因?
- チンチラが急にぐったりしたら?
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
チンチラとは?もふもふで知能の高い小動物!

チンチラは、アンデス山脈の標高の高い場所に生息する小動物です。げっ歯目チンチラ科チンチラ属に分類され、やわらかい被毛が特徴的です。
チンチラの被毛は非常に高密度に生えており、1つの毛穴から50~100本もの毛が生えているといわれています。美しい被毛をもつことで乱獲されていた歴史があり、野生のチンチラは絶滅危惧種に指定されています。
チンチラの性格は陽気で活発で、なつきやすい子もいるようです。自分の名前や人間の言葉を覚えるほどかしこい点も人気の理由なのでしょう。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
チンチラの寿命は10年以上で長生き?
野生のチンチラの平均寿命は、10年程度といわれていますが、飼育下では20年以上生きた例もあります。
ハムスターの平均寿命は2~3年、ウサギは7~8年程度とされますので、ほかの小動物と比較しても、チンチラは長生きといえるでしょう。
チンチラと人間の年齢を比較すると?
チンチラの1歳は、人間の年齢に換算すると12歳前後といわれています。
2年で20歳前後、3年で24歳前後と年をとっていき、3歳以降はゆるやかに成長していくのです。10年で60歳前後に換算され、シニア期に入ります。
チンチラはどんな病気になりやすい?

ここからは、チンチラがなりやすい病気やケガを6つ紹介します。チンチラを飼育する前に気をつけるべきケガや病気について知っておきましょう。
熱中症
チンチラは、温度や湿度が低い乾燥地帯で暮らしていたため、日本の湿度の高い暑さが苦手です。室温や湿度が高い状態が続くと、熱中症を発症しやすくなります。
- 体が熱い
- 耳がいつもより赤い
- 呼吸が速い
- 食欲がない
- ぐったりしている
上記のような症状は熱中症のサインかもしれません。
熱中症は、最悪の場合、命を落とす危険性がある病気です。夏場はエアコンや除湿機などを活用して、室温は25度以下、湿度は40%以下を保てるようにしましょう。
不正咬合
不正咬合は、チンチラの歯科疾患のなかで最も発症率の高い病気です。チンチラの歯は一生伸びつづけるため、牧草などを与えて歯が削れるようにする必要があります。
チンチラが不正咬合を発症すると、下記のような症状がみられます。
- よだれを流す
- 食欲低下
- 体重減少
不正咬合は、食事や生活習慣を見直しても改善が難しいケースもあるようです。動物病院で定期的に歯をカットする処置を受けなければならない場合もあるでしょう。
皮膚糸状菌症
皮膚糸状菌症とは、皮膚や毛に真菌(カビ)が感染することで引き起こされる病気です。ストレスや高温多湿の環境、衛生状態が悪いなかでの飼育などで発症するといわれています。
皮膚糸状菌症を発症すると、下記のような皮膚の異常があらわれます。
- 顔面・頭部・四肢の脱毛
- 赤み
- フケ
治療には抗真菌剤の薬を投与することが一般的です。また治療と同時に、飼育環境や室温管理などの見直しが必要になる場合もあります。
胃腸のうっ滞
うっ滞(うったい)とは、胃の内部にガスが異常に発生し、胃腸の動きが悪くなっている状態を指します。「鼓腸症(こちょうしょう)」と呼ばれることもあるようです。
水分の多い食事やストレスなどが原因といわれ、以下のような症状があらわれます。
- 食欲不振
- 元気がない
- ウンチが小さい
- ウンチに血液が混ざる
うっ滞は命にかかわるケースもあるため、気になる症状が見られたら動物病院に相談しましょう。
結膜炎
チンチラは、目に砂や異物が入ると結膜炎を発症することがあります。結膜炎のおもな症状は、下記のとおりです。
- 目やに
- 涙
- まぶたの腫れ
- 目をしきりにかく
結膜炎の治療は、点眼液などが処方されます。砂浴びは結膜炎を悪化させるおそれがあるため、治療が完了するまで控えるのが望ましいでしょう。
骨折
チンチラの骨は細く小さいのが特徴です。俊敏に飛び回るように動くため、家具やケージにぶつかって骨折をしてしまうケースは多くあります。
骨折をした場合、骨折した場所をかばうような動きがみられます。たとえば、足を浮かせて歩いたり、歩き方がいつもと違ったりする場合は、骨折を疑いましょう。
骨折の治療は、手術を行うか、ギプスで固定するかのどちらかです。チンチラの場合、骨が非常に細く、手術が難しい動物病院もあります。万が一の事態に備え、かかりつけの動物病院を探しておきましょう。
上記以外に、チンチラは以下のような病気にもなりやすいといわれています。
- てんかん
- 便秘
- 膿瘍
- 膀胱炎
チンチラはストレスに弱い?突然死もある?

チンチラは活発な性格をしていますが、神経質で繊細な一面ももち合わせています。そのため、環境の変化や飼育環境が悪い場合などに、ストレスを感じてしまうようです。
チンチラがストレスに感じることの一例を紹介します。
- ほかの動物と同じ空間で飼育する
- 騒がしくて落ち着かない環境で飼育する
- 相性の悪いチンチラと同居させる
チンチラを追いかけまわしたり、大きな音で驚かせたりして強いストレスをかけると、けいれんを引き起こし急死する可能性もあります。チンチラがストレスを感じないよう、飼育環境を整えることが大切です。
チンチラの病気のサインは?急にぐったりしたら注意!
チンチラの体調が悪いときは、下記のようなサインを出すことがあります。
- 食べるご飯の量が少ない
- ぐったりとしている
- ウンチが少ない
- おしっこの回数が多い
- 皮膚に赤みがある
いつもチンチラのことをみている飼い主さまが「いつもと様子が違う」と感じた場合、何かしらの異常を抱えているケースは少なくありません。これらのサインがみられたら、できるだけ早く動物病院で診察を受けましょう。
チンチラの病気になりにくい飼い方のポイント

ここからは、チンチラが病気になりにくい飼育のポイントを紹介します。5つのポイントを詳しくみていきましょう。
部屋の温度・湿度を管理
チンチラは、密度の高い被毛をもっており、暑さや湿度に弱いのが特徴です。そのため、部屋の温度と湿度は、1年中しっかり管理する必要があります。
チンチラの適温は20度前後とされています。夏場は25度以下になるようにエアコンを活用して調整しましょう。
また、チンチラが快適に過ごせる湿度は40%未満です。室温が低くても、湿度が高いと熱中症や体調不良になる可能性があります。そのため、室温だけでなく夏場の湿度調整もチンチラを飼育するうえで不可欠です。
チンチラの暑さ対策は、エアコンと除湿機の併用がおすすめです。
除湿機能つきのエアコンもありますが、室温が安定しなかったり、設定した湿度まで下がらなかったりする可能性があります。そのため、エアコンを冷房設定で稼働させながら、除湿器も活用すると、室温と湿度を管理しやすくなるでしょう。
エアコンや除湿器と一緒に、アルミ製のプレートやテラコッタのトンネルなどの涼感グッズの活用も検討してみてください。
砂浴びは欠かせない!
チンチラは、犬や猫のようにお風呂に入る代わりに、砂浴びをして被毛をきれいに保っています。毛穴から「ラノリン」と呼ばれる油を分泌していますので、余分なラノリンや被毛の汚れを落とすためにも、1日1回は砂浴びをさせましょう。
砂浴びの砂は、チンチラ専用の粒が細かいものを選び、衛生的に保つためにも、毎日交換するのがおすすめです。
牧草やチモシーで歯をケア
チンチラの主食は牧草です。牧草をよく食べることで、奥歯が削られて不正咬合を予防できます。
牧草にはチモシー・アルファルファ・オーツヘイなどさまざまな種類がありますが、チモシーを与えることが一般的です。チモシーは高繊維質で歯が削れやすい一番刈りがおすすめです。
また、チンチラには専用の固形フード(ペレット)を副食として与えます。ただし、ペレットはあくまで副食です。理想としては、牧草9割・ペレット1割の割合で1日の食事を用意しましょう。
部屋んぽで太りすぎを防止
「部屋んぽ」とは、ケージからチンチラを出して室内で自由に遊ばせることです。野生下のチンチラは、岩場で生活しており飛び跳ねたり走ったりと活発に動きます。部屋んぽをさせることで、ケージよりも広い空間で運動でき、太りすぎ防止やストレス解消に効果的です。
部屋んぽの頻度は1日1回程度です。1回の部屋んぽで30分以上は遊んであげると良いでしょう。
かかりつけの動物病院を見つける
チンチラはすべての動物病院で診てもらえるわけではありません。そのため、チンチラを診察できる動物病院が近くにあるかどうか事前に調べておくことが大切です。
チンチラを診察できる動物病院がみつかったら、定期的に健康診断を行うと良いでしょう。健康診断は病気の早期発見につながります。とくに高齢のチンチラは体に不調が出やすいため、健康診断とあわせて普段から変わった様子はないかチェックしておきましょう。
チンチラは食べちゃダメ!危険なもの一覧

チンチラは野菜や野草、フルーツなどを食べることができます。しかし、なかにはチンチラが食べると危険な食べ物もあります。チンチラに与えてはいけない食べ物の一例は、下記のとおりです。
- チョコレート
- アボカド
- ネギ
- ニンニク
- じゃがいも
- ビワやアンズなどの種
- アサガオ
- 観葉植物
食べると危険な物は、チンチラの近くに置かないことが大切です。万が一、食べてしまった場合は、すぐに動物病院を受診してください。
チンチラの誤飲・誤食を防ぐためには、部屋んぽスペースを整理することが大切です。
部屋んぽスペースに、観葉植物や花を飾っている場合、ほかの部屋に移動させたほうが良いでしょう。また、リビングを部屋んぽスペースにしている場合、食材が落ちている可能性のあるキッチンには入れないように仕切りを作ることをおすすめします。
チンチラを部屋んぽさせる前に、チンチラにとって危険なものがないか確認しましょう。
チンチラにペット保険は必要?入れるプランはある?

チンチラは小動物のなかでも長生きで、20年以上生きることもあります。チンチラも年をとると病気になりやすいため、ペット保険で万が一の備えをしておくことをおすすめします。
ペット保険には、チンチラが入れるプランもあります。以下の記事では、おすすめのペット保険を紹介しています。気になる方はぜひ参考にしてください。
まとめ│チンチラと長く健康に暮らそう!
今回は、チンチラがなりやすい病気や飼育のポイントについて解説しました。
チンチラは飼育下で平均寿命が10年以上と長生きな小動物です。長生きのためには、飼育環境を整えたり、ストレスを与えたりしないことが大切です。
また、チンチラの治療費は高額になるケースが少なくありません。とくに高齢のチンチラは動物病院を受診する回数が増える可能性が高まるため、万が一のためにペット保険への加入を検討しておきましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
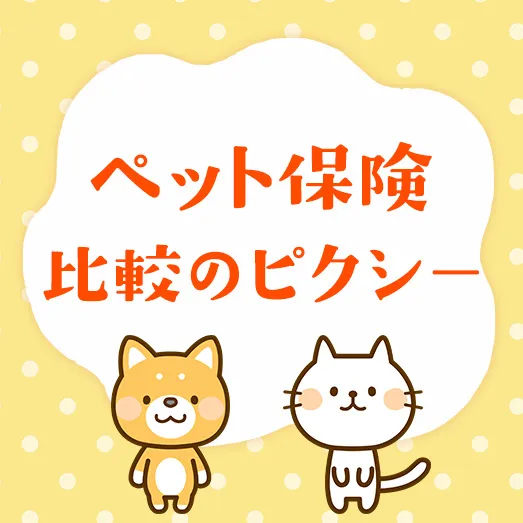
【ペット保険比較】10秒でカンタン比較
あなたの家族はどちら?
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
種類は?
年齢は?
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田犬
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴犬(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上
- スコティッシュフォールド
- マンチカン
- アメリカン・ショートヘア
- ノルウェージャン・フォレスト・キャット
- ラグドール
- ブリティッシュ・ショートヘア
- ミヌエット
- サイベリアン
- ベンガル
- ラガマフィン