
「保護猫を飼いたい!」と思っていても、実際にお迎えする方法がわからない方は多いのではないでしょうか。この記事では、保護猫とはどういう子たちなのか、保護猫を迎え里親になるための5つのステップ、お迎え準備や飼い方までを具体的に解説します。
保護猫と幸せに暮らしていくために、ぜひ最後までご覧ください。
- 保護猫と出会える5つの場所は?
- 保護猫の里親になるための条件
- 野良猫を保護するにはどうすればいい?
- 保護猫のお迎え費用はどれくらい?
- 猫をお迎えするときに用意すべきグッズ
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
保護猫とは│定義や種類、背景は?

保護猫とは、何らかの理由で飼い主がいない状況から保護された猫を指します。その背景はさまざまで、飼育放棄された「捨て猫」や、屋外で生まれ育った「野良猫」、迷子になってしまった元飼い猫などが含まれます。
【保護猫となった理由の一例】
- 迷子
- 繁殖引退
- ブリーダー崩壊
- 飼い主の飼育放棄
- 行政に持ち込まれた
このような猫は、動物愛護センターや民間の保護団体、個人ボランティアなどによって保護され、新しい家族を探しています。環境省が発表している資料によると、その数(令和5年度の引き取り数)は25,224頭で、そのうちの56.3%が子猫です。そして、引き取り数の66.0%は飼い主が不明となっています。
参照:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」
ペットショップやブリーダーからではなく、保護猫をお迎えすることの意義は以下のようなものが挙げられます。
- 殺処分されるはずだった命を助けられる
- より自分に合った猫を家族に迎えられる
- 成猫の場合は子猫よりも飼育の負担が少ない
保護猫は、それぞれが異なる過去を持ち、性格や人への慣れ具合も一頭一頭異なるため、しっかりと向き合う覚悟を持ってお迎えしなければなりません。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
【保護猫の迎え方】出会える5つの方法
保護猫を家族として迎え、里親になるための方法は5つ挙げられます。ここでは、それぞれの方法の特徴や流れについて詳しく解説していきます。
①保健所や動物愛護センター
「保健所」や「動物愛護センター」は、都道府県や市町村が運営する公的な施設です。これらの施設では、迷子や飼育放棄などで行き場を失った猫たちが保護されています。
ウェブサイトなどで収容されている猫の情報を公開しており、職員に相談しながら自分の家庭環境に合う猫を探すことが可能です。譲渡を受けるには、飼育環境に関する審査や、適正な飼育方法を学ぶための講習会への参加が義務付けられている場合もあります。
収容期限が定められていることもあり、ここから猫を迎えることは、殺処分数を減らすという社会的な意義も持ち合わせています。
②動物保護団体の譲渡会
民間の「動物保護団体」が主催する譲渡会は、保護猫と直接触れ合える貴重な機会です。商業施設や専用シェルターなどで定期的に開催され、多くの猫たちが新しい家族を待っています。
譲渡会では、猫を一時的に預かりお世話をしているボランティアスタッフから、それぞれの猫の性格や好きなこと、健康状態など、詳しい情報を直接聞くことができます。
譲渡自体は無料の場合が多いですが、ワクチン接種や不妊・去勢手術にかかった医療費の一部を「譲渡費用」として負担する仕組みが一般的です。事前に開催日時や場所、参加条件などを確認して訪れると良いでしょう。
③動物病院による里親募集
地域のかかりつけ「動物病院」が、保護猫の里親募集の窓口となっているケースもあります。飼い主が見つからずに持ち込まれた子猫や、ケガなどの治療中に保護された猫などが対象となることが多く、院内の掲示板やウェブサイトで里親を募集しています。
猫の健康状態やこれまでの経緯について、獣医師や動物看護師から説明を受けられる場合もあり、安心してお迎えできるかもしれません。費用については、病院や猫の状況によって異なります。
④譲渡型の猫カフェ
譲渡型の「猫カフェ」は、店内で里親を募集している保護猫と触れ合える施設です。通常の猫カフェと同様に、ドリンクなどを楽しみながら猫たちと過ごすことができます。
リラックスした環境で猫たちが過ごしているため、ケージの中にいる姿を見るだけではわからない、その猫本来の性格やほかの猫との関わり方などをじっくり観察できます。
もし気に入った猫がいれば、スタッフを通じて里親になるための申し込みをして、面談やトライアルへと進む流れになるでしょう。
⑤里親募集サイト
インターネット上には、保護猫の「里親募集サイト」が多数存在します。全国各地の保護団体や、個人ボランティアが保護している猫の情報が掲載されており、年齢や性別、毛色、地域などの条件で検索して、希望に合った猫を探すことができます。
気になる猫を見つけたら、サイトを通じて保護主と連絡を取り、お見合いの日程などを調整します。手軽に多くの情報を得られる反面、個人間のやり取りになる場合もあるため、トラブル防止の注意は必要です。
譲渡条件や費用、アフターフォローの有無などを事前にしっかりと確認し、信頼できる相手かどうかを見極める必要があります。
⑥野良猫を保護
「野良猫」を保護してお迎えする場合には、とくに細心の注意が必要です。可能なら自治体や地域ボランティアなどの専門家に手を借りることも検討しましょう。
野良猫は人に慣れていないことも多く、捕獲や搬送にはケージや捕獲器などの準備が必要です。また、保護したら動物病院で健康チェックを受け、ワクチン接種やノミ・ダニの駆除、不妊・去勢手術を行うことが推奨されます。
野良猫は人との生活に慣れるまで時間がかかるケースもあり、少しずつ家や人に慣らしていくのが理想です。また、地域猫としてボランティア団体などにより管理されている場合もあるため、保護する前にまずは確認することが大切です。
里親になるための条件│必須チェックリスト

保護猫の里親になるためには、猫が生涯にわたって幸せに暮らせることを保証するための、いくつかの条件を満たす必要があります。
譲渡契約の前に以下のような条件が確認されます。
- 居住環境
- 脱走防止策
- 家族構成
- 年齢
- 性別
- 仕事
- 留守番時間
猫を飼えるペット可の住居か
保護猫を迎える前提として、住居がペットの飼育を許可している必要があります。マンションやアパートなどの集合住宅の場合は、管理規約や賃貸借契約書をかならず確認し、「ペット可」の記載があることを確かめなくてはなりません。
完全室内飼いと脱走防止策を徹底できるか
保護猫の譲渡条件として、ほとんどの場合「完全室内飼い」が義務付けられています。屋外は交通事故や感染症、ほかの動物との喧嘩、虐待など、猫にとって多くの危険が潜んでいるためです。玄関ドアや窓の開閉は慎重に行い、網戸が破れていないか、ロックがしっかりかかるかなどが定期的に確認されます。
家族全員が保護猫のお迎えに賛成か
保護猫を家に迎えることに対して、同居している家族全員が猫を迎えることに賛同していることは絶対条件です。また、事前に家族の中に猫アレルギーを持つ人がいないかを確認することも非常に重要です。家族のうち一人でも反対していたり、アレルギーの問題があったりする状況で無理に飼い始めると、最終的に飼育放棄につながる悲しい結果を招きかねません。
食費や医療費などを負担する経済力があるか
猫を飼育するには、継続的な経済的負担がともないます。日々の食事代やトイレの砂といった消耗品の費用に加え、ワクチン接種や定期的な健康診断、ノミ・ダニ予防などの医療費が必要です。予期せぬ高額な医療費にも対応できる安定した収入があるかどうかが問われます。
猫の生涯にわたってお世話を継続できるか
譲渡団体の多くは、「猫の一生を責任もって面倒をみられる」里親を重視しています。そのため、応募者の年齢に上限を設け、高齢者や単身者の場合は、万が一のときに世話を引き継げる後見人を求めるケースが一般的です。さらに、毎日の食事・トイレ掃除・遊びやスキンシップなど、猫と十分に時間を過ごせる環境があるかどうかも大切な条件となります。
保護猫の迎え方│正式譲渡までの5つのステップ

保護猫の迎え入れは、猫と里親候補の双方が幸せになれるよう、トライアルなどの慎重なプロセスを経て行われます。ここでは、出会いから正式な家族になるまでの具体的な5つのステップを解説します。
【ステップ1:出会い】気になる猫を見つける
保護猫には、譲渡会や動物保護団体のウェブサイト、さらには猫カフェなど、さまざまな場所で出会えます。なるべく直接会いにいき、性格や雰囲気を感じ取れる機会をもつのがおすすめです。
「この子だ!」という直感で決める場合もありますが、すぐに判断せず、年齢・性格・健康状態・これまでの経緯などプロフィールも確認しましょう。自分や家族のライフスタイルと合うかどうかをじっくり検討することが大切です。
【ステップ2:申込】必要書類を提出して面談へ
保護猫の里親になるための手続きとして、保護団体などが用意した申込書を提出します。家族構成や住居の種類、飼育経験の有無、先住ペットの状況、留守番時間といった情報を正直かつ詳細に記入しましょう。
書類提出後は、団体の担当者との「面談」が行われます。この面談は、猫の生涯に責任を持つ覚悟があるか、適切な飼育環境を提供できるかなどが確認されます。
【ステップ3:自宅訪問】飼育環境や家族の確認
多くの場合、トライアルの前にスタッフによる「家庭訪問」が行われます。提出書類の内容と実際の飼育環境が一致しているか、そして猫が安全に暮らせる環境であるかを確認するのが目的です。
具体的には、窓や玄関の脱走防止対策が十分か、猫にとって危険な物が室内に放置されていないか、といった点をチェックします。また、同居する家族全員と会い、猫を迎えることへの同意を再確認する機会にもなります。
【ステップ4:トライアル】同居して相性チェック
問題がなければ、通常1週間から2週間程度の「トライアル期間」が始まり、保護猫を自宅に預かって実際に暮らしてみます。猫が新しい環境や家族に順応できるか、そして里親家族と猫の相性は良いか、などを見極めるお試し期間です。
とくに、先住のペットがいる場合や、小さなお子さんがいる家庭では、お互いがストレスなく過ごせるかを確認する重要な機会となります。もし相性が合わないと判断した場合は、譲渡を辞退することも可能です。
【ステップ5:正式譲渡】契約手続きを行い家族へ
トライアル期間が双方にとって良好に終了し、家族として迎える意思が固まったら、最終ステップである「正式譲渡」の手続きに移ります。
保護団体が用意した譲渡契約書に、終生飼育の誓約、完全室内飼いの徹底、適切な健康管理の実施、定期的な近況報告の義務といった項目を確認し、署名・捺印します。すべての手続きが完了した瞬間から、保護猫は法的に新しい家族の一員。保護猫との暮らしが本格的に始まります。
保護猫のお迎えに必要な初期費用と維持費
保護猫を家族に迎えるにあたり、どれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておきましょう。ここでは、初期費用と維持費の具体的な内訳と目安について解説し、経済的な準備をサポートします。
保護猫をお迎えするときの初期費用
保護猫を迎える際にかかる初期費用は、大きく次の3つに分けられます。
・食費:1kgあたり500~1,000円
・生活用品費:5,000~10,000円
保護猫を迎える際には、保護団体へ支払う譲渡費用がかかります。この費用は、保護されている間に行われた医療処置の実費分を、次の保護猫のために充当する目的で設定されています。
おもな内訳は、不妊・去勢手術、猫エイズ・猫白血病のウイルス検査、混合ワクチン接種、ノミ・ダニ・回虫などの駆除、マイクロチップの装着費用などです。
保護猫の飼育にかかる維持費用
猫の飼育には、主食となるキャットフードやおやつなどの食費、そして猫砂やペットシーツといったトイレ用品費などがかかります。猫の健康状態などによって異なりますが、毎月かかる費用はおよそ9,500円です。この金額はあくまでも目安なので、最低でもこの金額はかかると考えておきましょう。
さらに、年に1回のワクチン接種や定期的な健康診断、ケガや病気をした際の治療費といった医療費も計画に入れておく必要があります。とくに医療費は高額になることがあるため、ペット保険への加入を検討するのも一つの方法です。ペット保険の保険料は、プランや猫の年齢などでも異なりますが、平均して月1,000~5,000円程度かかります。
保護猫を飼いたい!必要な飼育グッズは?

ここでは、保護猫との新生活をスムーズにスタートさせるために、最低限準備しておきたい基本的な飼育グッズと、安全対策のためのグッズをリストアップして紹介します。
猫の生活に欠かせない基本の飼育グッズ
猫が健康で安心して暮らすためには、基本的なグッズをあらかじめ準備しておくことが大切です。最低限そろえておきたいものは以下のとおりです。
- フードや水のボウル:壊れにくく丈夫な器を用意
- 猫用ベッド:リラックスしてくつろいでもらうため
- ケージ:新しい環境に慣れるまでの隠れ家として大切
- キャットフード:年齢や健康状態に合ったフードを選ぶ
- トイレと猫砂:猫が落ち着いて排泄できる大きさ
- 爪とぎ器:家具や壁の傷防止のために必要不可欠
- キャリーバッグ:動物病院への通院や災害時の移動に
- お手入れグッズ:慣れてきたら猫用ブラシや爪切りなど
猫の安全対策に必要なグッズ
猫が室内で安全に暮らせるようにするためには、危険を未然に防ぐ工夫が欠かせません。とくに脱走や事故は大きなリスクにつながるため、安全対策グッズを準備しておきましょう。
脱走防止や感電・ケガ防止グッズとしては以下のようなものが挙げられます。
- 窓や網戸にはストッパーやロック
- 脱走やキッチンへの侵入防止にペットゲート
- コンセントや電気コードを覆うカバー
また、猫が誤って口にすると危険な観葉植物や、飲み込んでしまうおそれのある小さな物は、猫の手が届かない場所に移動させるか、片付けておく必要があります。
保護猫の飼い方│お迎え後のお世話・慣らし方

ここでは、保護猫をお迎えしたあとのお世話の仕方や、家や家族に慣れてもらう方法などを紹介。日々の食事やコミュニケーション、しつけの進め方まで、保護猫が心を開いてくれるためのポイントを具体的に解説します。
まずは動物病院で健康診断や検査を
保護猫を迎えたら、できるだけ早く動物病院で健康診断を受けさせましょう。譲渡元で検査やワクチンが済んでいても、環境の変化で体調を崩すことがあります。診察では体重測定・触診・聴診のほか、便検査で寄生虫の有無を確認すると安心です。
かかりつけ医を決めておくと、今後の通院やケガや病気の際もスムーズです。医療記録があれば持参し、ワクチン計画や日々のケアについても相談しましょう。
キャットフードの選び方と与え方
フードは年齢や健康状態に合った「総合栄養食」を選びます。子猫用・成猫用・シニア用があるのでライフステージに合わせましょう。
お迎え直後は、保護先で与えられていたフードを用意し、切り替える場合は1週間ほどかけて少しずつ移行すると安心です。成猫は1日2回が基本で、常に新鮮な水を飲める環境を整えます。
距離感は猫のペースに合わせて
保護猫は、人間に慣れていない、あるいは過去の経験から恐怖心を持っていることがあります。家に迎えた初日は、無理に触ろうとしたり、大きな声を出したりせず、まずは猫が安心できる静かな環境を提供することに専念します。
ケージや部屋の隅など、猫が自分で選んだ隠れ場所にいる間はそっとしておき、猫の方から出てくるのを待ちます。飼い主は同じ空間で静かに本を読むなどして過ごし、猫に「この人は危害を加えない安全な存在だ」と認識してもらうことが第一歩です。
猫が少しずつ興味を示してきたら、おやつを差し出したり、猫じゃらしで優しく誘ったりして、距離を縮めていきます。
社会化やしつけも少しずつ行う
猫が新しい生活に慣れ、リラックスする様子がみられるようになったら、しつけや社会化トレーニングも始めます。
社会化とは、掃除機やインターホン、来客など、日常生活で起こるさまざまな音や出来事に慣れさせることです。大きな音を立てる際は、おやつを与えるなど良いことと関連付けると、恐怖心を和らげることができます。
トイレのしつけは、猫がそわそわし始めたらトイレに連れて行くことを繰り返すことで覚えます。もし粗相をしても、決して叱りつけず、臭いを完全に消して原因を探ります。
爪とぎや噛み癖などの問題行動も、代替案(爪とぎ器を用意する、噛んでも良いおもちゃを与える)を示しながら根気強く教えていきます。
野良猫を保護するときの注意点やNG対応
野良猫を家に迎える際は、健康管理や安全な環境づくり、猫のペースに合わせた接し方が大切です。焦らず信頼関係を築くことで、安心して暮らせる家庭が作れます。
健康チェックと安心できる環境づくり
野良猫を迎えるときに一番大切なのは健康管理です。外で暮らしていた猫は、ノミ・ダニ・回虫などの寄生虫や、猫風邪、猫エイズ(FIV)、白血病(FeLV)などの感染症を抱えていることも少なくありません。まずは動物病院で健康診断・ワクチン・必要に応じた不妊・去勢手術を済ませましょう。
また、いきなり家の中を自由にさせるのではなく、静かな部屋やケージを用意して、猫が安心できるスペースから慣れさせるのが理想です。隠れ場所を確保してあげると不安が和らぎやすくなります。
野良猫にやってはいけないNG対応
人に慣れていない野良猫に、抱っこやスキンシップを無理強いするのは禁物です。怖がらせると心を閉ざしてしまい、人間不信につながります。大きな声で叱る、急に手を伸ばすといった行為も避けましょう。
また、外に出してしまうと、せっかくの人馴れが振り出しに戻るだけでなく、交通事故や感染症の危険もあります。食事も、人間の食べ物ではなく、かならずキャットフードを与えましょう。
野良猫の保護に向いている人/向いていない人
野良猫の保護には「根気強さ」と「柔軟さ」が必要です。
向いているのは、
- 時間をかけて猫のペースに合わせられる人
- 動物病院へ定期的に通える経済力がある人
- 騒がしくない住環境を用意できる人
反対に、短期間で慣れてほしいと焦ってしまう人や、猫と過ごす時間がほとんど取れない人には向いていません。野良猫は人に慣れるまで数か月~数年かかることもあるため、焦らず見守る姿勢が必要です。
保護猫・野良猫を育てるための注意点

保護猫はペットショップから迎える子猫と違って、さまざまな経験をしてきた過去があります。警戒心やこだわりが強い場合があるため、保護猫の生活環境が変化する際には特に配慮が必要です。
なつくまで時間がかかる
順応性が比較的高い子猫であれば、なつくまでにはそれほど時間がかからないかもしれません。一方、過去に辛い経験をした成猫であれば、すぐにはなつかないでしょう。それでも、少しずつ猫のことを理解し、猫の方から来てくれるまで気長に待つことも必要です。
病気や後遺症があるかもしれない
保護猫の中には、病気や後遺症を抱えている猫もいます。そのような保護猫を迎える場合は、適切な治療を受けさせるための経済力と日々のケアを行うための知識が必要です。先住猫に感染する病気もあるので、事前にしっかり確認してください。
しつけは粘り強く
保護猫の中でも、野良猫や多頭飼育されていた猫は警戒心が強く、しつけが難しい場合もあります。そんな時は、あきらめてしまうのではなく、譲渡してもらった愛護団体のスタッフや保健所の職員に相談してみてください。
一生世話をする覚悟で飼おう
「運命の猫」と思って迎えた保護猫が、思っていたよりも手がかかったり病気になってしまったりするケースも見受けられます。それでも、1度飼うと決めたのであれば、一生世話をする覚悟が必要です。一時の安易な気持ちで、保護猫を飼うことがないようにしてください。
要確認!この条件でも保護猫を飼える?
里親になるための条件として、次のようなさまざまな項目が確認されます。ここでは、例として一人暮らしや賃貸住宅でも保護猫を飼えるのかについて解説します。
一人暮らしでも保護猫を飼える?
一人暮らしの場合は、保護猫を譲渡してもらえない、または要相談としている場合がほとんどです。その理由としては、留守の時間が長くなる、引っ越しや結婚などで生活が変化する可能性などがあげられます。
一人暮らしでも猫を飼いたいという方は、ペットショップやブリーダーから猫を迎えることを検討してみると良いかもしれません。
関連記事:一人暮らしでも猫は飼えるの?飼うときの条件や飼いやすい種類をご紹介
賃貸住宅でも保護猫を飼える?
賃貸住宅で「ペット可」「ペット相談」の物件であっても、猫は不可とされている物件もあるので事前に確認してください。
また、猫を飼える物件であっても賃貸トラブルを避けるため、キズやニオイの対策はしっかり行いましょう。
まとめ│保護猫を飼いたいなら事前調査や心構えを!
この記事では、保護猫を飼いたいという方のために、基本知識から出会い方、譲渡条件、お迎えの流れ、必要な費用やグッズ、迎えた後の暮らし方までをまとめました。
保護猫を家族に迎えることは、命を救うと同時に暮らしを豊かにしてくれる素晴らしい経験です。もちろん覚悟や準備は欠かせませんが、正しい知識があれば猫も人も安心して幸せな時間を過ごせます。ぜひ参考にして、新しい生活の一歩を踏み出してください。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
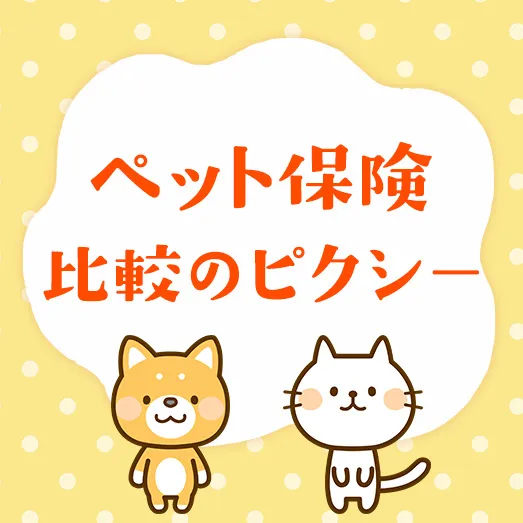
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








