
愛犬の度重なるイタズラに頭を悩ませる飼い主は少なくありません。この記事では、犬のイタズラをやめさせる方法について、その原因から具体的な対策、正しいしつけ方までを網羅的に解説します。
愛犬の行動の理由を理解し、適切な対応を学ぶことで、お互いが快適に暮らせる関係を築くためのヒントを提供します。破壊行動の背景にある犬の気持ちをイメージしながら、解決策を探っていきましょう。
- 犬がやってしまいがちなイタズラは?
- イタズラをしてしまう犬の気持ちって?
- 犬がイタズラをしたらどう叱るべき?
- 子犬のイタズラっていつまで続くの?
- 犬のイタズラ防止に効果的なグッズはある?
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
許せない?犬のイタズラ・破壊行動6選!

犬と暮らす中で、多くの飼い主が経験するイタズラや破壊行動があります。思わず笑ってしまうようなものから、高価なものを壊されて頭を抱えてしまうケースまでさまざまです。
ここでは、特に飼い主が「許せない」と感じがちな代表的なイタズラ・破壊行動を紹介します。
【1】リモコンや靴下、小物などを隠す
犬がリモコンや靴下、スリッパといった小物をどこかへ隠してしまうイタズラは、飼い主の匂いが強くついているものへの執着が原因の一つです。飼い主の匂いは、犬にとって安心できるものであり、それを自分の縄張りであるベッドやハウスに運んで安心感を得ようとします。
また、単に遊びの一環として、物を咥えて運ぶ行動を楽しんでいる場合もあります。この行動は、犬が獲物を巣穴に持ち帰るという本能的な習性の名残とも考えられています。
特に飼い主が探している様子を見て、かまってもらえていると勘違いし、行動がエスカレートすることもあるため注意が必要です。
【2】おやつや食べ物の盗み食い
テーブルの上に置いておいたパンやおやつ、ゴミ箱の中の調理くずなどを犬が盗み食いしてしまうことがあります。このイタズラは犬の嗅覚が非常に優れているため、食べ物の匂いを敏感に察知し、食欲という本能的な欲求に抗えないことが主な原因です。
特に空腹時や、栄養バランスが偏っている場合にこの行動がみられやすくなります。一度成功体験をすると繰り返す傾向が強いため、お迎えしたときから、食べ物の管理を徹底しましょう。
人間の食べ物の中には、犬にとって中毒症状を引き起こす玉ねぎやチョコレートなどが含まれている可能性があり危険です。
【3】ティッシュやチラシなどを散らかす
犬のイタズラでは、ティッシュペーパーを箱から全部引き出したり、郵便受けから落ちたチラシをビリビリに破いて散らかしたりする行動もよくみられます。
この行動の背景には、退屈しのぎやストレス発散、あるいは紙を破る際の音や感触を楽しんでいるといった理由が考えられます。特に子犬期には、さまざまなものに興味を示し、口に入れて感触を確かめる行動が多くみられます。
紙類は誤飲してしまうと消化管に詰まる危険性もあるため、犬が届く場所に置かないようにするなどの物理的な対策が求められます。
【4】家具や壁、電気コードをかじる
家具の脚や壁紙、電気コードなどをかじるイタズラは、感電の危険があり非常に危険です。
これは特に子犬の歯の生え変わりの時期に多くみられます。歯茎がむずがゆくなり、その不快感を解消するために手近なものをかじってしまうのです。成犬の場合は、運動不足によるストレスや、留守番中の退屈さ、分離不安などが原因として考えられます。
また、壁紙や家具の破片を飲み込んでしまうと、消化器系に問題を起こす可能性もあります。犬がかじっても良いおもちゃを与えることで、かじりたい欲求を安全な方法で満たしてあげることが大切です。
【5】おもちゃやクッションを破壊する
犬がおもちゃやクッションを徹底的に破壊してしまう行動には、犬の狩猟本能が関係しています。おもちゃを獲物に見立て、それを仕留めるという一連の行動を疑似体験しているのです。クッションやぬいぐるみを振り回し、噛みちぎることで、エネルギーを発散し満足感を得ています。
しかし、この犬の破壊行動には、おもちゃの部品や綿を誤飲してしまう危険性も伴います。丈夫な素材でできたおもちゃを選んだり、遊び終わったら片付ける習慣をつけたりすることで、事故を防ぐことができます。遊びの欲求を満たしつつ、安全に配慮することが重要です。
【6】無駄吠えや飛びつきをする
来客時のチャイム音に激しく吠え続けたり、散歩中にほかの犬や人に会うたびに飛びついたりする行動も、飼い主を悩ませるイタズラの一種と捉えられます。
これらの問題行動の原因は、警戒心や恐怖心、あるいは興奮や「遊んでほしい」という要求のあらわれなど多岐にわたります。特に社会化期に十分な経験を積んでいない犬は、未知の対象に対して過剰に反応することがあります。
これらの行動は、放置すると習慣化し、周囲に迷惑をかけるだけでなく、犬自身にとっても大きなストレスとなるため、早期のトレーニングやしつけによってコントロールを教える必要があります。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
犬はなぜイタズラするの?4つの原因と心理
愛犬がなぜイタズラをするのか、その心理を理解することは問題解決への第一歩です。飼い主がその心理を読み解き、原因に応じた適切な対応をするために、考えられる4つのイタズラの原因を解説します。
①退屈でエネルギーが有り余っている
犬がイタズラをする大きな原因の一つに、退屈やエネルギーの発散不足があります。特に活動量の多い犬種や若い犬は、毎日の散歩だけではエネルギーを消費しきれず、その有り余った体力を室内での破壊行動などに向けてしまうことがあります。
人間が暇な時に何か手持ち無沙汰になるのと同様に、犬も刺激が足りないと退屈を感じ、自分で遊びを見つけようとします。その結果が、家具をかじる、物を散らかすといったイタズラにつながるのです。
②留守番中の寂しさをまぎらわしている
飼い主が外出している留守番中に限ってイタズラをする場合、分離不安が原因である可能性が考えられます。
犬は本来、群れで生活する動物であるため、一匹で過ごすことに強い不安や寂しさを感じることがあります。その不安感を紛らわすために、飼い主の匂いがついた靴や服をかじったり、物を破壊したりすることで安心感を得ようとします。
また、物を壊すという行為自体が、不安な気持ちから気をそらすための転嫁行動となっている場合もあります。このタイプのイタズラは、叱るだけでは改善が難しく、犬が安心して留守番できるような環境づくりやトレーニングが必要です。
関連記事:子犬は何時間お留守番できる? 一人暮らしで飼う際の注意点を紹介
③物を壊したいという本能的な欲求
犬が物を噛む、あるいは壊すという行動は、本能に根差した欲求の一つです。
子犬期には歯の生え変わりで歯茎がむずがゆくなるため、物を噛むことでその不快感を和らげようとします。成犬になっても、犬は口を使って物の感触を確かめたり、顎を使う欲求を満たしたりします。特に狩猟犬としての本能が強い犬種は、動く物を追いかけ、捕まえ、噛むという一連の行動に喜びを感じます。
飼い主が好きなものではなく、犬自身が好きな感触のものを破壊対象に選ぶこともあります。この本能的な欲求そのものをなくすことはできないため、欲求を安全な形で満たせる代替案を用意することが重要です。
④飼い主にかまってほしいサイン
犬は非常に賢く、どうすれば飼い主の注意を引けるかを学習します。過去にイタズラをした際に、飼い主が慌てて駆け寄ってきたり、大声で名前を呼んだりした経験があると、「イタズラをするとかまってもらえる」と誤学習してしまうことがあります。その結果、飼い主の気を引くためにわざと目の前でイタズラをするようになるのです。
この場合、犬は叱られていることよりも、注目されていることをポジティブに捉えてしまっている可能性があります。イタズラに対して過剰に反応することが、かえって行動を強化させているケースは少なくありません。
愛犬のイタズラを防ぐための効果的な対策

愛犬のイタズラを効果的に防止するためには、叱るだけでなく、そもそもイタズラをしない、できない環境を作ることが重要です。ここでは、すぐに実践できる具体的な防止策をいくつか紹介します。愛犬の性格や生活環境に合わせて、最適な対策を取り入れてみましょう。
物理的にイタズラができない環境を整える
犬のイタズラ防止の基本は、問題行動を起こせない環境を作ることです。まず、かじられたくないものや誤飲の危険があるものは、犬の届かない場所に片付けましょう。
特に電気コードはカバーで覆う、家具の裏に隠すなどの対策が必須です。ゴミ箱は蓋つきのものに変え、食べ物は戸棚や冷蔵庫にしっかりしまいます。
また、留守番時や目を離す際には、ケージやハウス、あるいはサークルで囲った安全なスペースで過ごさせることも有効な手段です。
トイレのシーツを破いてしまう場合は、メッシュ付きのトイレトレーを使用すると良いでしょう。飼い主の靴など、匂いがついたものを好む場合は、靴箱にきちんと収納することを徹底します。
散歩や遊びの時間を増やして欲求を満たす
犬のイタズラの多くは、有り余ったエネルギーやストレスが原因です。そのため、毎日の散歩や遊びの時間を充実させ、心身ともに満足させてあげることが非常に効果的な対策となります。
散歩はただ歩くだけでなく、コースを変えたり、匂い嗅ぎの時間を十分に取ったりすることで、犬にとって良い刺激になります。ドッグランなどで思い切り走らせるのも良いでしょう。
室内では、「持ってきて」遊びや知育トイを使った遊びを取り入れ、頭と体を使わせます。
飼い主とのコミュニケーションを伴う遊びは、犬の満足感を高め、問題行動の減少につながります。十分な運動と刺激によって、犬は落ち着きを取り戻し、室内でのイタズラの必要性を感じなくなります。
イタズラに代わるおもちゃを与える
犬が持つ「噛みたい」「壊したい」という本能的な欲求を、イタズラ以外の方法で満たしてあげることが重要です。そのためには、犬が安全に噛んだり壊したりできるおもちゃを与えることが有効です。
例えば、硬さや素材の異なるさまざまなおもちゃを用意し、愛犬の好みを探してみましょう。中にフードを隠せる知育おもちゃは、退屈しのぎに最適です。また、噛むとキューキューと音が鳴るおもちゃは、犬の狩猟本能を刺激し、夢中にさせることができます。
イタズラされやすいものと似た感触のおもちゃを与えることで、興味をそちらに移すことも可能です。ただし、壊れたおもちゃの誤飲には注意し、定期的に点検・交換してください。
留守番中にイタズラさせない対策をする
留守番中の犬のイタズラを防ぐには、犬が安心して静かに過ごせる環境を整えることが大切です。外出前には長めの散歩に行くなどして、犬を適度に疲れさせておくと、留守番中は寝て過ごしてくれることが多くなります。
また、飼い主の匂いがついたタオルやおもちゃをケージに入れておくと、犬が安心感を得やすくなります。コングなどの知育トイにウェットフードやおやつを詰めておけば、長時間それに集中してくれるため、退屈や寂しさを紛らわすのに効果的です。
外出時と帰宅時に過剰に構いすぎず、さりげなく出入りすることも、犬の分離不安を助長させないためのポイントです。
犬のイタズラの正しい叱り方とNG対応
愛犬がイタズラをした時、感情的に怒鳴ってしまうこともあるかもしれません。しかし、効果のない叱り方は犬を混乱させ、信頼関係を損なうだけです。ここでは、犬に伝わる正しい叱り方と、避けるべきNG対応について解説します。
効果的に伝えるための正しく叱るコツ
犬のイタズラに対するしつけで最も重要なのは、現行犯の瞬間に叱ることです。時間が経った後では、犬は自分がしたことと、叱られたことが結びつかず、なぜ叱られたのかを理解できません。
イタズラをしているその場で、「ダメ」「イケナイ」など、短く低い声で一貫した言葉を使って注意します。このとき、犬の目を見て真剣な表情で伝えることがポイントです。
叱った後は、犬がイタズラをやめたらすぐに褒める必要はありません。しばらく無視をすることで、「イタズラをすると飼い主がかまってくれなくなる」と学習させます。
犬がしょんぼりして反省しているように見えても、それは飼い主の怒りのサインを察知しているだけの場合がほとんどです。一貫した態度で、何が良くて何が悪いのかを根気強く教えていくことが効果的なしつけにつながります。
ついやってしまいがち!NGな叱り方
犬を叱る際に、ついやってしまいがちなNG対応がいくつかあります。まず、大声で名前を呼びながら怒ることは避けるべきです。犬は自分の名前を呼ばれることを「悪いこと」と関連付けてしまい、名前を呼んでも来なくなってしまう可能性があります。
また、手で叩いたり、物を投げつけたりする「体罰」は許されない行為です。ただむやみに犬に恐怖心を与えるだけで、信頼関係を著しく損ないます。犬はなぜ怒られるのかを理解するのではなく、飼い主そのものを怖い存在だと認識してしまいます。
さらに、時間が経ってから発見したイタズラの痕跡に対して説教をしても、犬は何に対して叱られているのか理解できず、ただ混乱するだけです。
【よくある質問】犬のイタズラで注意すべきことは?

犬のイタズラに関する悩みは尽きないものです。ここでは、子犬のイタズラ対策から効果的なイタズラ防止グッズまで、犬のイタズラに関するよくある質問に答えていきます。
好奇心旺盛な子犬期のイタズラ対策とは?
子犬期は、見るものすべてが新しく、好奇心から口に入れて確かめようとするため、イタズラが最も多い時期です。この時期の対策として最も重要なのは、誤飲を防ぐための環境整備です。電気コードや薬品、小さな物などを徹底的に片付け、安全な空間を確保しましょう。
トイレの水の誤飲などを防ぐため、使用時以外は蓋を閉める習慣もつけましょう。また、噛んでも良いおもちゃを複数用意し、子犬の噛みたい欲求を満たしてあげることが不可欠です。この時期のしつけは、成長後の行動に大きく影響するため、根気強く向き合いましょう。
犬のイタズラは何歳ごろまで続くの?
犬のイタズラがいつまで続くかは個体差が大きいですが、一般的には心身ともに成熟し、落ち着きが出てくる1歳半から2歳頃には減少する傾向にあります。
子犬期に見られる好奇心旺盛なイタズラや、歯の生え変わりによる甘噛みなどは、成長とともに自然と収まることが多いです。しかし、エネルギーの発散不足や分離不安などが原因のイタズラは、年齢を重ねても続く可能性があります。
成犬になってもイタズラが減らない場合は、その行動の根本的な原因を探り、運動量を増やしたり、コミュニケーションの方法を見直したりするなどの対策が必要です。
成犬になってもイタズラが直らない場合は?
成犬になってもイタズラが続く、あるいは急にイタズラをするようになった場合は、その背景に何らかの原因が隠れている可能性があります。運動不足やストレス、飼い主とのコミュニケーション不足、あるいは生活環境の変化などが引き金になることがあります。
特に夜中に破壊行動をするなど、これまでにない行動が見られる場合は注意が必要です。痛みや不快感といった体調不良が原因で問題行動を起こしている可能性も考えられます。
行動が急に変化した場合は、まずは健康状態に問題がないか、かかりつけの獣医師に相談してみることをおすすめします。それでも改善しない場合は、ドッグトレーナーなど専門家の助けを借りるのも一つの方法です。
犬がわざとトイレを失敗するのもイタズラなの?
犬がわざとトイレを失敗するように見える行動は、実は「飼い主の注意を引きたい」「不安やストレスを感じている」といった心理的なサインであることが多くあります。環境の変化や構ってもらえない寂しさが原因で、わざと失敗してみせるのです。
また、ただのイタズラではなく、トイレの場所やタイミングに不満がある可能性も考えられます。叱るだけでは逆効果になることもあるため、まずは原因を探り、安心できる環境を整えてあげるように心がけましょう。
犬のイタズラ防止グッズで効果的なものは?
犬のイタズラ防止に役立つグッズは数多く市販されています。代表的なものとしては、フードを中に入れて時間をかけて取り出させるタイプの知育トイが挙げられます。これは犬の退屈な時間を減らし、集中力を養うのに効果的です。
また、家具やコードなど、かじられたくない場所に塗布する苦味成分のスプレーも販売されています。犬が嫌がる味を学習させることで、その場所をかじるのを防ぐというグッズです。
噛む力が強い犬には、壊れにくい丈夫な素材でできたおもちゃを選ぶことが重要です。愛犬の性格やイタズラの種類に合わせて、これらのグッズをうまく活用することで、問題行動を軽減させることが期待できます。
まとめ│犬のイタズラは原因や心理を探ることが大切!
犬のイタズラは、エネルギーの発散不足や本能的な欲求、飼い主へのサインなど、さまざまな理由から起こります。
その犬の行動の背景を理解し、環境を整えたり、ストレス解消のためにしっかりと遊びや散歩に付き合ったり、一貫したしつけを行ったりすることで、問題行動は改善に向かいます。愛犬とのコミュニケーションを大切にしながら、根気強く向き合っていきましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
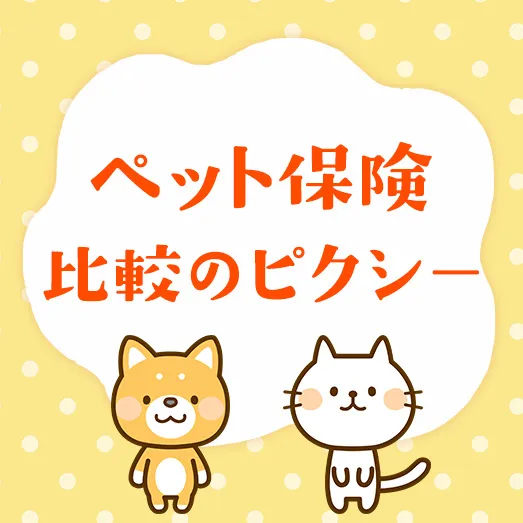
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








