
子猫を家族に迎えたら、健康維持のために、ブラッシングなどのお手入れが欠かせません。しかし、初めて子猫を飼う方にとっては、ブラッシングをいつから始めるべきか、どんなやり方があるのか、また、子猫が嫌がる場合にはどうすればよいのかなど、疑問や不安も多いことでしょう。
本記事では、以下のことを中心に、子猫のブラッシングについて詳しく解説します。
- 子猫は何か月からブラッシングが必要?
- 子猫にブラッシングが必要な理由とは?
- ブラッシングを嫌がる子猫にはどうする?
- ブラッシング好きな猫になってもらうには?
- 子猫におすすめなブラシはある?
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
子猫のブラッシング│いつから始める?頻度は?

子猫のブラッシングはいつから始めるのがよいのか、そして頻度はどれくらいで行うべきなのか、迷う人は多いかもしれません。ここでは、ブラッシングを始める時期や、頻度の目安などを解説します。
生後1か月頃から触れる練習をスタート
子猫のブラッシングは、生後1か月ごろから手で優しくなでる練習を始めるのが理想です。生後2〜3か月ごろを過ぎると本格的に行う準備が整います。
子猫のブラッシング練習のポイントは、いきなりブラシを使うのではなく、まずは飼い主の手で触られる心地よさを教えてあげること。背中や頭、耳、足先など少しずつ範囲を広げることで、子猫との信頼関係も築けます。
また、幼いころから体を触られることに慣れておくと、将来的なブラッシングや爪切り、耳掃除などのお手入れがスムーズになり、猫のストレスも軽減できます。焦らず子猫のペースに合わせて少しずつ慣らしていくことが、ブラッシングを好きになってもらう第一歩です。
短毛種と長毛種のブラッシング頻度
子猫のブラッシング頻度は、被毛の長さによって調整することが大切です。
短毛種の子猫の場合、週に1回程度のブラッシングで十分とされています。柔らかいブラシを選び、子猫の皮膚を傷つけないように優しくブラッシングすることを心がけましょう。
一方、長毛種の子猫は毛が絡まりやすいため、毎日こまめなブラッシングが必要です。抜け毛が増える換毛期には、1日に2回行うとよいでしょう。被毛の絡まりやすい耳の後ろやあご、足のあたりはとくに念入りにブラッシングしてあげましょう。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
猫のブラッシングの3つのメリット
猫のブラッシングには、健康面や精神面においても多くのメリットがあります。ここでは猫にブラッシングをするメリットを3つ挙げてご紹介します。
毛玉を吐き出す「毛球症」の予防
猫は毛づくろいで体を清潔に保ちますが、その際に抜け毛を飲み込むことがあります。通常は便や吐き戻しで排出されますが、大量に飲み込むと胃で毛玉になり、「毛球症」を引き起こすことがあります。
猫が毛球症になると嘔吐や食欲不振、便秘などがあらわれ、重症の場合は手術が必要になることもあります。定期的なブラッシングで抜け毛を取り除くことは、毛球症の予防に非常に有効で、とくに換毛期や長毛種の猫では毎日のケアが大切です。
皮膚トラブルやノミ・ダニへの対策
ブラッシングは、猫の皮膚トラブルやノミ・ダニなどの外部寄生虫の早期発見にも役立ちます。被毛をかき分けながら皮膚をチェックすることで、普段は見えにくい傷や炎症、フケ、赤み、かゆみなどに気づくことができるのです。
ノミやダニを見つければ、早期に駆除や治療などの対策が可能です。また、定期的に抜け毛を取り除くことで毛が密集して湿気がこもるのを防ぎ、皮膚病のリスクも減らせるでしょう。
スキンシップで信頼関係が深まる
ブラッシングは被毛の手入れだけでなく、飼い主と猫の信頼関係を深めるスキンシップの時間にもなります。優しくなでられることで猫は安心感を得て、「なでられる=心地よい」と記憶します。
リラックスしたブラッシングはマッサージ効果もあり、ストレス軽減につながります。子猫のうちから定期的に行うことで、人に世話されることに慣れ、将来も落ち着いてグルーミングを受け入れられるようになります。
猫はブラッシングしないとどうなる?

猫は自分で毛づくろいをしますが、飼い主がブラッシングをしないでいると、健康や生活にさまざまな影響が出る可能性があります。たとえば以下のような問題が起きかねません。
- 毛球症から食欲不振などに
- 被毛や体臭にトラブル発生
- 皮膚病や感染症のリスク
- ストレスや行動に悪影響
ブラッシングを怠ると、猫の毛玉が増えてしまったり、皮膚トラブルや感染症のリスクが高まったりするでしょう。毛が絡まって不快な状態が続くと、かゆみや痛みから、噛み癖や攻撃的な威嚇などの問題行動につながる場合もあります。
ブラッシングを通して快適な環境と信頼関係を作ることが、猫の精神的な安定にもつながるでしょう。
子猫用ブラシの選び方|種類と特徴を解説
子猫のブラッシングには、適切なブラシを選ぶことが非常に重要です。ここでは猫用のブラシの種類、子猫におすすめのブラシや長毛種・短毛種それぞれに合ったブラシを解説します。
猫のお手入れ用ブラシの種類は?
猫のお手入れ用ブラシには、それぞれ特徴があり、被毛のタイプや用途に応じて使い分けることができます。以下の表でおもなブラシの種類と特徴をまとめました。
| ブラシの種類 | 特徴・用途 |
| ピンブラシ | 先端が丸く扱いやすい。被毛のほぐしや軽いマッサージに適している。 |
| ラバーブラシ | ゴムやシリコン製で、抜け毛の除去とマッサージ効果を兼ね備える。 |
| 獣毛ブラシ | 豚毛や馬毛など天然素材で、被毛にツヤを与える効果が期待できる。 |
| スリッカーブラシ | 細い金属ピンが密集しており、毛のもつれや絡まりを効率的にほぐすのに最適。 |
| コーム | 仕上げや顔周りなど細かい部分のブラッシングに便利。 |
| グルーミンググローブ | 手にはめてなでるように使えるため、ブラシを嫌がる猫にも受け入れやすい。 |
ブラッシングを嫌がる猫におすすめなのは、柔らかいラバーブラシやグルーミンググローブです。子猫の被毛の特徴や性格にあわせて、最適なブラシを選んであげましょう。
子猫の初めてのブラッシングにおすすめのブラシは?

子猫の初めてのブラッシングには、皮膚を傷つけにくい柔らかい素材のブラシがおすすめです。優しい刺激でブラッシングに慣れさせることで、子猫がブラッシングを楽しい時間だと認識しやすくなります。
子猫におすすめのブラシは以下のとおりです。
- ラバーブラシ
- ピンブラシ
- グルーミンググローブ
ラバーブラシは、シリコンやゴム製の柔らかいブラシで、優しくマッサージするようにブラッシングできるため、子猫のデリケートな皮膚にも負担をかけにくいという特徴があります。
ピンブラシを選ぶ際は、ピンの先端が丸くなっているものを選ぶと、皮膚への刺激を和らげることができます。また、グルーミンググローブ(グローブ型のブラシ)は、飼い主が猫をなでる感覚で使えるため、ブラシに慣れていない子猫や、触られるのが苦手な子猫にも安心して使用できます。
【被毛別】長毛種や短毛種の子猫にはどんなブラシ?

子猫の被毛の長さによって、おすすめのブラシの種類は異なります。
- 短毛種におすすめ:ラバーブラシ・獣毛ブラシ
- 長毛種におすすめ:スリッカーブラシ・ピンブラシ・コーム
短毛種の子猫には、被毛に自然なツヤを与える獣毛ブラシ、抜け毛を効率的に集められるラバーブラシがおすすめです。ラバーブラシは、皮膚に心地よいマッサージ効果も与えられます。
一方、長毛種の子猫、たとえばラグドールのような豊富な被毛を持つ猫には、スリッカーブラシやピンブラシ、コームが適しています。スリッカーブラシは、絡まった毛や毛玉をほぐすのに効果的ですが、皮膚を傷つけないために力を入れすぎないことを意識しましょう。
ピンの先端が丸いピンブラシは、被毛の奥まで届きやすく、毛玉を予防するのに役立ちます。コームは、とくに毛玉ができやすい耳の後ろや足回り、しっぽなどの部分の毛並みを整えるのに便利です。
【4ステップで解説】子猫のブラッシングのやり方
子猫のブラッシングは、正しいやり方と順序で行うことで、猫が嫌がらずに快適に受け入れてくれるようになります。ここでは、子猫のブラッシングをスムーズに進めるための4つのステップを解説します。
ステップ1:ブラシの存在に慣れる
まず、子猫にブラシの存在自体に慣れてもらうことから始めましょう。いきなり体をブラッシングするのではなく、ブラシをおもちゃのように見せて遊ばせたり、においを嗅がせたりして、怖いものではないと認識させます。
子猫がブラシに興味を示し、警戒心がない状態になったら、ブラシの毛先に手で触れて、優しい感触であることを教えてあげてください。この段階を焦らず、子猫がブラシに対して安心感を抱くまで、時間をかけて慣らしていくことが大切です。
ステップ2:嫌がりにくい場所から
子猫がブラシの存在に慣れてきたら、次は実際にブラッシングを試みます。最初は猫が嫌がりにくい場所から始めるのがコツです。
一般的に、猫が触られて喜ぶのは、頭や首周り、あごの下などです。これらの場所は、猫自身が毛づくろいしにくい箇所でもあるため、気持ちよいと感じやすい傾向があります。力を入れすぎず、なでるような感覚でブラシを動かすことが重要です。
ステップ3:毛の流れに沿ってゆっくり
猫がブラッシングに慣れてきたら、まずは頭から首、背中にかけて、毛の流れに沿ってゆっくりとブラシを動かしましょう。力を入れすぎると皮膚を傷つけたり、痛みを与えてしまう可能性があるため、軽いタッチで行うことが大切です。
とくに長毛種の場合は、毛が絡まりやすいので、無理に引っ張らず、毛玉がある場合は根元を指で押さえながら、丁寧にほぐすようにブラシをかけましょう。
慣れてきたら、毛の流れとは逆方向にブラシを動かすことで、奥に入り込んだ抜け毛や絡まった毛を効率的に取り除くことができます。尻尾は猫によっては嫌がる場合もあるため、様子を見ながら慎重に触れてみましょう。
ステップ4:終わったらご褒美をあげる
ブラッシングが終わったら、かならず子猫にご褒美をあげましょう。おやつを与えたり、大好きなおもちゃで遊んであげたり、たくさん褒めて撫でてあげたりすることで、ブラッシングが楽しいこと、良いことだと認識させることができます。
このポジティブな経験を繰り返すことで、子猫はブラッシングに対してよい印象を持つようになり、次からのブラッシングもスムーズに受け入れてくれるようになります。とくに、ブラッシング中に大人しくできた時には、しっかりと褒めてあげることが大切です。
子猫がブラッシングを嫌がる理由は?
子猫がブラッシングを嫌がるのは、単にブラッシングやブラシの感触に慣れていないことが大きな理由です。幼少期に触れられる経験が少ない子猫や、社会化が十分でない子猫は、人に体を触られること自体に抵抗を感じやすくなります。
子猫がブラッシングを嫌がるおもな理由は以下のとおりです。
- 過去の痛い経験やトラウマ
- ブラッシングのやり方が合わない
- 使用しているブラシが合っていない
- 猫のそのときの気分や一時的な感情
- 警戒心が強い怖がりな性格
- 病気や体調不良で敏感になっている
ブラッシングのやり方が間違っている、拘束時間が長すぎる、あるいは気分ではないといった一時的な感情も、子猫がブラッシングを拒否する要因となります。もしブラッシング中に暴れる、噛むといった行動が見られる場合は、これらの中に原因があるかもしれません。
もし、猫が極端にブラッシングを嫌がる場合は、ケガや病気による痛みが隠れていることもあるため、必要に応じて獣医師に相談すると安心です。
子猫が嫌がるときのブラッシング方法と慣らすコツ

子猫がブラッシングを嫌がる場合でも、焦らず少しずつ慣らしていくことが大切です。ここでは、子猫がブラッシングを嫌がるときの効果的な方法と、慣らすためのコツをいくつかご紹介します。
リラックスしている場所と時間帯に
子猫がブラッシングを嫌がる場合、まず試すべきは、子猫が最もリラックスしている場所と時間帯を選ぶことです。たとえば、お昼寝の後や食後など、落ち着いてまどろんでいる時が狙い目です。
また、子猫が普段からよく過ごすお気に入りの場所や、安心できる環境でブラッシングを始めるとよいでしょう。騒がしい場所や興奮している時には避け、静かで落ち着いた空間を選ぶことが重要です。
まずは手やガーゼでなでる練習から
ブラッシングを嫌がる子猫には、いきなりブラシを使うのではなく、まずは飼い主の手や柔らかいガーゼでなでる練習から始めましょう。
子猫が触られることに慣れていない場合、手で優しく体をなでることで「触ってもらうと気持ちがいい」というポジティブな経験を積み重ねさせることが大切です。
ガーゼを使う場合は、猫の毛の流れに沿って優しく拭くようにすると、軽い刺激で抜け毛を取り除く練習にもなります。このステップを十分に踏むことで、ブラシへの抵抗感を減らし、次の段階へスムーズに進めることが可能になります。
ストレスに気をつけ短時間で切り上げる
ブラッシングに慣れない子猫が嫌がる場合は、ストレスを与えないように細心の注意を払い、短時間で切り上げることが重要です。無理に長時間ブラッシングを続けると、子猫はブラッシングを嫌なものとして認識してしまい、今後さらに抵抗するようになる可能性があります。
最初は1回あたり数秒程度から始め、少しずつ時間を延ばしていくようにしましょう。1回のブラッシングは3分程度が理想的です。子猫の様子をよく観察し、少しでも嫌がる素振りを見せたら、すぐに中止してください。
おやつやおもちゃで気をそらしながら
子猫がブラッシングを嫌がる場合、おやつやおもちゃを使って気をそらしながら行うのも有効な方法です。
たとえば、子猫の大好きなおやつをペースト状にして紙パックなどに塗り、それを舐めさせている間に後ろからそっとブラシでなでる「おやつペロペロ作戦」は、ブラッシング嫌いを克服するのに効果的かもしれません。
また、お気に入りのおもちゃで遊んであげながら、その隙に素早くブラッシングをするのもよいでしょう。子猫がブラッシング以外のことに集中している間に、手早く済ませることで、ブラッシングへの意識を逸らすことができます。
嫌がるときは無理強いしないこと
最も重要なのは、子猫がブラッシングを嫌がるときは絶対に無理強いしないことです。
とくに、暴れる、噛むといった抵抗が見られる場合は、すぐに中断してください。
無理に押さえつけてブラッシングを行うと、子猫はブラッシングそのものだけでなく、飼い主に対する不信感を抱くようになり、将来的にさらなる問題行動につながる可能性があります。一度嫌いになってしまうと、再び慣れさせるのは非常に難しくなります。
子猫をブラッシングするときの注意点
子猫をブラッシングする際には、いくつかの注意点を守ることが大切です。これらは子猫の健康と安全を守り、ブラッシングを楽しい習慣にするために不可欠です。
毛玉や皮膚の異常をチェック
ブラッシングは単に抜け毛を取り除く行為に留まらず、子猫の健康状態をチェックする大切な機会です。ブラッシング中は、被毛をかき分けて皮膚に赤みや腫れ、傷、フケがないか、ノミやダニなどの寄生虫がいないかなど、細かく観察しましょう。
とくに、短毛種の子猫でも皮膚の状態を確認するため、週に1回程度の頻度でブラッシングを行うことが推奨されています。もし何か異常を発見した場合は、早めに獣医師に相談することが重要です。早期発見・早期治療は、子猫の健康を守る上で非常に役立ちます。
毛玉は無理に引っ張らない
ブラッシング中に毛玉を見つけても、決して無理に引っ張らないでください。毛玉を無理に引っ張ると、子猫の皮膚に強い痛みを与えてしまい、ブラッシングを嫌がる原因となるだけでなく、皮膚を傷つけてしまう恐れがあります。
毛玉ができてしまった場合は、根元を指でしっかりと押さえ、毛玉の先端から少しずつブラシやコームで丁寧にほぐしていきましょう。もし自宅でほぐすのが難しい場合は、無理せず動物病院やプロのトリマーに相談することをおすすめします。
お腹や顔まわりはとくに優しく触れる
子猫のブラッシングでは、お腹や顔まわりなど、とくにデリケートな部分は優しく触れることが非常に重要です。多くの子猫はこれらの部位を触られることに敏感で、嫌がる傾向があります。
お腹のブラッシングは、子猫を抱き上げるかあおむけにして行うとよいのですが、嫌がる場合は無理強いせず、できる範囲で短時間で済ませましょう。
顔まわり、とくに耳の後ろやあご、頬は毛が絡まりやすい箇所でもあるため、コームなどを使って慎重に、顔の中心から外側に向かって優しくブラッシングしてください。目や耳を傷つけないよう注意し、ブラシの刺激が強くなりすぎないように心がけましょう。
まとめ|子猫のブラッシングは早めに慣らして一生の習慣に
子猫のブラッシングは、単なる被毛ケアに留まらず、健康維持、皮膚トラブルの早期発見、そして飼い主との信頼関係構築に不可欠な大切なお手入れです。
子猫が幼い頃から、優しく、段階的にブラッシングに慣れさせることで、将来にわたってストレスなくお手入れを受け入れてくれるようになります。子猫のデリケートさに配慮しながら、ブラッシングを一生の楽しい習慣にしていきましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
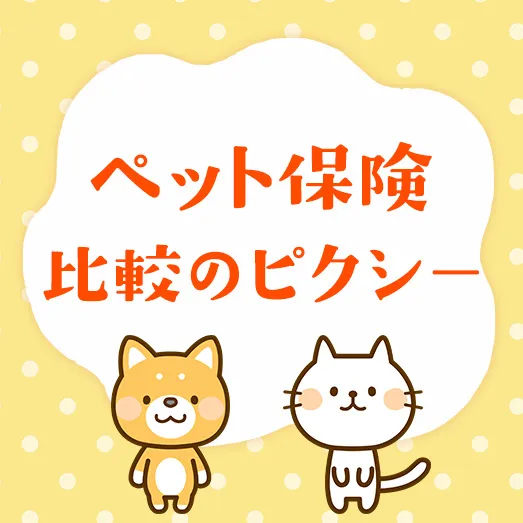
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








