
「マンチカンは病気にかかりやすい」「骨折しやすい」といった話を聞いたことがあり、飼うにあたって不安を覚えている方もいるのではないでしょうか。
どのような猫種でも、病気や骨折をしてしまうことはあります。大切なのは、早期に異常を発見し、早めに治療を受けさせることです。
そこで、この記事ではマンチカンがかかりやすいおもな病気に罹患したときや骨折したときの症状について解説します。飼育上の注意点についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
- マンチカンの特徴
- マンチカンのかかりやすい病気や骨折の特徴
- マンチカンの飼育上の注意点
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
マンチカンの特徴

マンチカンというと、足の短い愛らしい姿のイメージがありますが、実際には普通の足の長さの子もいます。毛色や柄もバリエーションが豊富です。
ここでは、性格や容姿、歴史といったマンチカンの特徴について解説します。
性格|好奇心旺盛で人懐っこい
マンチカンはとても人懐こく、やさしくて穏やかです。猫は基本的に警戒心の強い生き物ですが、マンチカンは初めて会う人でもあまり警戒せずなつく傾向にあります。先住猫やほかのペットがいても、問題になることは少ないでしょう。
甘えん坊で、飼い主さまに深い愛情を抱き、そばによってすりすりしたり膝に乗ったりする子も珍しくありません。
好奇心も旺盛で、活発に活動します。おもちゃで遊んでもらうのも喜ぶので、1日に1度は時間を取って相手をしてあげましょう。
容姿の特徴|短足だけではなく長足も
個体差はありますが、成猫のマンチカンは体重3~5kg、体長60cmほどとされます。短足のイメージが強いマンチカンですが、実際には一般的な猫と同じくらいの長さの足(長足)の子も珍しくありません。短足と長足の中間くらいの中足の子もいます。
歴史的にさまざまな猫と交配されてきた経緯があるため、毛色や模様はバラエティ豊かです。ホワイト、ブラック、ブラウン、クリーム、タビー、ミックスなどがあり、世界最大の血統登録団体であるTICA(国際猫協会)ではどの色も認めています。また、短毛種と長毛種がいますが、毛の色や長さによる性格の違いなどはありません。
瞳の色もさまざまな違いがあり、ヘーゼルやグリーン、ゴールド、ブルー、オッドアイなどの子がいます。
歴史|突然変異から始まる
マンチカンは、突然変異で自然に生まれた比較的新しい猫種です。足の短い猫については1944年ごろから報告されています。ただし、現在のマンチカンのルーツとなったのは1983年に北米のルイジアナ州で見つかった足の短い猫でした。その猫が生んだ子猫にも短足が多かったことで、本格的に繁殖が始まります。
1991年にキャットショーに出たときは「突然変異で生まれた」とみなされました。しかし、その後に各地で足の短い猫が見つかったため、世界最大規模の血統登録団体TICAによって新しい猫種として公認されるにいたります。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
マンチカンがかかりやすい病気の種類と骨折

公的なデータはありませんが、一般にマンチカンの寿命は11~13歳程度とされます。健康に長生きしてもらうためには、かかりやすい病気の特徴を知っておき、早期発見に努めることが大切です。
ここでは、マンチカンに多い病気や骨折したときに見られる症状について解説します。
椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、背骨と背骨の間にある椎間板が変形し、神経を圧迫することで起こる病気です。マンチカンの短足種は足が短いために四肢の骨や関節に負担がかかりやすく、椎間板ヘルニアになりやすいとされています。肥満による椎間板への負担の増大や高い場所からの落下による衝撃なども発症を引き起こす要因です。
発症すると、以下のような症状があらわれます。
- (初期)背骨を触ると腰を落とす、嫌がる
- ふらつく
- 足を引きずる
- 運動を嫌がり横になる
- 歩行困難になる
- 排泄できなくなる
早期治療を始めれば悪化が防げるので、様子がおかしいなと感じたらすぐに受診しましょう。重度になると外科手術が必要になります。
猫伝染性腹膜炎(FIP)
猫伝染性腹膜炎は、猫腸コロナウイルスの変性が原因で起こる病気です。猫腸コロナウイルスを保有している猫自体は珍しくなく、感染しても症状が出ないケースは珍しくありません。しかし、なんからの要因で体内に入ったウイルスが遺伝子変異をおこすと、猫伝染性腹膜炎を発症します。
症状はウェットタイプとドライタイプに大きく分類され、同時に2つのタイプを発症することもあります。おもな症状は以下のとおりです。
- ウェットタイプ:腹膜炎・胸膜炎が起こり、腹水や胸水がたまる
- ドライタイプ:多臓器に肉芽腫を形成する
- 元気を失い、食欲をなくす
- 体重が減る
- 熱をだす
- 下痢や嘔吐が起こる
- 苦しそうな呼吸をする
症状に対する対症療法をおこなうことが一般的です。治療費は高額になりますが、海外で承認された薬を輸入して治療する方法もあります。
毛球症
毛球症は、毛づくろいのときに飲みこんだ毛が排出されずに腸や胃にたまって起こる症状のことです。猫はきれい好きでよく毛づくろいをします。通常、毛づくろいの際に飲み込んだ毛は便や吐き戻しで排出されるため、問題ありません。
しかし、うまく出ずにたまってしまうと、以下のような症状を引き起こすことがあります。
- 食欲が低下する
- 便秘になる
- お腹を触られるのを嫌がる
- 腸閉塞を起こす
毛球を出しきれずに何度も吐くと胃液によって食道が荒れ、逆流性食道炎を起こすことがあります。胃の中で毛球が大きくなりすぎると吐きだせないため、内視鏡による摘出や手術が必要です。さらに、小腸に進むと詰まって腸閉塞を起こし、放置していると命にかかわります。
外耳炎
外耳炎は、耳の入り口から鼓膜までの「外耳道」に炎症が起こる病気です。マンチカンに限らず、一般に猫は外耳炎にかかりやすい傾向にあります。発症する原因は、細菌や真菌の増殖、寄生虫(ダニ)の侵入、植物の種子やごみなどの異物が入ったことによる刺激、アレルギーなどさまざまです。
発症すると、以下のような症状が見られます。
- 耳をかゆがり、しきりにかく
- 頭を振ったりこすりつけたりする
- 外耳道や耳の内側が赤くなる
- 耳がにおう
- 耳垢が増える
自然治癒は難しいため、外耳炎が疑われるときは動物病院を受診しましょう。状態によって耳道を洗浄したり点耳薬を投与したりして治療を進めます。アレルギーが原因のときは検査してアレルゲンの特定が必要です。
下部尿路疾患(下部尿路症候群)
下部尿路疾患は、特定の病気の名称ではなく、膀胱や尿道など下部尿路に発生する病気の総称です。たとえば、尿道炎や結石症、特発性膀胱炎などが挙げられます。
病気にもよりますが、発症すると以下のような症状が見られます。
- トイレに頻繁に入るがなかなか出ない
- 排尿の時間が長い
- 頻繁に陰部をなめる
- 排尿時に痛がって鳴く
- 血尿がでる
おしっこがまったくでなくなると、命にかかわります。1日以上排尿していないときは、すぐに病院を受診しましょう。
マンチカンに限らず、猫は下部尿路疾患にかかりやすい傾向にあります。いつでも新鮮な水がたっぷり飲めるように複数の水飲み場を設置し、トイレに入るのを嫌がらないように清潔に保つなどの工夫が必要です。
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症は、サイロキシンと呼ばれる甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで起こる病気です。過剰分泌が起こる原因は明らかになっていません。
サイロキシンは代謝を上げる働きがあるホルモンで、過剰な分泌によって必要以上の代謝が起こり、以下のようなさまざまな症状を引き起こします。
- 食欲が増すのにどんどん痩せる
- 水をがぶ飲みする
- 活発になる
- 攻撃的になる
- 嘔吐や下痢をする
一見すると元気で活発に動くため、病気だと気づけずに発見が遅れることがあります。愛猫が、食べている量のわりには痩せてきたというときは注意しましょう。シニア期になると発病率が上がります。
慢性腎臓病
腎臓病は腎臓が十分に機能しなくなる病気で、急性と慢性があります。急性腎臓病はウイルス感染などによって起こり、急激に悪化するため発病後は早急な治療が必要です。一方、慢性腎臓病は、長い期間をかけてゆっくり腎臓の機能が低下します。
慢性腎臓病にかかると、以下のような症状が見られます。
- 水をよく飲む
- 大量の色が薄いおしっこをする
- 口内炎や胃炎が起こる
- 食欲が減る
- 毛づやが悪くなる
完治は難しいものの、治療で症状の進行を遅らせることは可能です。点滴や投薬、食事療法などをおこないます。
遺伝性疾患|骨軟骨異形成症
骨軟骨異形成症は遺伝子疾患のひとつで、骨や軟骨に変形が生じます。マンチカンのほか、スコティッシュフォールドなどでも発症が多い病気です。
おもな症状は以下のとおりです。
- 痛みのせいで関節が動かしにくくなる
- 足をひきずったり、歩けなくなったりする
- 骨や軟骨に変形が生じる
鎮痛剤や抗炎症薬を投与して痛みを抑える、重度の場合は外科手術をおこなうなどの治療がおこなわれます。進行性の病気のため、早めの発見・治療が重要です。
骨折
猫は高い場所からジャンプしたときなどに骨折することがあります。マンチカンの短足種は、関節に負担がかかりやすいため骨折のリスクが高くなりますが、長足種でも骨折の危険は十分にあるため注意しましょう。
骨折したときに見られるおもな症状は、以下のとおりです。
- 骨折部位が腫れる
- 足を引きずる、歩けなくなる
- 全身の発熱を伴う
- 異常な鳴き声をあげる
- 動かなくなりじっとしている
治療は、ギプスやプレートによって骨を固定する手術をおこない、鎮痛剤によって痛みを抑えます。交通事故に遭わないよう完全室内飼いにし、安全な飼育環境を整えることが大切です。
年齢別のマンチカンがかかりやすい病気
子猫と1歳をすぎた成猫とでは、かかりやすい病気に違いがあります。ここでは、子猫と成猫に分けて注意したい病気を紹介します。飼育上の注意点についても解説するので、参考にしてください。
子猫
0~1歳の子猫でとくに注意したいのは誤飲です。好奇心旺盛なため、意外なものを食べて喉やお腹に詰めるおそれがあります。ひも状のものや尖ったもの、薬などは誤飲すると大変危険なため、かならず手の届かない場所で保管しましょう。
親猫からもらった抗体がなくなるため、猫風邪にも注意が必要です。下痢や嘔吐もよく見られ、原因にはミルクやキャットフードがあわない、ストレス、寄生虫や感染症などがあります。
先述の猫伝染性腹膜炎は1歳未満で起こることが多いため、感染が疑われるときはすぐに受診しましょう。
成猫
1歳をすぎると、外耳炎や下部尿路疾患が多くなります。また、7歳以降はシニア期に入り、慢性腎臓病や甲状腺機能亢進症などの発症例も増えてきます。下部尿路疾患や腎臓病を予防するには、普段からこまめに水を飲ませることが欠かせません。日ごろからスキンシップをはかり、いつもと違う様子があればすぐに気づけるようにしておきましょう。
シニア期に入るほど病気のリスクも上がるので、こまめな観察が必要です。
マンチカンの病気や骨折を防ぐ飼育上の注意点

マンチカンがかかりやすい病気のいくつかは、飼う際に注意することである程度予防できます。ここでは、愛猫に健康で過ごしてもらうために注意したい飼育上のポイントについて解説します。
運動ができる環境を整える
愛猫が健康的な生活を送るためには、運動できる環境が必要です。とくに、マンチカンは体格や体質から太りやすいため、動ける環境を意識的に整える必要があります。肥満は椎間板ヘルニアや骨折などを招く要因になるため、要注意です。
広さがある安全なスペースを確保したくさん遊んであげましょう。活発で遊び好きなマンチカンにとって、飼い主さまと遊ぶことはよい運動になるだけでなく、ストレス解消にもつながります。
キャットタワーを設置する場合は、とくに短足種のマンチカンは足腰や関節に負担がかかりやすいため、低めのものを選びましょう。ステップ間隔も狭いものにしたほうが安心です。また、キャットタワーの下にはマットを敷くなど、安全に着地できる工夫を施しましょう。
フードと飲み水を管理する
マンチカンがかかりやすい下部尿路疾患や慢性腎臓病などの病気を防ぐには、水分を十分に摂取させる必要があります。猫に無理に飲ませることはできないので、新鮮な水を入れたボウルを複数設置し、いつでも飲める環境を整えましょう。
あまり水を飲まない場合は、ウェットフードを取り入れたりミルクやスープを与えたりするのも効果があります。
肥満を防ぐためには、運動させるだけでなく、高たんぱくで低カロリーな質の良いキャットフードを用意することも大切です。パッケージの記載にしたがって給餌し、与えすぎに注意しましょう。
ブラッシングで被毛ケアをする
マンチカンの被毛はあまり毛玉にはなりませんが、それでも毛球症になることはあります。予防するには、毎日のこまめなブラッシングが有効です。とくに、春や秋の毛が生え変わる時期は抜け毛も増えるので、丁寧にブラッシングをしましょう。
愛猫の毛並みが整うだけでなく、よいスキンシップの時間になります。「足を触るとひどく嫌がる」「皮膚にケガをしている」といった体調の変化や異常にも気づきやすく、早期発見にもつながります。
定期健診を受ける
マンチカンに限らず、猫は体調が悪いときに隠そうとする傾向があります。日ごろからきちんとお世話をしていても、初期の段階では病気を見過ごしてしまうことも少なくありません。
病院でチェックを受ければ、病気が見つかりやすくなります。そのため、定期的に検査を受けるようにしましょう。病院によって検査の内容は異なりますが、健診では問診・身体検査・血液検査・尿検査などをおこないます。
1~7歳は年に1回、7歳以降は半年に1回以上のペースで健康診断を受けるのが理想です。
まとめ│マンチカンのかかりやすい病気の特徴を知って早期発見に努めよう
マンチカンは短足のイメージが強いものの、実は長い足の子もいます。短足種はとても愛らしい姿ですが、関節や四肢に負担がかかりやすく、骨折リスクも高いので、飼育の際は十分に注意しましょう。とくに、椎間板ヘルニアや骨軟骨異形成症に注意が必要です。
肥満になりやすいので食事はしっかり管理し、適度に遊んで運動させましょう。キャットタワーを立てるときは、低めでステップの幅が狭いものにすると安心です。
日ごろから愛情を注いでお世話し、いつもと違う様子が見られたらすぐに動物病院を受診しましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
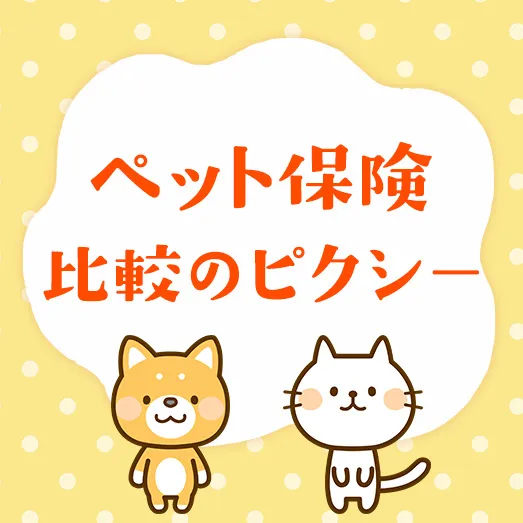
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








