
トイ・プードルはその愛らしい見た目と賢さで人気の高い犬種ですが、長く健康に過ごしてもらうためには、寿命やかかりやすい病気について知っておくことが大切です。特に、関節・目・皮膚・歯のトラブルが多いとされ、早期発見と適切なケアが寿命を延ばす鍵となります。
この記事では、トイ・プードルの平均寿命や遺伝的な病気のリスク、かかりやすい病気の症状・原因・予防策を詳しく解説し、飼い主さまができる健康管理のポイントを紹介します。
- トイ・プードルの平均寿命や健康を維持するポイント
- かかりやすい病気の種類と症状、原因について
- 病気を予防するための日常的なケア方法
- シニア期に必要な健康管理と定期検診の重要性
- よくある健康トラブルへの対処法と病院に行くべきタイミング
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
トイ・プードルの寿命と病気の基礎知識

トイ・プードルとできるだけ長く一緒に過ごすためには、寿命やかかりやすい病気について知っておくことが大切です。平均寿命は12〜15歳とされていますが、健康管理によってはさらに長生きすることもあります。
一方で、小型犬特有の病気にかかりやすい傾向もあります。大切な家族である愛犬が元気に過ごせるように、寿命や病気についての基礎知識を一緒に学んでいきましょう。
トイ・プードルの平均寿命はどのくらい?
トイ・プードルの平均寿命は12〜15歳といわれていますが、適切なケアを行うことで15歳以上生きることも珍しくありません。中には20歳近くまで元気に過ごす子もおり、日々の健康管理によって寿命を延ばすことが可能です。
寿命に影響を与える主な要因としては、遺伝的な特徴や生活環境、食事や運動の習慣などが挙げられます。特に、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、定期的に健康診断を受けることが健康寿命を延ばすポイントになります。
また、年齢を重ねるにつれて関節や歯、内臓の病気のリスクが高まるため、シニア期にはより丁寧なケアが必要です。愛犬が元気に長生きできるよう、日ごろから健康管理を意識して過ごしましょう。
トイ・プードルは遺伝的に病気になりやすいのか?
トイ・プードルは、小型犬特有の病気にかかりやすい傾向があります。特に関節・目・歯の病気が多く、これには遺伝的な要因も関係しています。
代表的な遺伝性疾患のひとつが膝蓋骨脱臼(パテラ)です。これは膝のお皿がずれる病気で、生まれつき関節が弱い犬に多く見られます。また、白内障や流涙症(涙やけ)も遺伝の影響を受けやすく、親犬が発症している場合は子犬も注意が必要です。
さらに、歯周病も小型犬に多い病気で、歯並びの影響で歯垢がたまりやすいことが原因となります。これらの病気を予防するためには、親犬の健康状態を確認することや、日々のケアを徹底することが大切です。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
トイ・プードルがかかりやすい病気と対策

トイ・プードルは、小型犬ならではの体の特徴から、関節や目、耳、皮膚、歯の病気にかかりやすい傾向があります。これらの病気は、早期に気づいて適切なケアを行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。
愛犬が元気に過ごせるように、病気の症状や原因を理解し、日常生活でできる予防対策を取り入れていきましょう。
関節の病気|膝蓋骨脱臼(パテラ)
膝蓋骨脱臼(パテラ)は、膝のお皿(膝蓋骨)が正常な位置からずれてしまう病気です。トイ・プードルのような小型犬に多く見られ、歩き方の異常や足を引きずるといった症状があらわれます。重度になると痛みを伴い、歩行が困難になることもあります。
この病気の主な原因は、遺伝的な要素や骨格の小ささです。特に関節が緩い犬は発症しやすく、ジャンプや激しい運動の繰り返しが悪化の要因になります。
予防のためには、滑りにくい床材を使い、膝に負担をかけない環境を整えることが重要です。また、適度な運動で筋力を維持し、肥満を防ぐことも効果的です。早期発見のために、日ごろから歩き方の変化に注意しましょう。
目の病気|流涙症(涙やけ)
流涙症(涙やけ)は、目の周りが赤茶色に変色し、目ヤニが増える病気です。トイ・プードルは目が大きく涙の分泌が多いため、特に発症しやすい犬種といえます。
原因としては、涙の排出異常が挙げられます。本来、涙は鼻へと流れる管(鼻涙管)を通って排出されますが、先天的に狭かったり詰まったりすると、涙があふれて目の周りが常にぬれた状態になります。また、アレルギーや細菌感染も原因のひとつです。
予防・対策として、毎日やわらかいガーゼやコットンで目の周りをやさしく拭き取ることが大切です。アレルギーが疑われる場合は、原因となる食べ物や環境を特定し、適切な対策をとるようにしましょう。
耳の病気|外耳炎
外耳炎は、耳の中の炎症によってかゆみや悪臭、耳垢の増加などの症状があらわれる病気です。トイ・プードルは垂れ耳のため耳の中が蒸れやすく、細菌やカビが繁殖しやすい環境になりやすいことから、外耳炎を発症しやすい犬種といわれています。
外耳炎の主な原因には、以下のようなものがあります。
- 耳の通気性の悪さ(湿気がこもることで細菌・カビが繁殖しやすくなる)
- 細菌やカビの増殖
- アレルギー反応
- 耳ダニの感染
予防のためには、定期的な耳掃除を行い、耳の中を清潔に保つことが大切です。また、シャンプーの際に耳に水が入らないように注意し、耳の通気を良くするために耳の毛を適度にカットすることも効果的です。
皮膚の病気|アレルギー性皮膚炎
アレルギー性皮膚炎は、強いかゆみや皮膚の赤み、脱毛などの症状を引き起こす病気です。トイ・プードルは皮膚がデリケートなため、アレルギー性皮膚炎にかかりやすい傾向があります。
主な原因は、以下のようなアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)です。
- 食物(特定の食材に対する反応)
- 花粉やハウスダスト(環境要因)
- ダニやカビ(室内環境による影響)
予防・対策としては、アレルゲンを特定し、できるだけ排除することが重要です。また、低刺激のシャンプーを使用し、定期的なスキンケアを行うことで、皮膚の健康を維持することができます。
歯の病気|歯周病
歯周病は、口臭や歯茎の腫れ、食欲低下などの症状を引き起こす口腔内の病気です。トイ・プードルはあごが小さく歯並びが密集しやすいため、歯垢や歯石がたまりやすく、歯周病になりやすい犬種といえます。
歯周病の主な原因は、歯垢や歯石の蓄積による細菌の増殖です。
- 歯垢が放置されると短期間で歯石に変わる
- 歯石がたまると歯茎に炎症が起こる
- 進行すると歯がぐらつき、最終的に抜けてしまうこともある
予防のためには、毎日の歯磨きを習慣化し、ときにはデンタルケア用のおもちゃを活用するのも効果的です。すでに歯石がついている場合は、獣医師による歯石除去を検討しましょう。
病気予防のために飼い主さまができること

トイ・プードルが健康で長生きするためには、日ごろの予防がとても大切です。関節や目、歯などのトラブルを防ぐためには、日常の健康チェックや適切な食事、運動管理が欠かせません。
また、病気の早期発見・早期治療のために、定期的な健康診断を受けることも重要です。ここでは、飼い主さまができる具体的な健康管理のポイントについて解説します。
日常の健康チェックポイント
愛犬の健康を守るためには、毎日の観察が欠かせません。特に目・耳・歯・関節の状態は、以下のポイントをこまめにチェックしましょう。
| チェック項目 | 確認するポイント |
| 目 | 充血していないか、目ヤニが増えていないか |
| 耳 | 悪臭がないか、耳垢が多くないか |
| 歯 | 口臭が強くないか、歯茎が腫れていないか |
| 関節 | 歩き方がぎこちなくないか、足を引きずっていないか |
| 食欲 | 急に食欲がなくなっていないか |
| 排せつ | 便の状態が普段と違わないか |
ちょっとした変化も体調不良のサインかもしれません。毎日のチェックを習慣にし、早めの対応で病気を予防しましょう。
食事と栄養管理のポイント
健康を維持するためには、毎日の食事の栄養バランスがとても重要です。関節のケアにはグルコサミンやコンドロイチンが、免疫力の向上にはビタミンやオメガ3脂肪酸が役立ちます。これらの成分を含むフードを選び、バランスの良い食事を心がけましょう。
また、トイ・プードルはアレルギーを起こしやすい犬種のため、食材選びにも注意が必要です。特定の食べ物に反応する場合は、アレルゲンを含まないフードに変更することで症状が改善することがあります。消化にやさしいタンパク質や添加物の少ないフードを選ぶことも大切です。
愛犬の体質や健康状態にあった食事を見極め、適切な栄養管理を行いましょう。
運動・遊び方の注意点
トイ・プードルは活発で運動が大好きな犬種ですが、関節に負担をかけない運動を心がけることが大切です。ジャンプの多い遊びやフローリングでの激しい走り回りは、膝蓋骨脱臼(パテラ)などの関節トラブルの原因になります。滑りにくい床材を敷いた室内でボール遊びをしたり、芝生のある公園で無理のない範囲で遊ばせたりするとよいでしょう。
また、老犬になると筋力が低下し、長時間の散歩や激しい運動が負担になることがあります。年齢にあわせて散歩の距離を短くしたり、段差の少ない道を選んだりする工夫が必要です。軽いストレッチやマッサージを取り入れることで、無理なく体を動かし健康を維持することができます。
定期的な健康診断の重要性
トイ・プードルが健康で長生きするためには、若いうちから定期的な健康診断を受けることが大切です。病気は早期発見・早期治療が鍵となるため、症状が出ていなくても定期的に検査を受ける習慣をつけましょう。
一般的に、1歳〜6歳の成犬期は年に1回の健康診断をおすすめします。この時期は主にワクチン接種や基本的な血液検査を行い、健康状態をチェックします。
一方、7歳以上のシニア期になると病気のリスクが高まるため、半年に1回の健康診断が望ましいです。心臓や腎臓の検査、レントゲンなどを追加することで、早期発見につながります。
トイ・プードルの病気に関するよくある質問(Q&A)

トイ・プードルは体が小さく、関節や目、皮膚などにトラブルが起こりやすい犬種です。病気の症状や治療法について、不安や疑問を抱える飼い主さまも多いのではないでしょうか。
ここでは、トイ・プードルがかかりやすい病気について、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 涙やけがひどいけど、病院に行くべき?
A1.涙やけが軽度で、日常的なケアで改善される場合は、すぐに病院へ行く必要はありません。しかし、目の周りが常にぬれている、赤みや炎症がある、目ヤニが増えているといった症状が見られる場合は、一度動物病院で診てもらうことをおすすめします。
涙やけの原因には、鼻涙管の詰まり、アレルギー、逆さまつげ、細菌感染などが考えられます。特に鼻涙管が生まれつき細いトイ・プードルは、涙の排出がスムーズにできず、涙やけになりやすい傾向があります。
自宅でのケアとしては、目の周りをこまめに拭く、低刺激のフードを試す、アレルゲンを取り除くなどが効果的です。改善しない場合は、早めに獣医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。
Q2. 膝蓋骨脱臼って治るの?
A2.膝蓋骨脱臼(パテラ)は、症状の程度によって治療法が異なります。軽度の場合は、適切なケアを行うことで悪化を防ぎ、日常生活に支障が出ないよう管理することが可能です。しかし、重度の場合は手術が必要になることもあります。
膝蓋骨脱臼は、グレード1から4に分類され、軽度(グレード1・2)の場合は滑りにくい床材を使用したり、適度な運動で筋力を維持したりすることで進行を防ぐことができます。グレード3以上の重度のケースでは、膝の痛みや歩行困難が見られるため、手術による改善が推奨されることが多いです。
早期発見と適切なケアが重要なので、愛犬の歩き方に異変を感じたら、早めに動物病院で相談しましょう。
Q3. シニア犬になったらどんな検査を受けたほうがいい?
A3.シニア期(7歳以上)になると、病気のリスクが高まるため、定期的な健康診断がより重要になります。年に1〜2回の健康チェックを行い、早期発見・早期治療につなげましょう。
シニア犬におすすめの検査は、血液検査、尿検査、レントゲン検査、超音波検査などです。血液検査では腎臓や肝臓の状態を確認し、尿検査では糖尿病や膀胱炎の兆候を調べます。レントゲンや超音波検査では、心臓や内臓の異常を早期に発見することができます。
また、関節のトラブルが増える時期でもあるため、歩き方の変化や痛みの有無をチェックし、必要に応じて関節の検査を受けることも大切です。愛犬がシニア期を快適に過ごせるよう、定期的な検査を習慣にしましょう。
まとめ│トイ・プードルの健康を守るためにできること
トイ・プードルは長寿な犬種ですが、関節や目、皮膚、歯の病気にかかりやすいため、日ごろの健康管理がとても重要です。膝蓋骨脱臼や涙やけ、歯周病などは、適切なケアを行うことで予防や症状の軽減が可能です。
愛犬の健康を守るためには、毎日の健康チェックやバランスの良い食事、適度な運動を心がけましょう。また、シニア期には定期的な健康診断を受けることで、病気の早期発見・早期治療につなげることができます。
トイ・プードルとできるだけ長く元気に過ごせるように、愛犬の様子をよく観察し、適切なケアをつづけていきましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
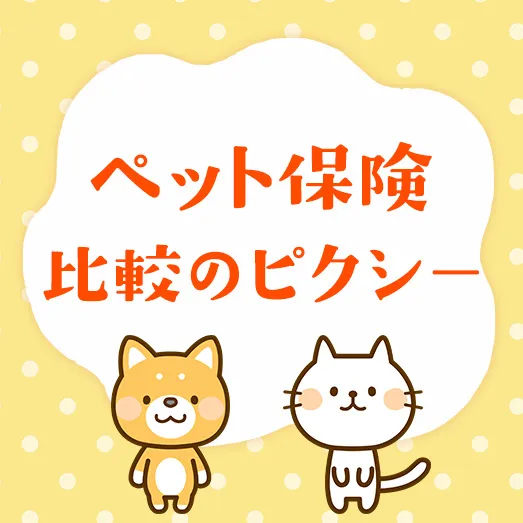
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








