
犬も、人間と同じように便秘に悩まされることがあります。日常生活の変化における生理的な便秘もありますが、なかには重大な病気が隠れているケースも。
そこで本記事では、犬の便秘について以下の点を中心に解説していきます。
- 犬が便秘になってしまうさまざまな原因
- どんな犬が便秘になりやすい?
- 便秘の症状と病院に連れていくタイミング
- 犬が便を出しやすくする方法
愛犬が便秘になっているときにやってはいけないことも合わせて紹介します。
犬の便秘について正しく理解するためにも、ぜひ最後までお読みください。
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
犬の便秘は何日から?判断基準はあるの?
犬の便秘には、明確な判断基準はありません。ただ、2〜3日うんちが出ていない場合は便秘が疑われます。
普段と比べてうんちが小さくコロコロしていたり、いきんでもなかなか出てこなかったりするのは、便秘の症状かもしれません。
子犬のうんちの回数は5回以上になることもありますが、成犬の場合は1日1~2回が一般的です。ただ、生活環境や運動量などによってもうんちの回数は変化するため、1日のうんちの回数に決定的な基準はないのです。
犬がうんちをしない原因は?

犬がうんちをしなくなる原因は、主に以下のとおりです。
- 身体に合わないフードを食べている
- 水分摂取量が少ない
- 運動不足
- ストレスなどによる腸内環境・自律神経の乱れ
- がんやヘルニアなどの病気・排便時の痛みによるもの
それぞれ詳しく解説していきます。
身体に合わないフードを食べている
犬にとって、消化吸収しにくい植物性タンパク質(小麦やとうもろこし)を使ったフードや人工添加物を多く使用しているフードなどが原因で便秘になることがあります。
また、あえて食物繊維の量が多く調節されている体重管理用のフードでも、便秘になる犬もいるため気になる場合は獣医師に相談しましょう。
水分摂取量が少ない
犬の飲水量が少ないと、うんちが硬くなる傾向にあります。
水をあまり飲まなくなる冬や、もともと飲水量が少ない犬は特に注意が必要です。愛犬があまり水を飲んでいないと感じる場合は、ウェットフードを利用して食事から水分を補給させるのも便秘対策の1つといえます。
運動不足
運動不足によって犬が便秘になることがあります。
運動不足によって腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなるのです。また、屋外でうんちをする犬の場合、天候などで散歩のリズムや回数が変わると、それが影響して便秘になってしまうケースもあります。
ストレスなどによる腸内環境・自律神経の乱れ
飼い主が変わったり、引っ越ししたりという環境の変化でストレスを感じ、腸内環境や自律神経が乱れることがあります。
その結果、知らず知らずのうちに愛犬が便秘になってしまうのです。
がんやヘルニアなどの病気・排便時の痛みによるもの
便秘がなかなか改善されない場合は、がんやヘルニアなどの病気が隠れている可能性もあります。
うんちをするときに痛がる、足腰が弱っていて踏ん張りたくても力が入りにくいなどという理由もまた、便秘の原因の1つです。
老犬が便秘になりやすい原因とは?
犬も人間と同様、年を取って高齢になると便秘になりやすくなります。
理由としては
- 消化管(腸など)の機能低下
- 飲水量・運動量の低下
などが挙げられます。それぞれ詳しくみていきましょう。
消化管(腸など)の機能低下
老化により身体機能が少しずつ衰えていくと、消化管の動きは鈍くなっていきます。
そのため、うんちが腸内に長く留まり便秘になりやすくなるのです。
飲水量・運動量の低下
老犬になると、身体の痛みや動かしづらさを感じ、運動量が減少することは少なくありません。
身体を動かさなくなれば喉の渇きも感じにくく、結果として運動量・飲水量の低下による便秘が起きやすくなります。
病気によるもの
腎機能の低下や糖尿病などによって脱水症状が引き起こされると、うんちの水分量が減って便秘になりやすくなります。
犬に多飲多尿の症状がみられたり、おしっこの色が薄いもしくは透明だったりする場合は獣医師に相談しましょう。
便秘になりやすい犬種
便秘自体はどの犬種でもなり得ますが、便秘を引き起こしやすい病気(椎間板ヘルニア、前立腺肥大、会陰ヘルニアなど)の好発犬種は特に注意が必要です。
- ミニチュア・ダックスフンド
- トイ・プードル
- ポメラニアン
- コーギー
- マルチーズ など
前立腺肥大や会陰ヘルニアは、特に中高齢で未去勢のオスがなりやすいとされています。
愛犬がいきんでも、なかなかうんちが出てこなかったり、痛がる様子がみられたりしたら動物病院を受診しましょう。
愛犬が便をしなくなった?動物病院に連れていくタイミングは?

愛犬が便秘になり、以下のような症状がある場合は動物病院の受診をおすすめします。
- 食欲の低下・嘔吐がある
- 元気がなく動かない
- 苦しそうな表情をしている
便秘の原因は、食事内容やストレスなどさまざまです。
うんちの回数や愛犬の状態においていつもと違うと感じたら、できるだけ早めに獣医師に相談しましょう。
愛犬が便秘の場合に自宅できる解消方法
愛犬が便秘になった際に、自宅でできる便秘解消法は以下のとおりです。
- ビオフェルミン(動物用)を与える
- ヨーグルトを与える
- 水溶性食物繊維を含む食べ物を与える
それぞれ詳しく解説していきます。
ビオフェルミン(動物用)を与える
ビオフェルミンは、腸の調子を整える整腸剤です。即効性はありませんが、継続して与えることで腸内環境が改善し、便秘解消に効果を発揮するといわれています。
愛犬にビオフェルミンを与える際は、犬の体重に合わせて量を調節しましょう。
注意点として、初めてビオフェルミンを愛犬に与えるときはしっかり経過観察を行い、異常がある場合は使用を中止して、必要に応じて動物病院を受診してください。
ヨーグルトを与える
ヨーグルトも、便秘解消の食べ物として知られています。
冷蔵庫で冷えたヨーグルトを一気に与えるとおなかが緩くなりやすいため、常温に戻したものを愛犬の様子をみながら少しずつ与えるといいでしょう。
注意点として、乳製品にアレルギーを持つ犬もいるため少量から与えて様子を見て、もしものときのために動物病院が空いている時間帯に与えるようにしてください。
水溶性食物繊維を含む食べ物を与える
水溶性食物繊維は、うんちに水分を含ませる働きがあります。水溶性食物繊維は、りんごやいちごなどの果物に多く含まれているため、こちらも愛犬の様子を見ながら与えましょう。
犬の便秘でやってはいけないこと!
愛犬の便秘を解消してあげたいと思ってしたことが、実は逆効果になる場合があります。
- 自己判断で便秘薬を与える
- 綿棒で肛門を刺激する
- 誤った部位・方法でのマッサージ など
それぞれ詳しくみていきます。
自己判断で便秘薬を与える
自己判断で市販の便秘薬を投与するのはやめましょう。
便秘の原因が何らかの病気だった場合、便秘薬によって病状が悪化する可能性もあります。便秘薬を投与する際は獣医師に相談し、用法用量をしっかりと守りましょう。
綿棒で肛門を刺激する
綿棒での肛門刺激は、肛門や腸を傷つけてしまう可能性があるため避けたほうが無難です。
さらに、綿棒での刺激がないとうんちが出せなくなってしまうおそれもあるため、自己判断で綿棒を用いるのはやめましょう。
誤った部位・方法でのマッサージ
便秘解消のためのマッサージは存在しますが、誤った部位や方法で行うマッサージは逆効果になります。
また、便秘の原因が病気だった場合は病状を悪化させるおそれもあるため、獣医師に相談して正しい方法を知ることが大切です。
まとめ│犬も便秘になる!早めに相談しよう!
ここまで、犬の便秘について解説してきました。
- 犬の便秘は、一般的に2~3日うんちが出なかったときに疑われる
- 犬の便秘の原因は、繊維質の過剰摂取や水分不足、運動不足など
- 犬の便秘を解消するには、適度な運動や水分補給、ヨーグルトの摂取など
- 犬の便秘でNG行為は、自己判断での便秘薬投与や綿棒での刺激、誤った部位・方法のマッサージ
長時間の便秘は、犬にとってつらいものです。便秘の原因を突き止めることで、病気の早期発見に繋がるかもしれません。愛犬のうんちの状態がいつもと違うと感じたら、できるだけ早めに動物病院を受診しましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
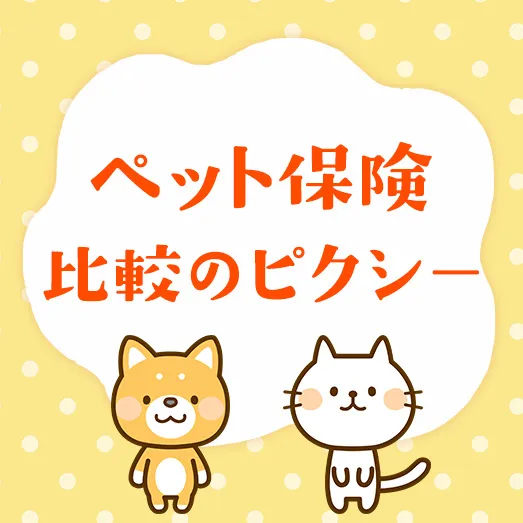
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上









