
小型犬の中でも小さなチワワですが、どんな病気にかかりやすいのでしょうか。初めてチワワと生活する飼い主さまなら、心構えとして知っておきたいですよね。健康的に過ごすためのポイントも、迎え入れる前に押さえておきたいものです。
今回は、チワワに多い病気と健康管理のポイントを紹介します。飼育方法もチェックして、育てる環境を整えましょう。
- チワワの性格や体型などの特徴や平均寿命
- チワワに必要なしつけや散歩について
- チワワがかかりやすいケガや病気
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
チワワの特徴

大きな目と耳が魅力的な、チワワの性格や体型などの特徴を紹介します。
容姿
チワワはアップル・ドームといわれる丸みのある顔が特徴です。くりんとした目が魅力的で、見つめられると思わず頬を緩めてしまう方も多いでしょう。
チワワの被毛はスムースコートとロングコートの2種類です。スムースコートは体に密着しており、ボディラインがはっきりとわかります。一方のロングコートは、風になびくほどのやわらかさと長さが特徴です。耳・首・尻尾には飾り毛があります。
チワワの毛色は、ブラック・レッド・クリーム・ホワイト・チョコが一般的です。柄では、地色に黄褐色の模様が入った「タン」と呼ばれる種類が注目されています。カラーの組みあわせは、ブラックタンやチョコタン、ブルータンなどです。
性格
チワワは好奇心旺盛で、初めて触れるものや場所でも突き進む勇敢な子が多いです。家族には忠実でしつけしやすく、初心者でも飼いやすいでしょう。
その反面、家族以外には警戒心が強い傾向にあります。無駄吠えしないように、小さいうちからトレーニングしましょう。
体型
チワワは平均体高12〜20cm、体重1.5〜3kgと小柄な体型です。世界的に小さいといわれている犬種のひとつで、極小チワワと呼ばれる種類もいます。体が小さいチワワですが、平均寿命は12〜16歳と、極端に短いことはありません。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
チワワの飼育ポイント
性格や被毛の特徴から押さえておきたい、チワワの飼育ポイントを紹介します。散歩の目安も参考にしてください。
子犬期にしっかりしつける
飼い主以外には警戒心が強くて臆病な性格から、周りの犬や人に対して攻撃的な子もいます。成犬になってからしつけるのは難しく時間もかかるため、できるだけ小さいうちにトレーニングしましょう。無駄吠えや行動をコントロールできるように心がけます。
外の世界や家族以外の人・犬も安全だと感じてもらうためには、積極的に外に出て家族以外とふれあう機会を作ると良いでしょう。
子犬のしつけでは、褒めることを意識します。だめなところを見つけてしかるのではなく、上手くできたときに思いっきり褒めてあげるのがポイントです。
定期的なブラッシング・シャンプー
ロングコートの子は、被毛が絡まったり毛玉ができたりしないように、毎日のブラッシングが必要です。とくに、春と秋の換毛期は抜け毛が多いため、丁寧にブラッシングしましょう。抜け毛を取り除くことは、皮膚病の予防にもなります。
シャンプーは月に1〜2回を目安にしましょう。汚れが気になる場合は、部分的に洗ったりシャンプータオルを利用したりするだけでも汚れを落とせます。頻度が多いと皮膚に負担がかかるため、やりすぎも良くありません。
小型犬でも散歩は必要
チワワのような小型犬でも、散歩は毎日必要です。1日2回20分ずつを目安にしましょう。チワワは小柄なため、運動量だけで考えると、室内の運動だけでかまわないと思われがちです。
しかし、社会性を身につけるためやストレス発散のためにも、散歩は必要です。また、社会性を身につけるためにも、散歩は良い経験になります。周りの環境に慣れてきたら、ドッグランを利用するのも良いでしょう。
また、チワワはスキンシップ好きな犬種のため、散歩以外にもふれあう時間をしっかり確保しましょう。スキンシップはストレス軽減にもつながります。
チワワに多いケガや病気は?

小柄なチワワに多いケガや病気を紹介します。
膝蓋骨脱臼(膝関節の病気)
膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)は通称パテラといわれる膝関節の病気です。膝蓋骨が正常な位置から外れることをいい、膝関節を伸ばせなくなります。
内側と外側のどちらにも外れることがありますが、とくに内側に外れることが多いでしょう。先天的な要因と、成長期の形成異常によって発症しますが、小型犬は先天的によるものが多いようです。
脱臼の程度によってグレードがありますが、初期なら外れた足をしっかり伸ばさずに上げたり鳴いたりする様子がみられます。脱臼の程度がひどくなると、うずくまるようにしか歩けなくなるでしょう。
この病気は膝関節への負担を減らすことが重要です。肥満にならないように、適度な運動と体重管理を行いましょう。また、室内の歩行が負担にならないように、滑りやすいところにはカーペットを敷きます。高いところからの飛び降りも避けましょう。
水頭症(脳の病気)
水頭症とは、脳脊髄液の量が過剰になり脳を圧迫し、脳神経組織の機能が低下する病気です。頻繁に見られる病気ではありませんが、発症しやすい年齢や犬種に特徴があります。
先天的な要因だけでなく、後天的な要因で起こることもある病気です。脳の腫瘍や損傷、脳出血によって引き起こされます。
水頭症にかかると、
- よく眠る
- 急に攻撃的になる
- 歩き方が普段と違う
- ひきつけが起こる
など脳に関連する症状が現れますが、気づかないことも少なくありません。しかし、程度によっては死につながる病気のため、早期発見が重要です。
水頭症に明確な予防法はありませんが、普段の行動をよく観察しておくと、初期段階で気づけることもあるでしょう。
気管虚脱(呼吸障害)
気管虚脱とは、気管が潰れて上手く呼吸ができなくなる呼吸障害です。元は難治性疾患とされていましたが、近年は外科手術で完治することもあります。
苦しそうな息遣いをしたり、単発の咳きこみが見られたりするのが主な症状です。明らかに苦しそうな様子がなければ、見逃してしまうような症状のため、気づかないこともあります。
気管虚脱の明確な原因はわかっていません。予防することは難しいため、小さな異変を見逃さないようにしましょう。
僧帽弁閉鎖不全症(心臓の病気)
僧帽弁閉鎖不全症は、とくに老犬の小型犬に見られやすい、血液が逆流してしまう心臓の病気です。初期に目立つ症状はありませんが、進行すると心不全を発症することもあります。この病気は、早期発見できるかが重要です。
初期段階ではわかりにくいですが、疲れやすく眠る時間が増えるなどの症状が現れます。呼吸困難やチアノーゼが現れたときはすでに進行しているため、早急な対応が必要です。
僧帽弁閉鎖不全症は、加齢によって僧帽弁がうまく閉じられなくなることで起こります。有効な予防法はありませんが、よく眠るのは歳のせいだと決めつけずに、ほかに気になる様子がないか確認しましょう。
尿路結石症(腎臓などの病気)
尿路結石症は尿管・腎臓・膀胱・尿道に結石ができ、尿が排泄できなくなったり痛みが出たりする病気です。細菌感染によって起こりやすい病気ですが、食生活が原因で起こることもあります。
血尿が出る、いつもと違うところでおしっこするなど、排尿の異変が主な症状です。体質や程度によっては、吐き気を起こす子もいます。
完全に予防することはできませんが、食事やおやつでミネラルを過剰摂取しないように気をつけることで、引き起こす原因を減らすことは可能です。
角膜炎(目の病気)
角膜炎は、目に異物が入るなどして角膜が傷つくことで起こる病気です。直接的な要因以外にも、アレルギーや細菌感染によって炎症が引き起こされることもあります。目を痛がったり、いつも以上に涙や目やにが多かったりする場合は注意が必要です。
角膜炎は治療しないと失明につながるおそれがあるため、異常を感じたら早めに動物病院で診察を受けましょう。定期的に目に充血やにごりがないかをチェックしておくことで、異変がわかります。
角膜炎はどの犬種でも発症しますが、目の大きい犬種はかかりやすいといわれています。
眼球突出(目の病気)
眼球突出とは、ぶつかるなどの衝撃によって飛び出し眼球がまぶたに締め付けられて、強い痛みや充血を伴う病気です。
見た目でも飛び出ていることがわかりますが、痛みによる以下の様子も現れます。
- じっとして震えている
- 涙が出続ける(まぶたを閉じられないため)
- 触れられるのを嫌がる
犬特有の頭蓋骨の形によって起こりやすい病気です。
低血糖症(血液の病気)
低血糖症は、血液中の糖分が減少することによって生じる、血液の病気です。子犬のころは低血糖状態になりやすいため注意しましょう。糖分の吸収が減少する「供給不足」と、大量に糖分を消費する「消費過多」によって引き起こされます。
子犬のころは体が小さいため、ご飯の間隔があいて空腹時間が多いと、低血糖になりやすくなります。成犬の場合でも、疾患の合併症で起こることもあるため油断はできません。
いつもより元気がない、下痢や嘔吐が続く場合は、低血糖を起こしている可能性があるため診察を受けましょう。低血糖症は重度になると、脱力が進んで昏睡状態になることもあるため、早急に処置が必要です。
子犬のころはご飯の回数を多めにし、空腹の時間を多く作らないようにしましょう。成犬では食事回数に気を配る必要はありませんが、定期検診によって病気を早期発見することで、低血糖症の予防につながります。
足の骨折(ケガ)
犬は、日常生活の中でも骨折することがあります。イスやソファからジャンプしたとき、滑ったときなどに骨折することがあるため、室内環境を整えることが重要です。
着地するときに起こりやすいため、骨折の多い箇所は前足です。特定の足をかばうように歩く、引きずるなどの症状がある場合は、骨折しているかもしれません。動物病院を受診するときは、患部を動かさないようにして連れて行きましょう。
チワワが震えるのは病気?
チワワが震えているのは、病気でないことも多いですが、病気が隠れていることもあります。それぞれの震える原因を確認して、見分けられるようにしましょう。
病気ではない震え
チワワは、ストレスや恐怖を感じているときや、寒さによって一時的に震えることがあります。嫌いなものやストレスになるものを遠ざける、室温を調整することで震えは止まるでしょう。
また、老犬の場合は老化によって手や頭が震えることもあります。原因は明確ではありませんが、病気ではありません。ただし、程度によって薬で対処することもあります。
これら以外にも、震えたときに飼い主さまにかまってもらえた経験があり、わざと震えることもあるようです。
病気による震え
一時的な震えが多い一方で、病気による震えもあります。病気が原因である場合は、震え以外にも症状があります。ほかに変わった様子がないか確認して、病気かどうかを見分けると良いでしょう。
震えが症状としてある病気の一例は、以下のとおりです。
- 中毒
- てんかん
- 腎臓病
- 水頭症
- 低血糖
明らかな震えの原因がわからない場合は、動物病院を受診しましょう。
チワワが健康的に過ごすためには
チワワの健康維持のためには、食事管理が欠かせません。また、健康診断とワクチン接種で、病気の早期発見と予防に備えることも重要です。それぞれのポイントを詳しく解説します。
食事管理
毎日食べるドッグフードは、年齢に合ったタイプを選びましょう。犬は年齢に応じて必要な栄養素のバランスが異なります。年齢にあわせたドッグフードを選ぶことで、その時期の必要な栄養素を摂取でき、健康的に過ごせるのです。
子犬期は空腹の時間を減らすためにも、生後6か月までは1日3回以上に分けて与えましょう。とくに離乳期は1日4回以上が目安です。成犬用のドッグフードを与えるのは、生後8か月以降にしましょう。
成犬期は、子犬期よりカロリーやタンパク質が控えられた成犬用、シニア期は健康維持をサポートできるシニア期用のタイプを選びます。
健康診断
病気を早期発見するためには、健康診断が欠かせません。6か月ごろから成犬期までは年1回、それ以降は半年に1回受診しましょう。検査項目は、血液検査や尿・便検査、レントゲン検査などです。健康状態によってMRI検査などが追加されます。
ワクチン接種
感染症から守るために、ワクチン接種を受けましょう。犬の予防接種には、狂犬病ワクチンと混合ワクチンの2種類あります。
狂犬病ワクチンは接種が義務付けられているため、毎年かならず受けなければいけません。設けられた会場で接種できますが、動物病院でも接種可能です。接種時期になれば案内が送られてくるため、忘れないようにしましょう。
一方、混合ワクチンは任意接種ではありますが、愛犬を感染から守るために年1回受けるのが望ましいでしょう。混合ワクチンには種類がありますが、生活スタイルによって選択します。
室内で過ごすことの多いシニア期なら6種混合ワクチンで構いません。ただし、外出の多い環境の子やほかの犬と接する機会の多い子は、8種もしくは10種混合ワクチンが良いでしょう。
チワワの病気にペット保険で備える

チワワが病気になっても十分な治療が受けられるよう、ペット保険で備えておきましょう。治療費は病気によって異なりますが、高額になるものもあります。
アイペット損保のデータから、チワワが膝蓋骨脱臼で手術した場合の治療費例を紹介します。
| 診療項目 | 金額 |
| 診察 | 800円 |
| 入院(5泊6日) | 15,000円 |
| 検査 | 25,000円 |
| 全身麻酔 | 15,000円 |
| 手術 | 165,000円 |
| 点滴 | 14,400円 |
| 処置 | 10,500円 |
| 注射 | 6,000円 |
| お薬 | 2,300円 |
| 合計 | 254,000円 |
参照:アイペット損保「チワワにペット保険は必要?」
※上記の診療内容・治療費等は参考であり、実際のお支払い例や一般的な平均・水準を示すものではありません。
※治療費は動物病院によって異なります。
別途通院が必要になるケースもあり、ペット保険があると安心です。ペット保険は治療による自己負担を軽減できるため、選択できる治療内容の幅が広がります。
まとめ|チワワの特徴を理解してケガや病気に備えよう
小さな体でどんなことにも好奇心旺盛なチワワの健康を守るためには、適切な食事管理や健康診断・ワクチン接種が重要です。
普段から健康状態をチェックして、変化を見逃さないようにしましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
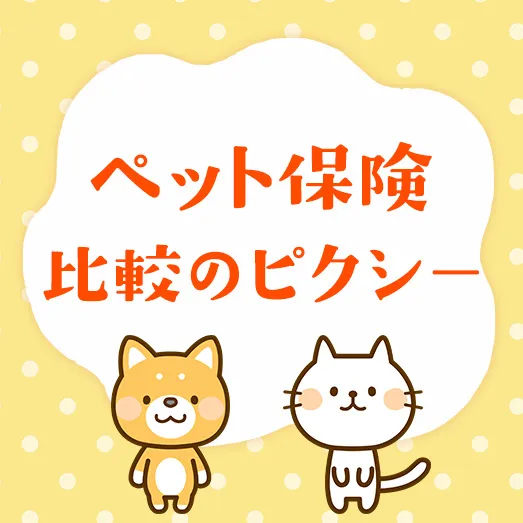
【ペット保険比較】10秒でカンタン比較
あなたの家族はどちら?
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
種類は?
年齢は?
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田犬
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴犬(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上
- スコティッシュフォールド
- マンチカン
- アメリカン・ショートヘア
- ノルウェージャン・フォレスト・キャット
- ラグドール
- ブリティッシュ・ショートヘア
- ミヌエット
- サイベリアン
- ベンガル
- ラガマフィン







