
「シー・ズーを飼ううえで気をつけたい病気や治療法、予防方法は?」
「シー・ズーと快適に暮らすための秘訣は?」
このように、シー・ズーを飼育するにあたって、いろいろと気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、シー・ズーの歴史や特徴、かかりやすい病気、飼い方のポイントなどについて紹介します。シー・ズーと暮らし始めた方や、これから飼いたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- シー・ズーの性格や寿命
- シー・ズーがかかりやすい病気
- 病気の症状や治療法、予防法
- シー・ズーを飼う際のポイント
【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。
まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。
シー・ズーとは?特徴・性格・寿命を解説

シー・ズーはどのような犬種なのか、まずは特徴や歴史、性格を知りましょう。
シー・ズーの体格や毛色、歴史について
シー・ズーはチベット発祥の犬種で、ラサアプソとペキニーズを交配して生まれたといわれています。長毛でかわいらしい顔立ちが魅力的で、中国で「獅子犬」として宮廷で愛されていました。
体格は体重約3.5〜7.5kg、体高約20~28cmの小型犬です。被毛は絹のような質感で白を基調とし、茶やゴールドなどのカラーが混合する場合があります。また、長毛のダブルコートで抜け毛は少ないですが、毛玉ができやすいので日々のケアが大切です。
トリミングは必須ですが、さまざまなカットでそのかわいさを堪能できるのも魅力のひとつです。
シー・ズーの性格
シー・ズーは、基本的に穏やかで人懐っこく、甘えん坊で寂しがり屋な性格をしています。飼い主さま以外の人や犬にもフレンドリーに接することができるうえに、比較的吠えにくいため、初心者でも飼いやすいといえるでしょう。家族への愛情も深く、忠実な傾向があります。
その一方で、頑固な一面ももち合わせています。甘やかすだけではわがままになってしまう可能性があるので、子犬のころからしっかりしつけることが大切です。
シー・ズーの寿命と子犬からシニアまでの健康管理
シー・ズーの平均寿命は12~16歳で、小型犬では平均的、中型犬や大型犬と比べると長生きですが、かかりやすい病気に注意が必要です。
子犬のころから気にかけることが大切ですが、とくにシニア期(7歳以上)になると病気のリスクが高まります。定期的な健康診断を受けるようにしましょう。
ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。
保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。
シー・ズーを飼う際のポイント
シー・ズーを飼う際に必要な管理や生活環境、ケア、しつけのポイントを解説します。
食事管理のポイント
シー・ズーは太りやすい体質なので、食事の管理が大切です。肥満になると、関節の炎症や糖尿病、腎臓病などの病気にかかるリスクが上がってしまいます。
フードは高たんぱくで食物繊維が多く含まれるものなどを選び、おやつは控えめにしたり、低カロリーのものを選んだりと工夫しましょう。市販で販売されているおやつは高カロリーなものが多いので、あげすぎには注意が必要です。
また、シー・ズーは長毛種のため、見た目で肥満度を判断することが難しい場合があります。日ごろからの触れ合いでチェックするのがおすすめです。
運動と散歩の適切な頻度
ストレス解消と運動不足回避のために、毎日の散歩は欠かせません。シー・ズーは太りやすい体質なので、適度な運動は肥満予防にも効果的です。室内や庭での遊びも運動になるので、家庭で遊べる環境を整えてあげることをおすすめします。
また、暑さに弱く体調を崩しやすいため、夏場は朝夕の涼しい時間帯に散歩するなど、熱中症に注意してください。
毛のケアとトリミングの重要性
シー・ズーは長毛犬種で被毛が絡まりやすいため、こまめなケアが必要です。毛玉ができると、そこから皮膚病にかかってしまう可能性があります。毎日のブラッシングで毛玉を防止しましょう。
トリミングの頻度は、1か月に1回程度が目安です。シニア犬の場合は負担がかかってしまうので、2か月に1回程度にすると良いでしょう。
しつけのコツ
頑固な一面をもつシー・ズーのしつけは、根気強く、褒めながら行うことがポイントです。
また、シー・ズーは基本的に人懐っこくフレンドリーな性格ですが、子犬のころから社会性を身に付けなければ過度な怖がりになってしまう場合があります。家族にお迎えしたら、積極的に外の環境に慣れさせ、しっかり社会化させるようにしましょう。
シー・ズーに多い病気

シー・ズーがかかりやすい主な病気の症状や原因、治療法について解説します。病気を発症した際にしっかり対応できるよう、病気について理解しておきましょう。
皮膚の病気
シー・ズーがかかりやすい、皮膚の病気について解説します。
◆脂漏症
この病気は、皮膚が乾燥してフケが増える「乾性脂漏」と、皮膚がべたつく、独特な体臭がするなどの症状があらわれる「油性脂漏」に分けられます。
水分不足や遺伝的体質、内分泌疾患、感染症などが原因とされています。主な治療法は、薬用シャンプーや食事管理です。
◆マラセチア皮膚炎
マラセチア皮膚炎は、犬のなかでもとくにシー・ズーに頻繁に見られる病気です。皮膚の脂が多くなることでマラセチアという真菌の仲間が過剰に増え、発症します。
皮膚の赤みやかゆみが強くあらわれたり、耳の中や内股などが脂でべたべたしたりするのが特徴です。真菌を抑えるシャンプーや、外用薬、内服薬などを用いて治療します。体質が要因になっていることが多いこともあり、根気強い治療が必要です。
◆アトピー性皮膚炎
慢性的なかゆみや皮膚の赤み、皮膚にブツブツができるなどの症状があらわれます。遺伝またはハウスダストや花粉などの環境アレルゲンが原因です。遺伝的要因と環境的要因が絡み合うため治療法には個体差がありますが、主にアレルギー対策や薬用シャンプー、投薬によって行われます。
シー・ズーは皮膚が弱いため、自然治癒任せにしていると免疫力が低下し、細菌感染などでさらに病状が悪化する可能性があります。異常を発見したら、すぐに病院に連れて行くようにしましょう。
目の病気
シー・ズーがかかりやすい、目の病気について解説します。
◆角膜炎
角膜炎はとくに短頭種犬に多い疾患で、角膜が炎症を起こした状態のことをいいます。角膜炎のなかでも、とくに発症率が高いとされているのが潰瘍性角膜炎です。炎症具合によって、表層性角膜潰瘍、実質性角膜潰瘍、デスメ膜瘤、角膜穿孔に分類されます。
逆さまつげや外傷が原因であることが多いとされており、かゆみから目をこする、目に膜がかかったように見えるなどの症状が見られます。
治療は、点眼薬や内服薬を使い分けます。症状が悪化すると外科治療が必要になる場合があるので、早めに受診するようにしましょう。
◆ドライアイ(乾性角結膜炎)
ドライアイ(乾性角結膜炎)は涙の量が不足することで起こり、目の乾燥や充血、痛み、目やにの増加、角膜の濁り、色素沈着などを引き起こします。
とくに短頭種に発症することが多く、進行すると結膜炎や視覚障害につながる可能性が高いです。
治療には原因にあわせた点眼薬や免疫抑制剤が用いられ、長期にわたる管理が必要になることがあります。早期発見が重要なので、異常を感じたらすぐに眼科検診を受けるのがおすすめです。ドライアイの予防は難しく、気付くのが遅く慢性化することがあるため、日ごろから目の健康チェックを行いましょう。
◆緑内障
緑内障は、眼球の内側の圧力が高まることによって視神経にダメージが与えられ、視覚障害が起こる疾患です。
主な症状としては、目の充血、痛み、眼瞳孔が大きくなる、目をしょぼしょぼさせる、目が開けなくなるなどが挙げられます。命にかかわる病気ではありませんが、進行すると視力低下や失明につながる可能性も否定できません。
治療法は、点眼薬を用いた方法が一般的です。点眼薬による治療が見込めない際は、外科的治療が必要になることもあります。
緑内障は、早期発見によって進行を抑えられるとされています。明確な予防方法は発見されていないので、日ごろからよく観察し、何か異常が出たときに気づけるようにしましょう。定期的に目の検査を受けるのも有用です。
◆逆さまつげ
シー・ズーは目が大きいため、逆さまつげになりやすい犬種です。逆さまつげは「睫毛重生(しょうもうじゅうせい)」と「睫毛乱生(しょうもうらんせい)」の、2つの状態に分けられます。
「睫毛重生」は遺伝であることが多く、まつげが内側に生える状態をいいます。また、「睫毛乱生」は傷や感染症、まぶたの構造によって起こり、まつげが眼球に向かって生える状態のことを指します。
どちらも、まつ毛が目に当たり刺激することで目が赤くなる、目やにが多くなる、涙がたくさん出る、目に痛みが出るなどの炎症を起こします。悪化すると、視力低下や感染症につながる場合があります。
抗生物質や抗炎症薬の目薬などによって治療を行いますが、完治するには手術が必要です。予防法として、まつ毛を抜く、切るということもできますが、確実に防ぐことは難しいでしょう。
耳の病気
シー・ズーがかかりやすい、耳の病気について解説します。
◆外耳炎
耳の入口から鼓膜までを外耳といい、外耳炎とは外耳に炎症が起きる病気です。細菌や真菌、ダニ、蒸れ、アレルギーなどのさまざまな原因が重なって発症します。皮膚病のひとつで、シー・ズーのような耳が垂れている犬種や、皮膚が弱い場合はかかりやすい傾向があります。
症状としては、耳が赤くなる、ただれている、かゆがる、頭を振る、液体がたまっている、耳垢が多いなどが見られます。
外耳を洗浄し、点耳薬を使用する治療法が一般的です。初期の進行はゆっくりですが、炎症が起こってから時間がたつほど治りにくくなります。悪化すると中耳や内耳まで炎症が広がり、手術が必要になる場合もあるので、早期発見と治療が大切です。また、慢性化した外耳炎の治療は難しく、長期にわたり根気強く治療を継続する必要があります。
確実に予防するのは困難ですが、耳の汚れが炎症の原因になることもあるので、日ごろからこまめに耳掃除をし、状態を確認してあげましょう。頭を振る、かゆがるなどの仕草がある場合は、早めに動物病院を受診することをおすすめします。
そのほかの病気
ここまでに紹介した以外に、シー・ズーがかかりやすい病気について解説します。
◆短頭種気道症候群
外鼻孔狭窄や軟口蓋過長症、気管低形成などの呼吸器の症状を総称し、短頭種気道症候群といいます。シー・ズーを含む短頭種が発症しやすい病気です。
いびきをかく、ガーガーと音を立てながら呼吸をする、場合によっては、咳や嘔吐などの症状が見られます。暑い場所にいるときや運動後、興奮状態であるときなどに呼吸が激しくなると、症状が出やすくなります。
根本的な治療には外科的な手術が必要で、原因によってさまざまな手術を組み合わせて行われます。そのなかでも、上気道整復術が多く行われる方法です。ただし、手術をしても、再発や術後経過不良、抜管後窒息死が起こる可能性もあります。
加齢とともに進行するケースが多いので、早い段階で治療を行うことが大切です。手術を行う際、短頭種は麻酔による呼吸不全のリスクが高いため、時期や方法などについては獣医師としっかり相談しましょう。
◆僧帽弁閉鎖不全症
僧帽弁閉鎖不全症は、心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁が正常に閉じず、血液が逆流して心不全を引き起こす病気です。
とくに小型犬や中高齢の犬に多く見られ、遺伝的要因も影響します。初期段階では症状がないこともありますが、進行すると咳や呼吸困難、運動時の疲労感などがあらわれます。治療は病状に応じて、食事療法や薬物治療などの内科治療を中心に行います。ただし、内科治療では根治は不可能なので、病気の進行を遅らせることが目的です。
進行していくと、肺水腫や腎不全、肝臓の腫大などが起こります。初期には症状が出ないため、定期的な健診が重要です。早期発見が長期管理の鍵となります。
◆椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、背骨にある椎間板が変性したり破壊されたりして、脊髄神経を圧迫、障害する疾患です。とくに短足犬種に発症しやすい傾向があります。遺伝的な要素も関与しており、若齢での発症が見られることもあります。
症状は痛みが主で、背中を丸める、散歩や階段の昇降を嫌がる、抱き上げると痛がるなどの行動が見られます。症状が進行すると、後ろ足の力が弱まり、最終的には歩行困難や麻痺にいたることもあります。椎間板ヘルニアの重症度はグレード1からグレード5まで分類され、グレードが高くなるにつれて神経障害が強くなります。
治療は症状の重症度に応じて異なります。軽度の場合(グレード1~2)は、痛み止めやステロイド剤の投与、長期間の安静が一般的です。重度の場合(グレード3以上)では、手術が必要になります。術後はリハビリで筋力の回復と神経機能の改善を目指します。
日常的な予防としては、適度な運動と体重管理が重要です。とくにリスクが高い犬種の場合は、高い場所からの飛び降りや激しい運動を避け、背骨への負担を最小限に抑えるようにしましょう。また、定期的な健康診断で症状を早期発見し、適切な対応を行うことが長期的な健康維持につながります。
◆膝蓋骨脱臼(パテラ)
膝蓋骨脱臼(パテラ)は膝蓋骨(膝のお皿)が正常位置からずれることにより発症する、膝関節における疾患です。小型犬に多く、遺伝的要因や外傷によって引き起こされます。
膝蓋骨脱臼の程度によって4つのグレードに分けられます。主な症状としては、足を引きずる、スキップするような歩き方をする、散歩を嫌がる、抱き上げたり触ろうとしたりすると痛がるなどが見られます。
進行度合いに応じて内科的治療や外科的手術が行われます。遺伝が原因であることが多いですが、適切な体重や運動管理、滑りにくい床にするなどの環境の整備で予防が可能です。
定期的に動物病院での健康診断を
愛犬の健康を守り長く生きてもらうため、動物病院で定期的に健康診断を受けるようにしましょう。1歳以上は年1回、7歳以降は年2回が理想です。健康診断を受けることで病気を早期発見でき、治療が可能になります。
まとめ|シー・ズーの健康を守るために

シー・ズーは、皮膚・目・呼吸器系の病気にかかりやすいため、日々のケアと健康管理が大切です。とくに、食事管理・適度な運動・定期検診を徹底し、愛犬が元気に長生きできるよう心がけましょう。
万が一治療が必要になった場合に備えて、早い段階でペット保険に入っておくことをおすすめします。加入条件や補償範囲、付帯サービスなども含めて判断して選びましょう。
【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。
また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。
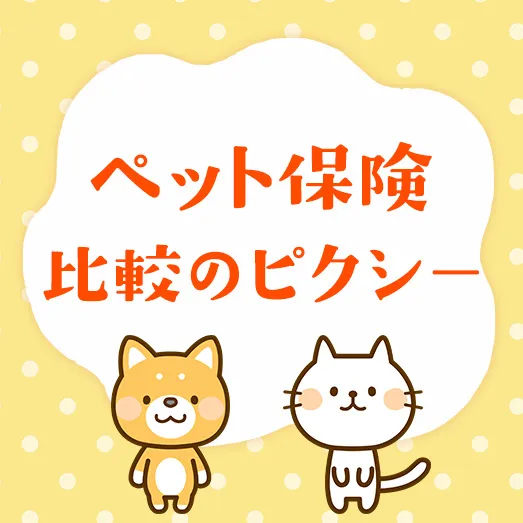
 イヌ
イヌ ネコ
ネコ
- 血統種
- ミックス
-
- 0歳
- 1歳
- 2歳
- 3歳
- 4歳
- 5歳
- 6歳
- 7歳
- 8歳
- 9歳
- 10歳
- 11歳
- 12歳
- 13歳
- 14歳
- 15歳
- 16歳
-
- トイ・プードル
- 秋田
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- ゴールデン・レトリーバー
- シー・ズー
- 柴(小柴・豆柴も含む)
- ジャック・ラッセル・テリア
- チワワ
- パグ
- パピヨン
- ビーグル
- フレンチ・ブルドッグ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラブラドール・レトリーバー
- その他犬種
- 6kg 未満
- 6kg以上 8kg未満
- 8kg以上 10kg未満
- 10kg以上 12kg未満
- 12kg以上 16kg未満
- 16kg以上 18kg未満
- 18kg以上 20kg未満
- 20kg以上 25kg未満
- 25kg以上 30kg未満
- 30kg以上 32kg未満
- 32kg以上 40kg未満
- 40kg以上 45kg未満
- 45kg以上








